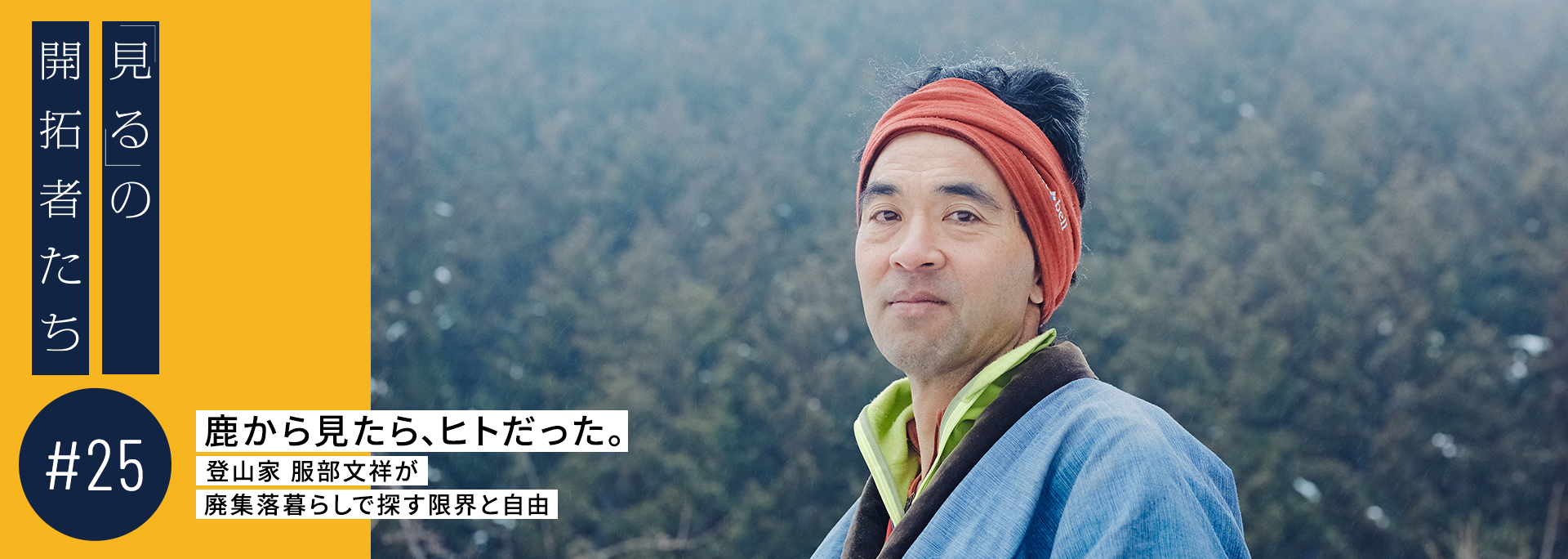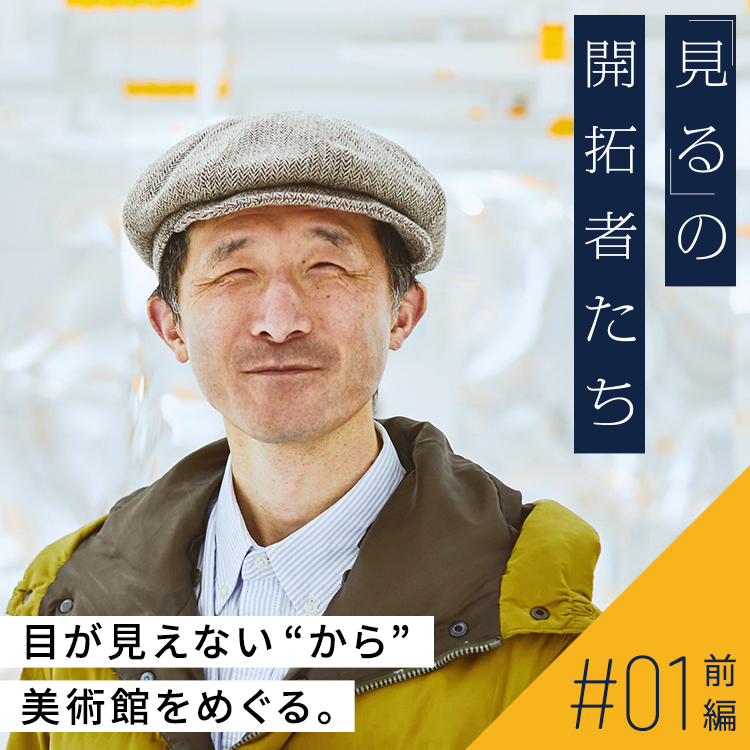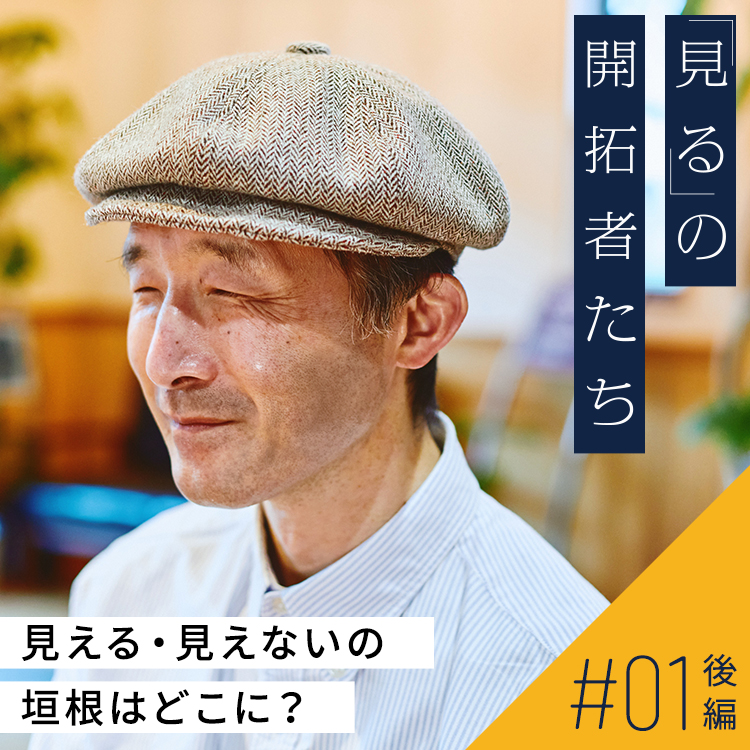僕らはふだん、システムの中を生きている。
「システム」というのは、たとえば価値を可視化して保存したり交換したりするお金がそうだし、車や自動車、飛行機などを使って速く、遠くまで移動できる交通システムがそうだ。あるいは水道、ガス、電気。スーパーに並ぶ商品。インターネット。教育システムとしての学校。広い意味で言えば、先人のつくったあらゆる道具がシステムであると言っていいのかもしれない。
システムは素晴らしい。再現性があり、ゼロから自分でやるより圧倒的に効率がよく、ラクだ。速い。スキルがなくてもそれなりにうまくやれる。そのことについてあらためて考える必要がない。その分のリソースを別の何かに割くことができる。
しかし、そんなシステムに身を委ねることに疑問を持ち、システムの外に出ようとする人もいる。たとえば、今回訪ねた服部文祥さんもその一人ではないだろうか。簡素な道具だけを背負い、食料も現地調達し、道なき道を登る「サバイバル登山」の提唱者であり、実践者。「狩猟」を行い、食料を確保するのに、獣の命を奪うところから自分で引き受けている。さらに数年前には、山奥の廃村(場所は非公開)の古民家を買い取り、時間をかけて改修。愛犬のナツを除けば、たった一人で「自給自足」の暮らしを送っているという。

今回の取材テーマは、そんなふうにしてシステムの外に出た人が何を見ているのか。現代の都市生活がその目にどのように映るか、だ。おそらくは、僕ら自身が試される取材になるだろう。
車一台がやっと通れる細い林道を抜け、急にひらけた雪の傾斜地に、ポツンとあった木造二階建ての一軒家。車のエンジン音を聞きつけ、中からすらっとした男性が姿を見せた。服部さんだ。
促されて僕らも中へ。ストーブに薪を入れると、部屋はすぐに暖かくなった。ちゃぶ台の上を片付け、人数分の座布団を並べ、「ちょっと薄いかもしれないけれど」と言ってお茶を出してくれた服部さん。勝手に気難しい世捨て人を想像していたけれど、意外に歓迎してもらえているのだろうか。著書やメディアで描かれるラディカルな思想家・実践者の姿と、目の前にいる人にはギャップがあるように感じた。

歩く旅が生きる速度を教えてくれた
そもそもなぜ、服部さんはシステムから外れた自給自足の暮らしをしているのか——。いきなり強い思想が返ってくるかも。僕らはそれに耐えられるだろうか。身構え、恐る恐る質問をした僕らはしかし、返ってきた答えにいささか拍子抜けさせられた。
「暇つぶしではないけれど、もう効率よくお金を稼ぐ必要もなくなって、人生やることがないんですよ。子どももほぼ自立してしまったから。そうなると企業に所属している必要がない。だから(家族が住む)横浜にいてもやることがない。もともと田舎暮らしには憧れもあったので、それでこんなことを始めた。おもしろいことがないんですよ、これくらいしか」

逆に、ここに来れば毎日おもしろいことにあふれているのかと思いきや、そういうことでもないらしい。
「おもしろくない。めんどくさい。都会にいるよりマシというだけ。何が面倒って、まず薪集め。風呂に入るのにも、ガチャガチャと薪を入れて、火をつけて、沸くまで30分から1時間。横浜にある自宅に帰るたびにすげえなって思うよ。スイッチ一つで風呂が沸くんだから。(自給自足の暮らしは)最初のうちはおもしろいかもしれないけど、日常になったら、どうしたってめんどくさいが先に立つ」
一息でそこまで言った服部さん。「ただ……」と、返す刀で言葉をつないだ。
「スローライフとはよく言ったもので、田舎の暮らしのゆったりとしたテンポのほうが、人間には合っているとも感じる」
服部さんがテンポ、スピード感について考えるようになったのは、「歩く旅」を始めたことがきっかけだった。たとえば、2019年末には約3カ月にわたり、北海道の山と山をつなぎ、歩き続ける旅に出ている。そういう旅をしていると「遠い未来のことを考えなくなる」のだという。
「人間が一日に歩ける距離には限度がある。どんなにがんばっても40キロ、荷物を背負っていれば20キロが現実的だ。そうすると、50キロ先のことを考えても仕方がない。明日のことは明日考えればいい、となる。しかしその分、その時その時のことは深く考えるようになるんだよね。思考がクリアになって、景色は霧が晴れるように、色鮮やかに立ち現れる」
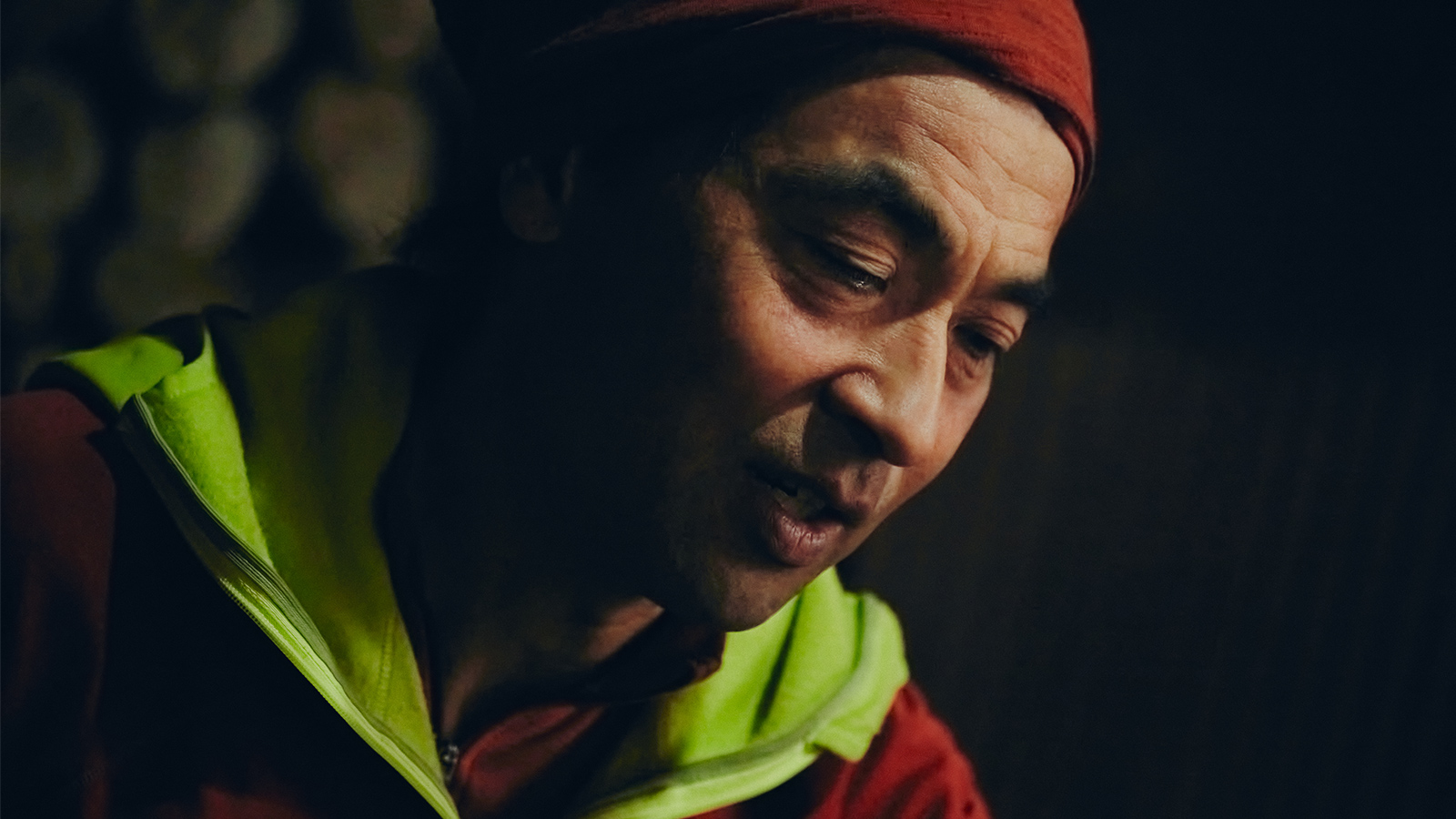
そういう思考が人間本来の思考のあり方だったのではないか。生物ごとに、サイズとか歩行速度に合った思考のあり方があるのではないか。そう服部さんは言う。車、飛行機、そういう移動速度を手にしたことで、人類はそれを失ってしまった可能性がある。速く、遠くに移動できるようにはなったが「その分、存在や思考のあり方は、薄っぺらく引き延ばされてしまったんじゃないかな」。
今の服部さんの暮らしは、基本的に徒歩圏内で成り立っている。不耕起無肥料の菜園で採れる野菜や、自ら撃った鹿の肉を食べて過ごしている。米や調味料は買ってくるのだが、10日〜2週間に1回、歩いて町へ下り、米を担いでくれば生活が成り立つ。
そういう徒歩圏内の生活をしていると、自然と身の回りをたいせつにするようになるのだという。
「畑をやるんでも、自分が食べるわけだから農薬なんて使わない。そのあたりを歩いている鹿が食べて毒になるようなものがないか、気をつけるようにもなる。そうやって身の回りをたいせつにすると、そこからの恩恵で、また自分の生活が豊かなものとして成り立つ。そういう好循環が回りだすんです」

ひるがえって都市の生活はどうか。「先日横浜に帰ったときには、柿が気になったな」と服部さん。
「どの家も庭の柿が落ちるのに任せている。それでいて外からバナナを買ってきて食べている。柿よりバナナの方がうまいのかもしれないけど、二重三重の無駄が起きている。でも、これは田舎でも同じ。駆除目的で鹿を撃ち、そのまま放置する人も多い。俺からすれば信じられない。それでいてオージービーフを買ってきて食べている」
バナナを食うのもいい。牛肉を食べるのもいい。それは否定しない。だが、それはプラスアルファであって、基本は徒歩圏内の暮らしというのがいいのではないか。遠く向こうのことばかり考えて、足元のことがおろそかになってはいないか。服部さんはそう僕らに問いかける。

「自分の目で見ること」は責任である
都市にいながらにして、そうした速すぎるテンポにあらがうことは難しいと服部さんは言う。なぜか。社会や会社が許さないからだ。
「絶えず追い立てられているから、自分の意思でちょうどいい暮らしを選ぶことができない。自分はサラリーマンが長かったからそう感じるのかもしれないけど。でも、自営業でもおそらく同じだろうね。飲食店が自分のペースに合わせて店を開けたり閉めたりしようものなら、たちまち客は遠のいてしまう」
さらなる問題は「システムの中にいる一人ひとりの振る舞いが、本人も意識しないうちに、そのシステムを強化すべく働いてしまうことだ」と服部さんは続ける。
「それを最近は自己家畜化(self domestication)と呼ぶらしい。若いころは自覚していなかったが、自分はそれを嫌だと感じる気持ちが人より強かった。だからこういう人生を送ってきたのかもしれない」

実は、こんな人里離れた場所に住んでいながらも、服部さんはこうしたシステムと完全に決別しているわけではない。かつては便利な移動システムを利用して世界中で山登りを楽しんできた。今もソーラーパネルで発電し、バッテリーに蓄電した電気でWi-Fiを動かし、YouTubeでサッカーのプレミアリーグのハイライトを見て楽しんでいる。引き続き雑誌『岳人』の編集員を務め、複数の媒体で原稿を書き、原稿料というかたちで現金収入を得ている。「半ば不本意ながらも年金は払い続けていて、あと10年もすればそれを受け取ることにもなる」という。
だから偉そうにいろいろ言える立場にはないのだ。そう言って自分にも矢印を向ける服部さんはどこまでもフェア。だが一方で、主たる問題意識は、システムを使うか否かではなく、「家畜状態」にあることに向けられているのが伝わってくる。
「自覚しているかどうか、ということだと思う。無自覚にシステムに乗っていくのではなく、自分の意思で、必要なときにだけ使わせてもらう。自分にとっての生きるとは何か、存在とは、システムとは何かを自覚する。その上で、むしろ自分から積極的にシステムを利用するくらいがいいんじゃないかな」

僕らが服部さんを訪ねたこの日は先客がいた。大学時代の友人夫婦だという。
僕らが到着したちょうどその時、二人は縁側で鹿を解体していた。服部さんが撃った鹿だ。半年に一回くらいの頻度で服部さん宅を訪れ、自分たちで鹿肉を解体し、首都圏の家に持って帰るのだという。吊るされた鹿は頭だけ残して肉が削ぎ落とされていた。縁側には生首が三つ並んでいた。皿の上に山積みになった骨はナツの食事だ。
僕らも日々肉を食べる。ほとんどの場合、それはスーパーで買ってきた肉だ。誰かが牛なり豚なりを育て、殺し、解体したもの。それが運ばれてきて店に並んでいる。命をいただく上での大部分の工程を見知らぬ誰か、あるいはシステムに代行してもらっている。
服部さんは自らの手でそれを行う。命を奪うところから自分で引き受けている。それが狩猟だ。狩猟もまたシステムへの反抗と言えるだろう。

服部さんに言わせれば、鉄砲を持って一方的に殺戮しその命を喰らっているという意味では獣と対等な関係を結んでいるなどとはとても言えないという。だが、服部さんは自分の足で歩き、自分の手で殺し、自分で解体して、その肉を食っている。その一部始終を自分の目で見ている。そこに僕らとの決定的な違いがある。
「自分のやっていることを自分の目で見る。目で見るというだけでも、ほんの少しだけど責任を果たしていると思うから。そう、責任だ! 見ることは責任。うん、JINS的じゃん。もちろんそれですべての責任を果たしているとは言えないんだけど。でも大事なことなんじゃないかな」

鹿の目を借りて、服部文祥はヒトになった
服部さんにとって、山登りはもともと自己表現の手段だった。
「憧れていたのはミケランジェロ、運慶、ダヴィンチのようなアーティスト。でも自分にはその才能がなかった。それで代わりに選んだのが山登りだった。自分は人よりうまく山に登れた。人よりうまくやれるというのは最高の自己顕示だと思うから。数ある表現行為の中でも山登りは特殊だよ。この社会に命を懸けていいとされていることは少ない。基本的には寿命以外で死ぬことはよくないとされている。そんな社会にあって、登山だけはまだ命を懸けることが許されている」
命を懸けた自己表現はおもしろい。世界が色鮮やかに見えるのだと服部さんは言う。
「死が近くにあるって気づいたとたん、感情がたかぶって、くだらないドラマを見ても泣けてくるんだ」

しかし、服部さんにとっての山登りの位置付けは、徐々に変化しているようだった。ひとつは、狩猟との出会いによって。
「狩猟をすると、いろいろなものの見え方が変わる。足元を見ているだけでは鹿は撃てないから、自然と周りを見る。足跡、糞、喰み跡。さまざまなものが浮かび上がり、山を面で見るようになる。最後に雨が降ったのはいつか。この後いつ降るのか。空間的にはもちろん、時間的にも厚みを増す。そうして鹿の気持ちになって考える。最初は図鑑的な情報から入るんだけど。だんだんと、鹿だったらどう振る舞うかを考えるようになる。そのほうが鹿が獲れるから」
おもしろいのは、そうやって鹿の気持ちになって考えているうちに、自分という人間が個から種になったことだ、と服部さんは続ける。
「鹿の目線に立って周りを見渡す。その視界に映ったのは、赤い服を着て鉄砲を持った、身長175センチのホモ・サピエンスだった。自分から見た鹿は鹿でしかないように。鹿から見た自分は服部文祥ではなく、ヒトだった」

そうすると、ものの見え方が変わった。揺るぎなかった自分の考え方、価値観が揺さぶられた。
「たとえば、それまでの自分は『女性や子どもに単独猟は無理だ』と言っていた。狩りも解体も力仕事だし、撃った鹿を山の中から運び出すのには体力がいるからね。逆に、自分は若いころから山ではかなり強い存在という自負もあった。ところが、それはあくまで人間社会の中での比較で、ほかの動物と比べれば同種間の違いなんてないに等しい。そういう視点に立ってあらためて考えてみれば体力なんて程度の差で、重くて1回で運べないなら、2回、3回に分けて運べばいいだけの話。たんに出来高の問題だった。鹿の目線になることで、そういう今までの自分の基準が揺れて、世界の見方が変わっていったんです」
世界の見方が更新された結果、以前ほど自己主張もしなくなったという。
「それまでの自分は、俺は人より山に登れるんだ、サバイバル登山だ、俺が服部文祥だと自己主張しまくっていた。でも、獣に囲まれた生活でいくら自己主張をしても仕方がないから。まあ、そうは言っても、ほかの人から見れば今もけっこう主張しているのかもしれないけどね」

目線を変えることは、価値観が変わるきっかけになる。振り返れば、26歳でK2に登った時もそうだった。
「ヒマラヤ登山なんて、ものすごくお金かかるからね。経済格差にものを言わせて山に登る自分たちの姿が、地元パキスタンの人たちの目にどう映るのかが気になった。そこから登山との向き合い方が変わった。国内の山に登るようになったし、フリークライミングをするようになり、その2年後にサバイバル登山を始めた。そこから狩猟、そして今の生活へと続いている。
K2に登ったとき、自分の目線は国境を越えた先で出会った人たちの目線に移った。今はそれがさらに種を超えて鹿の目線からホモサピエンスとしての自分とか人間社会を見てる、ということなのかな」

自分の限界を知りたい。知りたいことは、もうそれぐらい
命を懸けた自己表現を追求してきた服部さん。今も引き続き命のやりとりをし、生きるために必要な食べ物を自ら調達しているわけだが、この生活の中に「死ぬかもしれない」と思う瞬間はないという。以前のように命を懸けた登山に身を投じ、ヒリヒリするような刺激が欲しくはならないのだろうか。服部さんの答えは短く、はっきりしたものだった。
「(そういう刺激を求める気持ちは今も)ある。だが、できない」

できない理由は、54歳という年齢だ。
「身体が昔のように動かない。そうすると、同じように命を懸けたところで、得られる刺激は小さくなる。以前と同じことはなんとかできても、リスクにみあう新鮮な快楽は得られない。それではたいせつな命を懸けようとは思えない」
狩猟を通し、獣の命と向き合う生活、あるいは命を落とす危険のあるナツを傍に抱えることで、かつて感じていた刺激に近いものを得て、満足しようとしているのかもしれないね。服部さんはそう言って、横で寝そべるナツの首筋を優しくなでた。

猟に出ない日はほぼ毎日、午前中はパソコンに向かって原稿を書いている。こんな田舎にいながら、締切に追われる日々を送っているのだという。「そんなものに縛られない生活が理想ではある」。であるならば、なぜ完全なる自給自足の暮らしに振り切らないのか。僕らがイメージする服部文祥なら、そうしそうなものなのに。取材も終盤、ずっと気になっていた質問を思い切ってぶつけてみた。ここでも服部さんの答えは明確だった。
「だって怖いじゃん。現金を得るための手段を失うのは怖い。社会と断絶して、仙人みたいになるのも怖い」
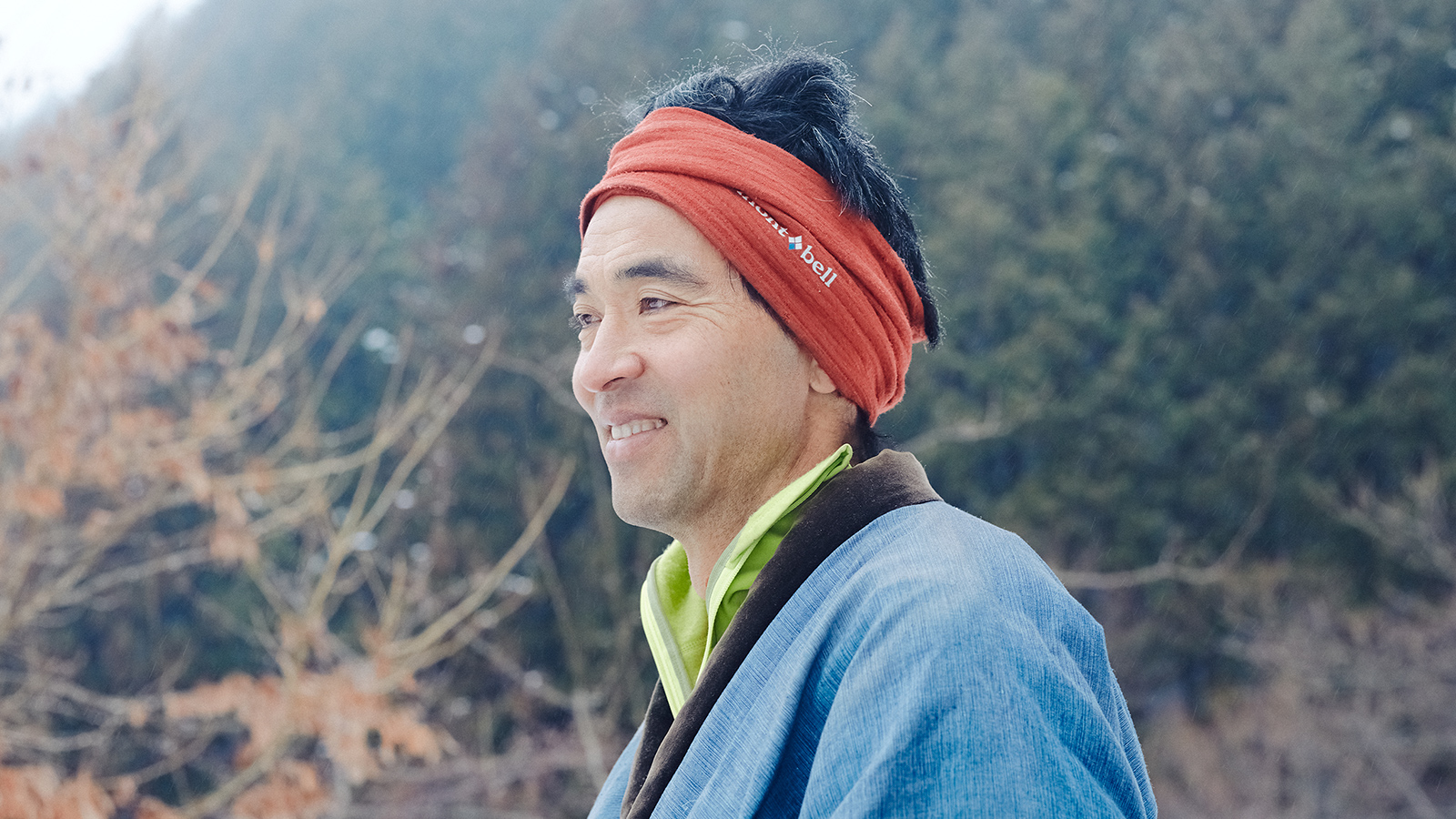
命を落とす危険と隣り合わせの生き方をしてきた服部さんが「怖い、怖い」と続けて口にしたのには驚いた。と同時に、そのバランス感覚は僕らとの距離をぐっと縮めるものでもあるように感じた。完璧でなくていい。白黒はっきりする必要などない。あの服部文祥でさえそうなのだから。
しかし、そんな僕らの不用意な接近に釘を刺すように、このような形の暮らしになっているのは決してバランスを取った結果ではない、と服部さんはあらためて強調した。
「理想と現実のバランスを取っているつもりはない。加齢という肉体的な理由。怖いという感情的な理由。そういう理由があるから理想通りにはいかない、というだけ。外から見たらバランスを取っているように映るのかもしれないけど。……要するに、これが今の自分の限界なんだ」

なぜこんな生活をしているのか——。冒頭の問いへの答えも、ここにあった。「こういう生活をして自分が何を感じるのか。そもそも耐えられるのか。それを知りたいんだ」と服部さんは言う。
「社会システムの外に出る分、ここでの生活にはどうしたって限界がある。自分は自分の限界を知りたい。逆に言えば、知りたいことがもうそれくらいしか残っていないんだよ」
なぜ、そうまでして限界を知りたいのだろう。「それは自由を感じたいからだ」と服部さんは続ける。自給自足のここでの暮らしは、確かにめんどくさいことばかりだ。僕らから見ればそれは縛り。あまりにも不自由な暮らしに見える。だが、服部さんはここでの生活に「確かに自由を感じている」という。
「自由とは何か。それはそのとき、その環境での自分の能力を全部発揮できている状態のことだろう。ところが、自分の能力を全部発揮するとは、すなわちそれが限界でもある。限界というと不自由に聞こえるけれど、実際はそうじゃない。すべてを出し尽くした本当の限界にこそ、本当に本当の自由があるんだ」
だから服部文祥はシステムの外に出る。そうして今日もまた自らすすんで「めんどくさくて、大しておもしろくもない」生活に身を投じるのだ。

【プロフィール】
服部 文祥(はっとり ぶんしょう)
1969年、横浜市生まれ。94年、東京都立大学フランス文学科卒業。山岳雑誌『岳人』編集員として活躍するかたわら、これまでに世界第2位の高峰K2(8611m)登頂や剱岳・八ツ峰北面、黒部別山東面の初登攀といった実績を重ねてきた。99年からは長期山行に装備と食料を極力持ち込まず身一つで挑む「サバイバル登山」を実践している。2022年に史上初の積雪単独北海道分水嶺ルート連続踏破を達成し、植村直己冒険賞を受賞。著書に第5回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞した『ツンドラ・サバイバル』(みすず書房)、第31回三島由紀夫賞候補作『息子と狩猟に』(新潮社)など。