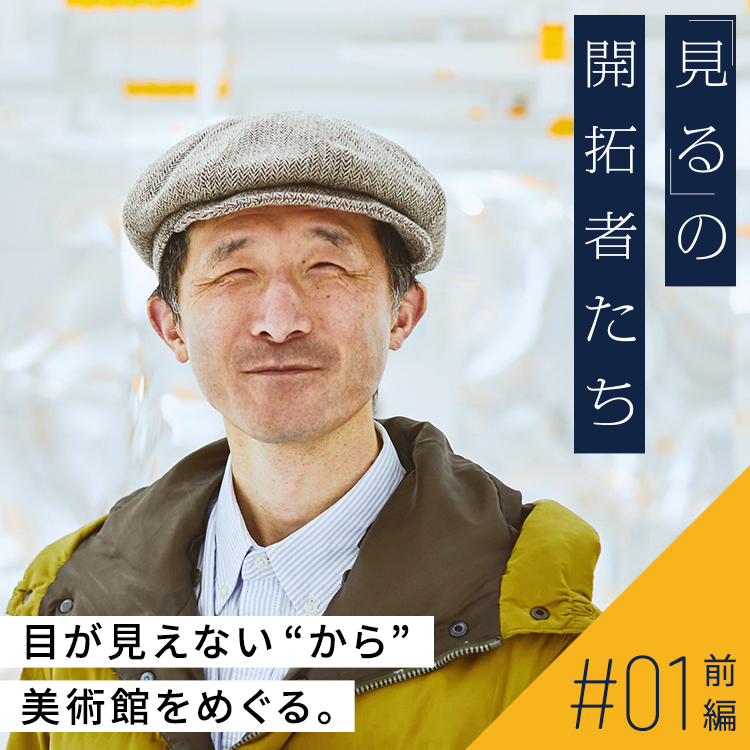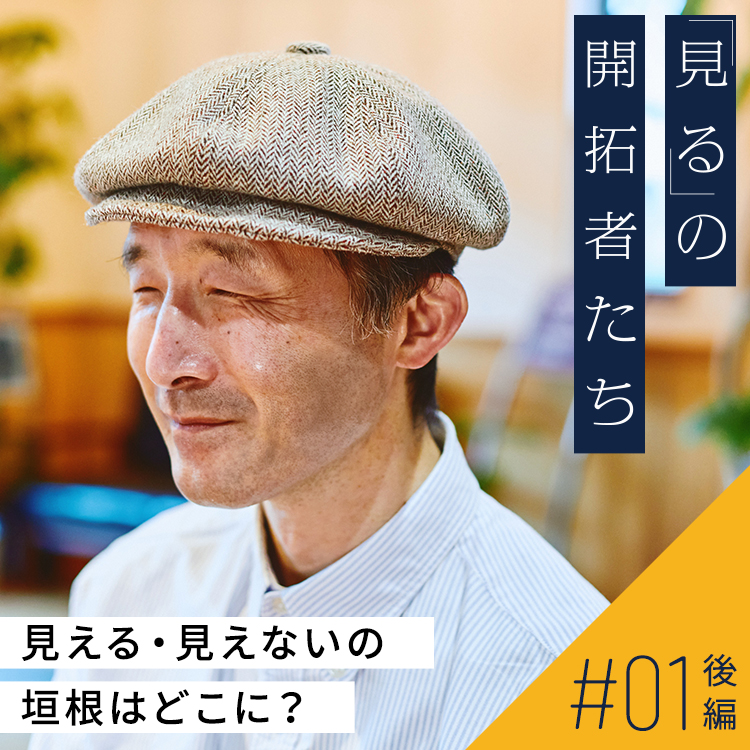キャパはおよそ800人あまり。『マームとジプシー』の代表作として知られる『cocoon』の上演を前に満員となったさいたま芸術劇場大ホールは、作品への期待からかただならぬ熱気と少々浮き足立つような空気に包まれていた。しかし幕が開き、役者が口を開いた途端、ホールにピリッとした緊張感が走る。
「ここは2022年。だれしもに席は用意されている。そのまえとそのあとは、あのとき隔てられた——」
この作品は、1945年、地上戦が展開された沖縄が舞台となっており、戦争に翻弄されながら生きた「ひめゆり学徒隊」の少女たちに着想を得て描かれている。看護隊として動員される以前の少女たちの賑やかな学園生活を象徴するような「いっせーのせ」という掛け声。だが、物語が進むにつれて、少女たちは残酷な世界に飲みこまれ、ひとり、またひとりと、その生命を終えてゆく。そんな惨劇の中でも、執拗に繰り返される「いっせーのせ」。それは、かつての平和な日常の記憶にも見えるし、決死の掛け声にも見えてくる。

写真:岡本尚文
藤田さんの作風は、「普通の演劇」とは大きく異なっている。
劇中、聞こえてくるのは沖縄でフィールドレコーディングされた、77年前と変わらないであろう自然の音。一方向にストーリーが進むのではなく、まるでポップスのサビのように印象的に繰り返されるセリフやシーン。ドラマのようにナチュラルな演技で感情移入させるのではなく、体力の限りを尽くして走りまわり息も切れぎれに切実な言葉を叫ぶ役者の姿。場面は極力暗転せず可変するフレームによって展開され、BGMも役者自身の手で鳴らされる。舞台を彩るすべての要素が、目の前で一気に起こり、観るものを魅了するのだ。
「いっせーのせ」
駆け巡る少女たちの声は、折り重なるたびに、舞台上にはちきれんばかりのエモーションを充満させていった。
フィクションにしか込められない「祈り」
『マームとジプシー』の舞台は、決して万人にわかりやすいスタイルではない。けれども、その作品は「実験」に満足するのではなく、幅広い観客に届くエンタテインメントとして昇華されている。『cocoon』という演目が生み出す感情は、多くの観客の心の奥深くへと突き刺さり、上演中も周囲の席には涙する人の姿がみられた。
2013年に初演された『cocoon』は、10年代の日本の演劇シーンを代表する演劇作品として再演が重ねられ、これまでにのべ16,000人以上もの観客を魅了してきた。いわゆる「芸能人」を起用していないにも関わらず、ここまでの規模の成功を収める演劇作品はごくわずか。しかし、藤田さんは『cocoon』に対してある「葛藤」を抱いていたと話す。

「演劇が持つ芸術性も、もちろん自覚していますが、同時に演劇というのはやはりエンターテインメントでもあると思うんです。過去に起きた出来事を知ってもらったり、そのことについて深く考えてもらうことだけを目的とする場ではなく、舞台を観にきてくれたみなさんの時間を借りているわけだし、一人ひとりにここに来れてよかったと思ってもらえるかどうかもたいせつですよね。だから当初、『戦争』という本当にあった出来事をモチーフとして扱うことに、戸惑いもありました。演劇という媒体で、実際に戦争で犠牲となった方々をモデルに『表現』するってなんなんだろうな、って」
なぜ歴史をフィクションとして伝えることが必要なのか? フィクションが事実をねじ曲げてしまうのではないか? 表現者として真摯に歴史に向き合うからこそ生まれる藤田さんの葛藤。しかし彼は、戦争という圧倒的な現実と歴史に敬意を払いながらも、フィクションが持つ独自の可能性を信じているという。
「戦争という史実を知りたければ、図書館に行って調べたり、資料館や戦跡へ足を運んで『沖縄戦ってこういうことだったんだ』と、見ていったほうがいいと思うんです。けれども、その当時、その場所に生きて暮らしていたそれぞれの人たちが持っていた感情は、史実の中で埋もれてしまっているものも圧倒的に多い。
もしかしたら、こういうこともあったかもしれない、こう思っていた人もいるかもしれない、という想像でしか補えない部分や史実の中で忘れ去られてしまうような些細なことをすくうためには、フィクションしかないと思うんです。そういう小さな声や、消えてしまいそうな存在を『忘れないでほしい』という祈りのような気持ちを抱きながら、この作品を製作しています」

視線が交わり想像が生まれる。想像が重なって演劇は生まれる
「祈りみたいな気持ち」を通じて届けたいもの。それは、決して藤田さん自身の「主張」ではないという。
舞台上を駆け回る少女たちの姿を、彼は「過去」のものとして描こうとはしないし、「反戦の象徴」として描くこともない。白い衣装に身を包んだ彼女たちは、現代に生きる私たちと何ら変わらない姿で舞台を駆け巡る。
「『これが世界、これが戦争です』って一方的に主張するのは演劇の役割じゃないと思っていて。それよりも、舞台上で展開される言葉や運動から、観客のみなさんが何かのヒントを拾ったり、新しい観点を見つけたりする。それが演劇の果たす役割なんじゃないかな。
コロナ禍をどうしようもなく過ごしてみて、以前は普通だと思っていた演劇表現が成立しなくなったように思うんです。作品をただ上演するだけでは演劇は成立しない。観客のみなさんが現実におけるいろんなハードルを越えて『この作品を観たい』『劇場に足を運びたい』と思ってくれるから、客席という空間が成立する。そして、舞台上から放たれるキャストからの視線と客席に座って舞台を見つめる観客のみなさんの視線がぶつかった瞬間に、はじめて演劇が成立し、生まれるんだと思う」

コロナ禍は、演劇において必須の前提である「観客が集う」ことの意味を大きく変えた。これまで当たり前だと信じられてきた観客が集うこと。実は、それが奇跡のようなバランスによって成り立っているという事実に気づいたとき、演劇は、舞台上で行われる一方通行の「コンテンツ」ではなく、舞台と客席とがぶつかりあった瞬間に生まれる「現象」へとそのあり方を変える。
だから、藤田さんは観客を信頼する。
観客はメッセージを受け取るだけの受動的な存在ではない。過去と現在が入り交じる複雑で抽象的な時間構成であったとしても、動き、声、ひかりなど舞台上のあらゆる要素からヒントを拾いあげ、一人ひとりの物語を構築することができるはずだと、藤田さんは信じている。
「演劇って、たとえば大手アパレルブランドのような媒体ではないんですよね。何万着ものお洋服を一気に届けられるような類いの。客席にいるせいぜい何百人かのお客さんにしか届けることができない。だからこそ、マームとジプシーは『こう着れば着こなせますよ』と、着方をわかりやすく提示するのではなくて、どちらかというとかたちも曖昧で、ぱっと見た感じでは着方もわからないような服を扱っているお店でありたい。固定観念を植え付けるのではなく、自由に着こなしてほしいんです。『こうも着れるし、ああも着れる』というふうに想像を重ねていくことが、演劇の醍醐味なんじゃないかな」

子どもの視点で思い出す、世界の本当の姿
『cocoon』に限らず、藤田さんが手掛ける作品には、いつも子どもたちが登場する。大人になりきっていない彼らが語る言葉の切実さ。いつも子どもの目線から世界を作り上げていく藤田さんの背景にあるのは、子どもの視線が見つめる「世界のわからなさ」だという。
「僕自身『大人』や『世界』のことなんてわかっていないし、おそらくまだ『子ども』なんです。リュックにはいつも積み木が入っていますしね」そう笑いながら、藤田さんは言葉を重ねる。
「子どもの視点からは、大人がつくったこの世界って、どうしたってまだわからないものだと思うんですよ。『cocoon』であれば、ひめゆり学徒隊の少女たちは、たまたま戦争へ向かうムードの国に、偶然産み落とされて、この世界には色んな側面があるだなんて知らずに、ただ目の前に広がる悲惨な世界を見つめながら、亡くなっていった。彼女たちは、世界が持つからくりや悪意を自覚すらできなかったかもしれないんです。
『戦争はよくない』『平和がたいせつ』というメッセージだけを描くのであれば、それは僕の仕事ではないかもしれなくて。沖縄戦をモチーフに描くときに、子どものまなざしから『わからなさ』を描きたかったんです。どうして、こんな世界になってしまったのか。そのほうが、この社会を映す鏡になると思って」

「大人」の社会では、「わからない」ことは愚かであるとされ、「わかる」ことが大前提とされる。けれども、子どものころ目の当たりにしていた、私たちを取り巻くこの世界の本当の姿はあまりに広く、あまりにもわからなすぎた。藤田さんの舞台は、子どもを通じて世界を描くことによって、かつて誰しもが抱いていたはずの「わからなさ」を思い出させてくれる。そして、そんな「わからないもの」を描くことこそが表現の可能性ではないか、と藤田さんは語る。
「たとえば、常に答えを求められる仕事もあるから社会が成り立っている部分もあるのかもしれないけど、表現って『わかること』をしなくちゃいけない場ではないと思う。曖昧であることも許されるべきだし、とくに演劇はそう。演劇は、常に流動的で固定化することができないし、終演するまで、その上演時間すらどうなるのかわからないメディアなんです」
「わかる」ことに慣れた私たちは、先の見通しが立たない状態に身を置かれると、どうしても不安な感情を掻き立てられてしまう。けれども一度立ち止まって、あえて「わからない」という状態を受け入れてみると、今までの「わかる」という状態が錯覚だったことに気づかされる。私たちは、いつだって「わからなさ」に取り巻かれていたし、実は今も「わからなさ」のまっただ中にいる。『cocoon』に登場する少女たちが、戦争が終わることなんてわからなかったのと同じように、私たちは明日がどうなるかすら、本当にはわからないのだ。

同じような昨日と今日。でも表現は日々を揺らす
およそ2時間30分に及ぶ圧倒的な舞台が幕を閉じると、満員の観客席からは、万雷の拍手が巻き起こった。そして、記憶に染み付くような余韻に思いを馳せながら、観客たちはそれぞれの帰途につく。彼らの脳裏には、さっき見たシーンが何度も何度も蘇っていることだろう。その記憶の反復は、まるで、舞台上で行われるリフレインのように。
その作品について「主張はないんです」と話す藤田さん。では、観客に何を受け取ってほしいと考えているのだろうか? そんな問いを投げかけると「お客さんに望むことはありません。本当に劇場に足を運んできてくれただけでうれしいんですが……」と留め置きながら、次のように続けた。
「自分が観客のみなさんに何に期待しているか、強いて挙げるとすれば、それは朝に見ていた風景と、観劇し終わった後に見た風景がすこしだけ違って見えていることかもしれません。自分は、演劇に対して『観た人の人生がガラッと変わった』というような変化を与えるようなことは求めていないし、当然、僕がそんな力を持っているとも思っていません。
でも、観客のみなさんの生活における視点をすこし揺らしたり、観劇体験がなんらかのきっかけとなって数年後に今とはちょっと違った人生を歩んでいるかもしれないことに、ほんの少しだけど期待しています。そもそも演劇に限らず、日常ってそんな小さな変化の繰り返しだと思うから。その積み重ねで、人生は営まれていくんだし。
この数年、『表現は不要不急』というような声を多く聞きましたが、自分の価値観をすこしだけ変えてくれるものに出会うことは、決して不要不急のことではないと思うんです。コロナ禍は、多くの被害も、人々のメンタルへの影響も及ぼしましたが、それと同時に、衣食住の外に『生』があることを教えてくれました」

小さな変化の繰り返しによって営まれていく私たちの生。藤田さんのつくる演劇は、そんな私たちの生をトレースするかのように、何度も何度も同じセリフが反復され、その都度、すこしずつその意味を変えていく。そうして、ふと振り返ったとき、その変化の大きさに驚かされる。
昨日は今日とすこし違っていた。明日もまた今日とはすこし変わっているだろう。沖縄で死んだ少女たちが過ごした時間は、微かな変化を繰り返しながら、私たちのところまでやってきた。そしてこれからも、微かな変化を伴いながら、その反復は繰り返されていくのだ。
帰り道に「いっせーのせ」と、ひとりごちてみる。真っ暗な住宅街に、小さく声が響く。何かが変わるわけでもない。何かがわかったわけでもない。でも、ふっと、あの少女たちを包み込む大きな時間の流れに触れたような気がした。

【プロフィール】
藤田貴大(ふじたたかひろ)
1985年4月生まれ。北海道伊達市出身。2007年にマームとジプシーを旗揚げして以降、全作品の作・演出を手掛けている。作品を象徴するシーンやセリフを何度も繰り返す“リフレイン“の手法で注目を集め、2011年に発表した三連作「かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。」で第56回岸田國士戯曲賞を26歳という若さで受賞。13年には太平洋戦争末期の沖縄戦に動員された少女たちに着想を得て創作された今日マチ子の漫画「cocoon」を舞台化し、同作で2016年第23回読売演劇大賞優秀演出家賞も受賞した。演劇作品以外でもエッセイや小説、共作漫画の発表など活動は多岐に渡る。