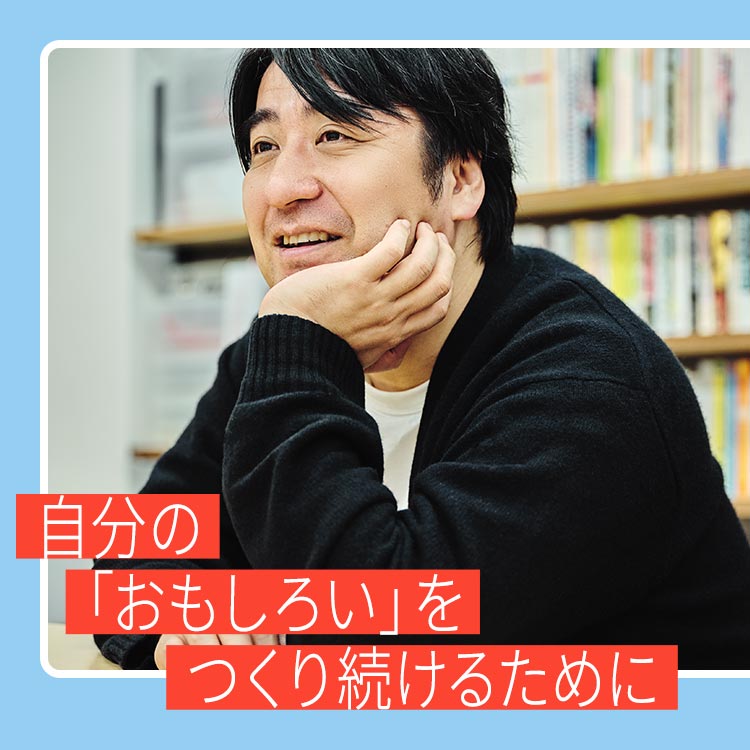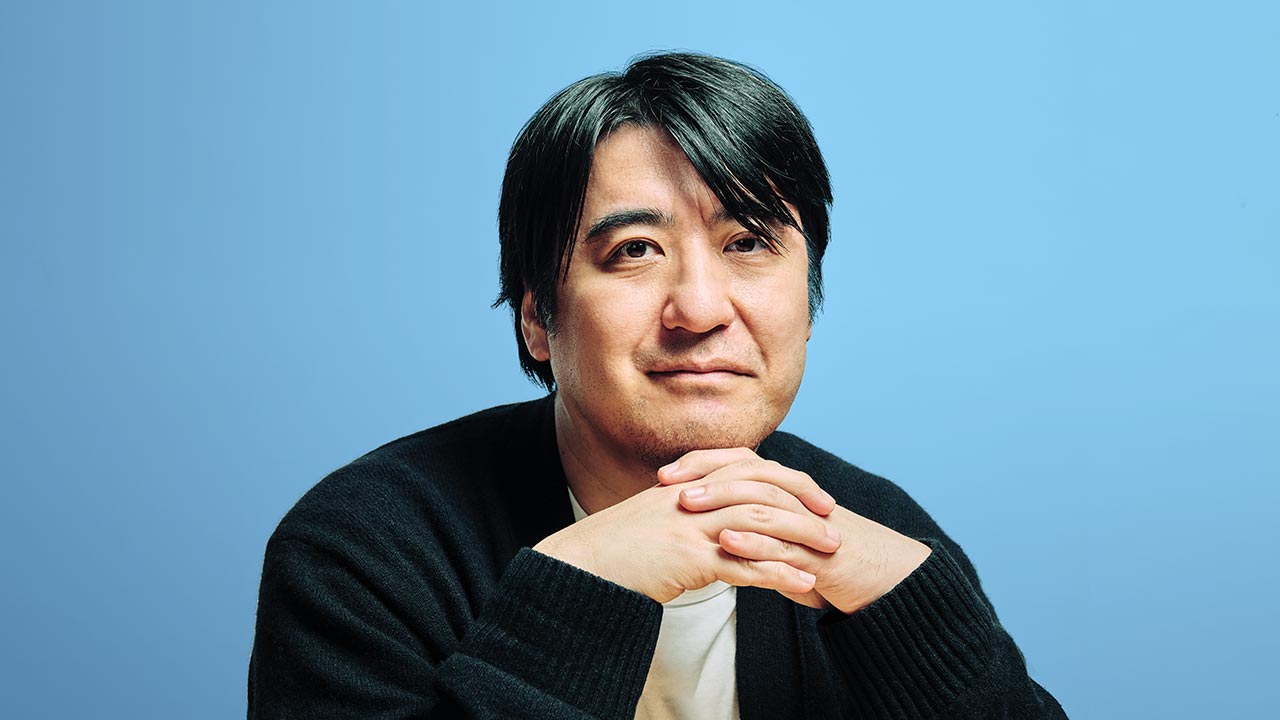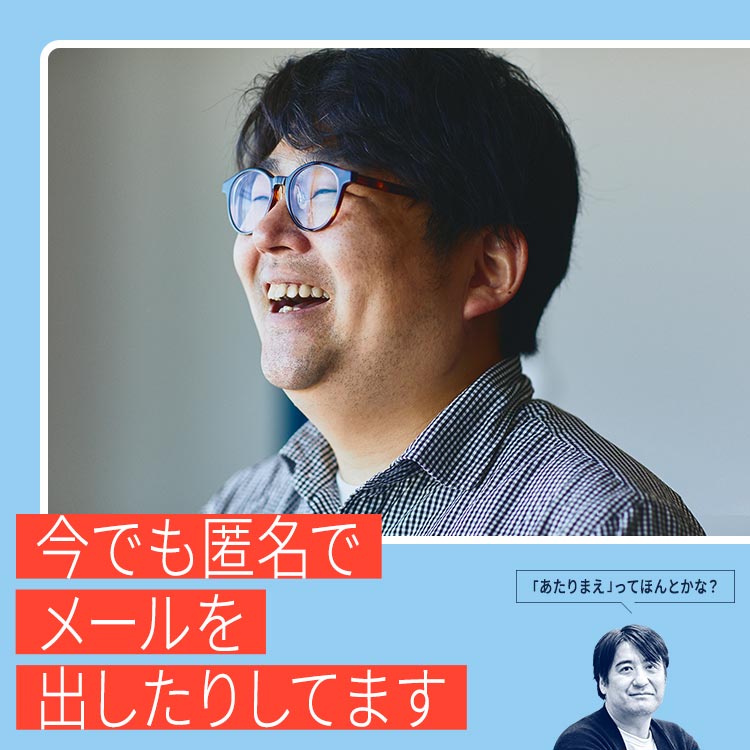お笑いなんて無理、がテレ東の「あたりまえ」だった
——佐久間編集長は、新卒で入社したテレビ東京でたくさんのバラエティ番組をつくってこられました。テレビ東京の深夜バラエティには「尖った」「変わってる」といった印象がありますが、もともとお笑いジャンルに強い局だったんですか?
いやいや、全然! いまでこそ学生の就職先としても人気のテレビ東京だけど、ぼくが入社した当時はお笑い番組どころか、若者が見るような番組はほぼありませんでした。バラエティといえば旅やグルメ、温泉で、しかもその多くが外部の制作会社にお任せ。それがテレ東の「あたりまえ」だったんです。
ぼくはお笑い番組をつくりたくてテレビ局を選んだんだけど、師匠もいなければ前例もツテもない。そして予算はホントに乏しい。割と絶望的な状況でしたね(笑)。
——やりたいことへの足がかりがない状態だった。
結果的に、だから自由にできたってところはあるんですけど。若いうちは自分が「おもしろい」と思う番組をつくるためにはどうすればいいか、ひたすら頭をひねっていました。ただ「やりたい」と思ってるだけじゃチャンスを手にすることはできないぞ、と。
——そこで出てきた結論は?
まず意識したのは、「お笑いがやりたいヤツ」ってキャラクターを自分に印象づけること。ことあるごとに「お笑い番組をつくりたいです」と口にして、企画書を出し続けました。
そうやってキャラが浸透するとだんだん、バラエティ関連のチャンスを回してもらえるようになるんですね。2年目のときには、若手芸人のネタ見せオーディションに誘ってもらえて。そこで出会ったのが劇団ひとりとおぎやはぎです。まだまだブレイク前でしたけど、「うっわー! おもしれー!」って。
——へー! そこでの出会いが後の『ゴッドタン』につながっていくわけですね。(編注・劇団ひとりとおぎやはぎは『ゴッドタン』前身の番組『大人のコンソメ』からレギュラー)
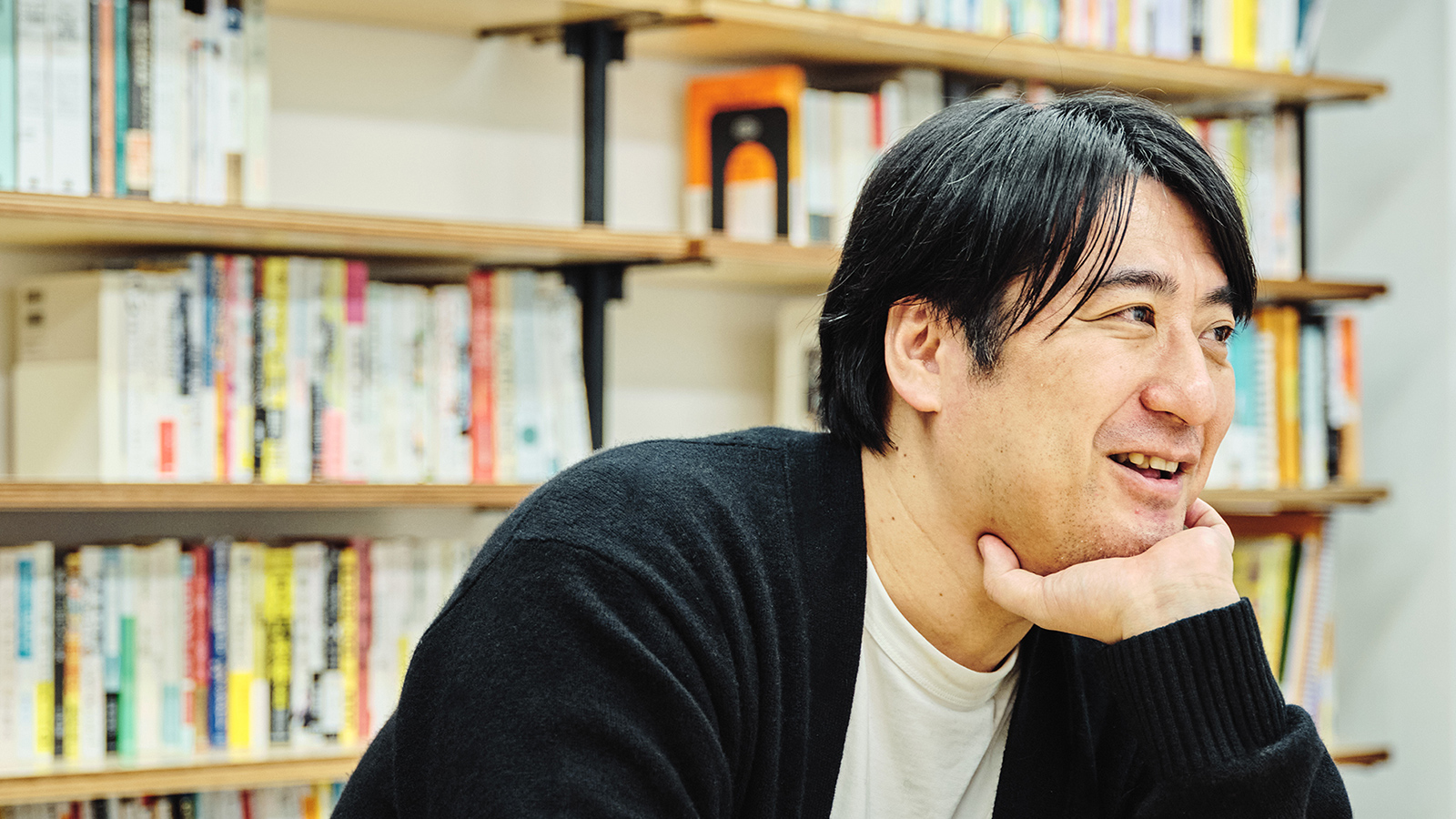
「あたらしい」を「あたりまえ」に育てるために
——でも、テレビ東京にはお笑い番組の「前例」がなかったわけですよね。めぐってきたチャンスをどう育ててきたのでしょう。
いざ自分の番組をつくれるようになってからは、「会社に『有望なプロジェクト』だと思わせること」と「会社と『オリジナルの評価指標』をつくること」を意識するようになりました。最低でもこのどちらかを満たさないとな、と。
——両方とも、「対会社」ですね?
だって、ぼくらはサラリーマンだから。運良くあたらしいことに挑戦できても、「継続してよし!」って判断されないと自分の意志とは関係なくプロジェクトは閉じられてしまう。だから、「どうしたら自分の仕事を会社に認めてもらえるか」を考えるのは、ものすごく大事です。
——なるほど……。おもしろければOKってわけじゃないんですね。
そうそう。テレビ局で言えば視聴率がすべてで、これはもはや「あたりまえ」を超えた「絶対」です。熱狂的なファンがいようが「テレ東」のブランディングに寄与しようが、視聴率が低ければあっさり打ち切りになってしまう。だから、確実に視聴率の取れる「安パイ」な番組が増えてしまいがちなんですけど。
そういう構造だったから、番組ごとに「できること」を考え尽くしました。たとえば、33歳ではじめた『ピラメキーノ』。
——伝説の子ども向けバラエティ番組ですね! はんにゃさん、フルーツポンチさんを一躍スターに押し上げた。
はい。リーマンショックで前の番組のスポンサーが降りちゃって、月〜金の夕方の枠がぽっかり空いたんです。それを見て、「この時間帯に家にいるのは小学生だよな」「フジテレビみたいな大きなお笑い番組は予算的に無理だけど、子ども向けならつくれるんじゃないか?」と仮説を立てました。
そこで、まずは半年でいいからこの枠を預けてほしいって会社を説得したんです。「他局の同時間帯に子ども向け番組はないからイケる」といったロジックと、最後は男気で押し切って(笑)。
とはいえ、ターゲット的に高視聴率をたたき出す可能性はほぼゼロだし、「子ども向け番組なんて前例がない」って強めに反対する人も社内にけっこう多かった。だから、なにか手を打たないとすぐ打ち切りの憂き目に遭うのは明らかでした。
そこで、視聴率以外の評価指標をいくつか提案したんです。イベントを成功させるとか、流行のギャグを最低ひとつは生み出すとか。それを会社と交渉して、ありがたいことに受け入れてもらって、番組をスタートさせました。

——へええ! 「あたりまえの評価軸」を変えるって、すごい力技です。営業部にいながら売上以外の目標をつくる、みたいな話ですもんね。
もともと、テレビには視聴率以外の指標が必要だよなって考えてたんです。まったく期待されてないし(笑)、試すにはちょうどいい枠だなと。
でも結果的に、生放送のリアルイベントに7000人動員したり、CD『ONARAはずかしくないよ』が20万枚のセールスを記録したりと目に見える結果を出したこともあって、『ピラメキーノ』は6年半も続けることができました。
——半年の約束が6年半に!
『ゴッドタン』の名物企画「キス我慢選手権」で映画を撮ったときも、「マジ歌選手権」のライブをはじめて東京国際フォーラムで実施したときも、「佐久間はなにを考えてるんだ?」「成功するわけがない」と言われたりもしました。
でも、これらは「突飛なことをして目立とうぜ!」って企画じゃないんですよ。あくまで「番組を続けるため」に考えたこと。興行収入なりDVDなり物販なりで稼げる番組に育てることで、会社から「続けていいよ」とハンコを押してもらうためのチャレンジだったわけです。深夜バラエティなんて、どんな話題作でも視聴率は知れてますから。
だから、ぼくにとって「あたりまえを壊すこと」は目的じゃない。番組を続けるために必要なアクションが、たまたま前例のないことだった、という感じですね。

エゴ100%だから、なんだってできる
——佐久間編集長は組織に属しながらも枠からはみ出た仕事をされていたわけですが、あたらしいことに挑戦できる人とできない人はなにが違うと思いますか?
うーん……おもしろい話を持ってきてもらえる、というのはあるかもしれないですね。「こんなことできない?」って相談を受けて、「いいっすね!」で実現していく企画もたくさんあるから。
——なるほど。なぜ佐久間編集長にはおもしろい話が集まってくるのでしょう?
「ちょっと変わった話でも否定せずに聞くヤツ」と思われてるからかな。単純に怖くないから、社内外からユニークな案件が寄せられるというか。
——たしかにいつも楽しそうで、人に囲まれているイメージがあります。
でも決して社交的なわけではなくて、いわゆる「会社飲み」に行くことはほとんどありませんでしたね。上司に誘われても、「今週は舞台のチケット取っちゃって」「来週はロケが入ってて」と延々断り続けて(笑)。
次第にまったく誘われなくなったけど、言いたいことは勤務時間中に伝えればいいから別に問題もなかったんです。実際、しょっちゅう上司を会議室に呼び出しては「こういうことがやりたい」と訴えたり「どうしたらうまく進められるか」と相談したりしていました。

——上司を呼び出す。ふつうと逆ですね……!
筋が通っていないことにはハッキリ文句を言うタイプだったし、サラリーマンとしては不器用なほうだと思います。でも、「外野のことを気にしてたら、自分がやりたいことをやる時間がなくなっちゃうよな」って考えていたので。
——「出世してやるぜ!」って気持ちはまったくなかったんですか?
出世に関しては、ホントに考えたことがないですね。ぼくのモチベーションは、「自分の人生を楽しくすること」。エゴ100%なんです。
自分が「おもしろい!」と思う人がつくるコンテンツに、ずっと触れていたい。そのためには売れてほしい。理想を言えば、自分も一緒にものづくりをして、その一助になりたい。……とにかく、おもしろいコンテンツで満たされた社会にしたいんですよね。あと、おじいちゃんになったときにつまんない人が天下を獲ってたらイヤだなってブラックな気持ちも多少はあります(笑)。
でも、こういう確かな目的があるから、自分にできることはなんだってしようと思えるんですよ。前例とか周りがどうとか考えずに。

疑うことからはじめよう
——「あたりまえ」より「おもしろい」を優先してきたからこそ、圧倒的にユニークなコンテンツを世に出すことができたんだな、とよくわかりました。
あと、テレビ局にいて実感したのは、「ルールチェンジは起こる」ということです。
昔は「ネットワーク先の多さこそ正義」だったから、系列局が少なく、全国にリーチできないテレビ東京はずっと「弱者」でした。でもいまはYouTubeや各種動画配信サービスがあるから、独自のネットワークが少なくても戦える。むしろ、しがらみの少ない小さい会社だからこそ、いろんなところと自由に組めたりもします。
ただ、こうしたインターネットの出現による「あたりまえ」の変化は他業界でとっくに起こっていて、テレビ業界にも降りかかることは明らかでした。見て見ぬふりをしてた人も多かったけど、ぼくはその変化を見越してコンテンツをつくってきたし、自分の働き方も考えてきたんです。「絶対こっちに来るだろ」って。
——「あたりまえ」を正しく疑うこと、違和感を見逃さないことも大切かもしれませんね。
もし、あなたの前に「あたりまえ」とか「そういうもん」、「常識だよ」って言葉を使って行く手を阻む人がいたら、たいして考えずにその場しのぎで言ってるのか、ちゃんと検証した上であなたのためを思って言ってるのか、しっかり見極めたほうがいいですよ。
自分に対してだってそう。常識や通説は一度疑ってみて、ちゃんと納得してから自分に取り入れる。そんなクセをつけられるといいんじゃないかなって思います。
(おわり)

前例にも周りの声にも振り回されずに、
ひたすら自分の信じる「おもしろい」をつくり続けた佐久間編集長。
「サラリーマン」でありながらブレずに信念を突き通したそのエピソードを、
豪快に笑いながら、こともなげに語る姿が印象的でした。
これまでJINSも〝あたらしい、あたりまえ〟をつくると掲げ、さまざまなチャレンジをしてきました。
たとえば、佐久間さんが「ごあいさつ」でおどろいていた料金の話もそうですし、
ブルーライトカットレンズの開発もそのひとつ。
それまで「視力が良くない人のもの」だったメガネを
「視力が良い人でも健康のためにかけるもの」にアップデートしたことで、
メガネに新たな価値を与えることができたのです。
メガネとは、視力を矯正するための道具。
——そんな常識を疑い、壊し、次の「あたりまえ」をつくったことは
佐久間さんのお話とも通ずるところがあると感じました。
* * *
次回からは、佐久間編集長が「ぜひとも話を聞きたい!」と名前をあげたトップランナーたちに、「あたりまえ」をめぐるいろいろな話をうかがっていきます。
編集長曰く「常にあたらしいことに挑戦している『安住しない』人たち」には
どんな共通点が、はたまた、どんな違いがあるのでしょうか。
順次公開していきます。お楽しみに!
【お知らせ】
佐久間宣行編集長による特集「『あたりまえ』って、ほんとかな?」の感想・おたよりを募集いたします!
いただいたメッセージは、すべて佐久間編集長にお届けします。記事内で言及される可能性も!?
投稿方法は、以下の「メッセージを送る」フォームに入力、または、Twitterでハッシュタグ「 #佐久間編集長に届け 」をつけてツイートしてください。
【メッセージを送る】
投稿締め切り:4月4日(月)23:59
みなさまからのメッセージをお待ちしております!