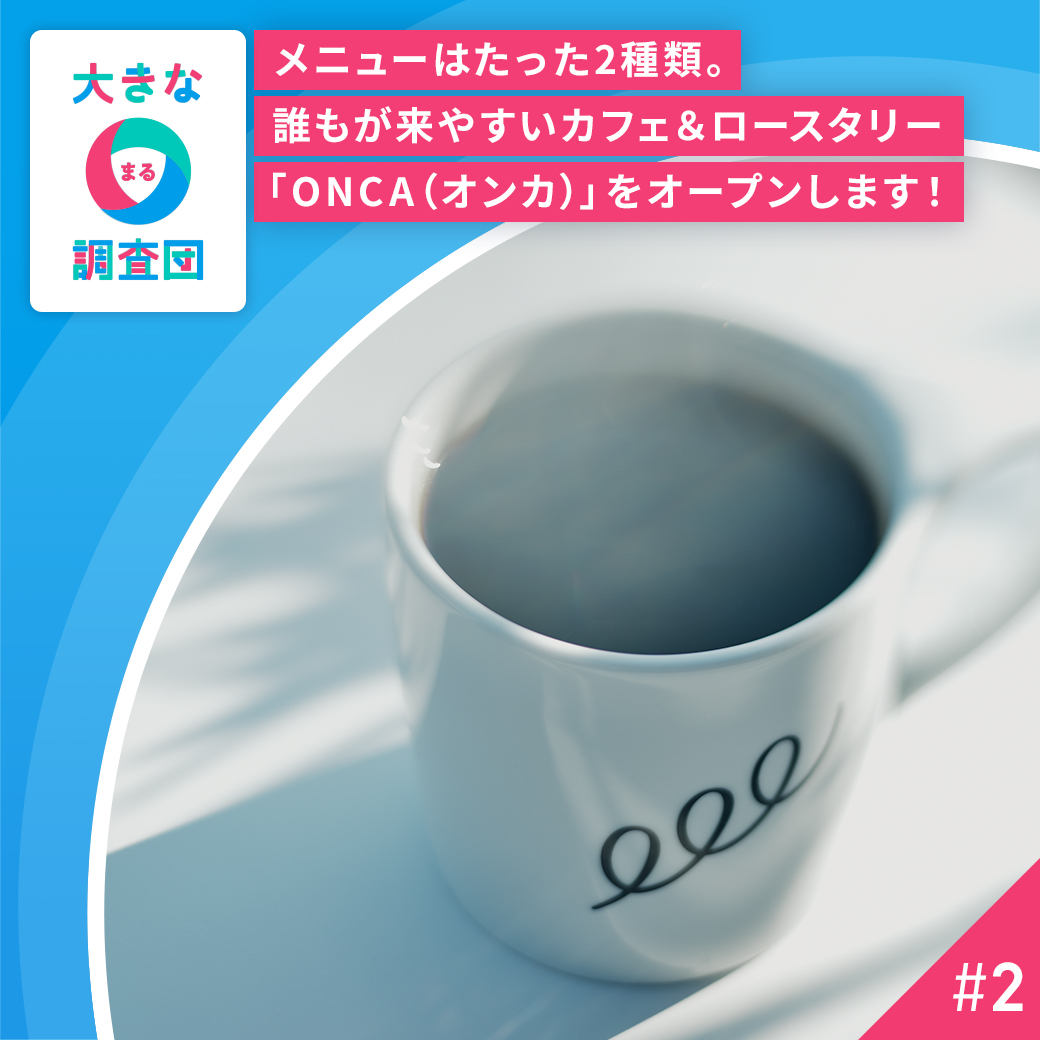JINS、(もちろん)初めての干し芋づくり
干し芋づくりの知らせを受け、“大きな〇調査団”は約1年ぶりに調査へ向かった。今回案内してくれたのは、大きな〇プロジェクトに携わる白石さんと千木良(ちぎら)さん。突然の干し芋宣言により、すでに頭のなかは干し芋でいっぱい。そもそも、干し芋ってどうやって作るんだろう……と思っていたら、さっそく、干し芋づくりの方法を教えてくれた。
千木良 「干し芋を作るには、農場で収穫したさつまいもを、蒸して切って天日干しします。今回育てたのは、“紅あずま”と“紅はるか”という品種。どちらの品種も試作で干し芋にしてみましたが、紅はるかのほうが向いていることがわかりました。そのため、紅あずまは生のまま販売、紅はるかは干し芋にして売ることに。紅あずまはホクホクした食感で、どちらかというと煮たり焼いたりといった、調理に向いています。それに対して紅はるかはねっとりとしていて、甘みがとっても強いんです。焼くだけでおいしくいただけるので、焼き芋に向いている。甘さと食感がいいので、近年は干し芋に使われることも増えているんですよ。
干し芋づくりの最初は、いもを蒸して火を通す工程です。焼く方法もあるんですけど、大量に一定の温度で火を入れる必要があるため、クラシックな“蒸し”にしました。
皮をむいて冷ましたら、こんなふうに大きい卵切り器みたいな道具で縦にスライスするんですよ。

最後にスダレと呼ばれる網で干したら、干し芋になります!網はちょっとこだわって、干し芋農家さんが使っているものを取り寄せました(笑)。毎日ひっくり返して、天日に当てて乾かします。干し芋は奥が深くて、天日干しでしか出ない食感があるそうなんですよ。干す期間は一般的に1週間と言われているんですが、ここ前橋だと3日くらいで終わりましたね。乾くと飛んでいっちゃわないか心配していましたが、甘味が強くてねっとりとした干し芋に仕上がって」
群馬は、風が強い。以前訪れたときも、両足で踏ん張らないといけないほどの向かい風が吹いていたことを思い出した。前橋を望む名峰・赤城山にちなみ、別名「赤城おろし」とも言われている群馬の空っ風。日本海側で湿気を帯びた風が山々にぶつかることで、文字通り、からっからの乾燥した風が街に吹き降りてくるそうだ。そんな群馬の気候は、実は干し芋づくりに最適なのかもしれない。

千木良 「これが干しあがってパッケージまで入れた完成品です。JINS PARKの無人販売所で、生の野菜の隣に置いて売っています。けっこう人気があって、週に20個くらい売れる時もあるんです」
スティックの形になっていて、食べやすそうなのが嬉しい。ついつい手が伸びてしまいそうだ。干し芋に最適な品種や均一な火の入れ方、干し芋が堅くならない方法など、たくさん実験をしたJINSの干し芋……そういえば、なぜ干し芋をつくることになったんだろう?

さつまいもが、一石何鳥にも!?
千木良 「実は、さつまいもをつくりたいという計画は私がJINS normaに加入する前の、2022年の秋ごろからあったんです。そのころ、3反(約3,000㎡)だった畑を10反にまで増やしたんですが、まだまだ計画がきっちりと作れていないためにスペースを十分に活かしきれていなくて……。土地が広いからといって闇雲に作物を育てればいいわけではないんです。野菜の種類によっては、土壌を改良したり保水性を向上させたりしないと育たなかったり、同じ科(編注:植物学に基づく種類)の野菜を続けて育てると連作障害といって育ちが悪くなってしまったりします。それから、生育に水が豊富に必要な野菜だと、水が汲み取りやすい農業用水が通っているところじゃないと育てにくいという問題もあって。さつまいもはまだ整っていない環境でも育てることができる強い作物なので、しばらく活用できていなかった農地を有効に使えると農場チームが考え、計画に加えられたんです」

なるほど。さつまいもは砂漠に近い地域が原産だと聞いたことがある。たくましいので手間もそれほどかからない、便利な作物なのである。
白石 「それに加えて、保管ができるというのも大きかったです。さつまいもって、追熟と言われる工程があるんです。つまり、収穫後にすこし寝かせて、実を熟成させること。2ヶ月くらい寝かせた方がおいしくなるんですよ。お金の面から見ても、長い期間をかけてちょっとずつ出荷できるので安定した収益を得られます」

育てやすく、保管しやすく、おいしさが増して、安定して収益を得られる……一石何鳥にもなるさつまいも。煮たり焼いたりして食べる生食用だけでも十分すぎるほどに便利そうだ。となると、気になるのはわざわざ干し芋をつくった理由。蒸して天日干しにして……。せっかく簡単に収穫できるのに、加工をすると手間がかかってしまうのではないだろうか。
千木良 「干し芋をつくったのは“B品”と呼ばれる、そのままだと販売できない作物を無駄にしないためです。収穫して出荷し、売ることのできる野菜は、大きさや見た目などの基準を満たしたA品と呼ばれます。それに対して、傷がついてしまったり規格外に育ってしまったりして、スーパーに並べられないものがB品です。前回のネギであれば、白い部分が30㎝ないと引き取ってもらえないので、残りは捨てるか個人的に家で食べるかしかできなかったんです。野菜としての品質は全く問題ないのに捨てるしかないものが大量に出てくる。食品廃棄の面や収益の面から見ると、非常にもったいないこと。だからさつまいもは加工することにしました。加工することで売値も生での販売の5倍くらいにできるので、今後生産量を上げることができれば、収益性の向上にも貢献できます。
はじめは、「焼くだけで高く売れる」という発想から焼き芋も検討していました。ただ、よく考えてみると干し芋なら皮を剥くので傷ついたさつまいもでも材料として使えますし、賞味期限も長いので流通させやすい。干し芋の方が手間はかかるけど、メリットが多いとわかりました。将来的には様々な場所で販売することで、JINS normaの認知拡大に繋がったらいいなと。何としてでもやりたかった企画です」
たしかに、少し傷がついているだけで捨てられてしまうのはとても残念だ。それが大好きな干し芋に活用されるのはなんだかちょっと、嬉しい気分。知れば知るほど、干し芋はJINS normaにぴったりに思えてくる。

つながって広がる、大きな〇
千木良 「JINS normaは10反(10,000㎡)の畑で農業をしていて、合計20人くらいのスタッフが関わっています。農業ってどれだけがんばって作物を売ったとしても、実は1反(1,000㎡)で年間100万円くらいにしかならないそうなんです。それを知って、今後圃場(ほじょう、編注:農作物を育てる場所)をしっかり活用して効率的に農作物を作り続けていっても、人件費も到底まかなえないことに気づいて。JINS normaと同じような、他の特例小会社についても調べたんですが、単独で黒字化している会社はほとんどありませんでした。けっこう落ち込みましたね。黒字化に成功している数少ない特例子会社は、やはり生産物の価値を高め、利益を生むために様々な工夫をしています。JINS normaもそうなりたくて、まず、すぐにできそうな食品加工の干し芋に挑戦しました」
白石 「僕たちとしては、障がいを持つスタッフたちにお給料としてもっともっと還元できるようにしなきゃと強く思っています。みんなが自分の稼いだお金できちんと日常生活を送れるように。だからこそ、作物を安定して無駄なく売ることに力を入れました。今はちょっとでも生産物の価値を高める方向を模索しています」

干し芋プロジェクトの裏にこんな想いがあったとは。JINS normaは家庭菜園ではなく、あくまで「農業」。効率よく栽培・収穫して、市場で収益化できたものをスタッフに還元する。干し芋は、その想いを実現するための手段だったということだ。
白石 「今はさつまいもに加え、とうもろこしもつくっているんです。とうもろこしも加工して長期保存ができます。それから、焼き芋や焼きとうもろこしにして販売できるので、JINS PARK前橋(前橋にあるJINS店舗とベーカリーカフェ「エブリパン」の複合施設)で開催するイベントとも親和性がある。安定的に育てられるようになったら、ゆくゆくはエブリパンのパンにも使えるようになると嬉しいです」

JINS PARKの冬イベントの時には焼き芋の屋台を出店したそうだ。地域のみなさんとのコミュニケーションの場所にもなっているのがJINS normaの事業。JINS normaの焼き芋・焼きとうもろこしや野菜でつくられたパンを食べながら、イベントを楽しめる日も近いかもしれない。
千木良 「JINS normaでは昨年の4月にオープンした、ONCA COFFEE & ROASTERY 前橋店でコーヒーの生豆をハンドピックする仕事を受託しています。そこで農場チームがカフェから出るコーヒーかすの再利用、堆肥化に目を付けました。今はエブリパンで提供するコーヒーも含め、出たコーヒー豆のかすは捨てずに全て回収し、発酵させて完熟堆肥として農場で使っています。コーヒー豆の力ってすごくて、堆肥にする以外にも除草や消臭のためにも使えるんですよ。おかげで、成長不良でやむを得ず畑に廃棄した野菜の腐敗臭もかなりおさえられています。さらに、“チャフ”という焙煎の度に大量に発生するコーヒー豆の薄皮も使っていまして。霜がつくのを防ぐために、えんどう豆など、冬越しをする作物の根元に布団みたいに敷いているんです。コーヒー豆が入っていた麻袋も捨てずに農場で再利用しています。様々な捨てるはずのものを捨てずに活用できているので、カフェと農場って、すごく相性がいいですよね」
初回の調査で、「いつかコーヒー豆のかすを農場の堆肥として使えたらいいな……」と話していた白石さん。久しぶりにやってきた調査団が目撃したのは、前橋でコツコツと進化しているJINS normaの姿だった。1年ちょっとで、大きな“食”の輪っかは繋がりつつある。いよいよ次からは“人の輪”も広がってくるのだろうか。
続報に乞うご期待。