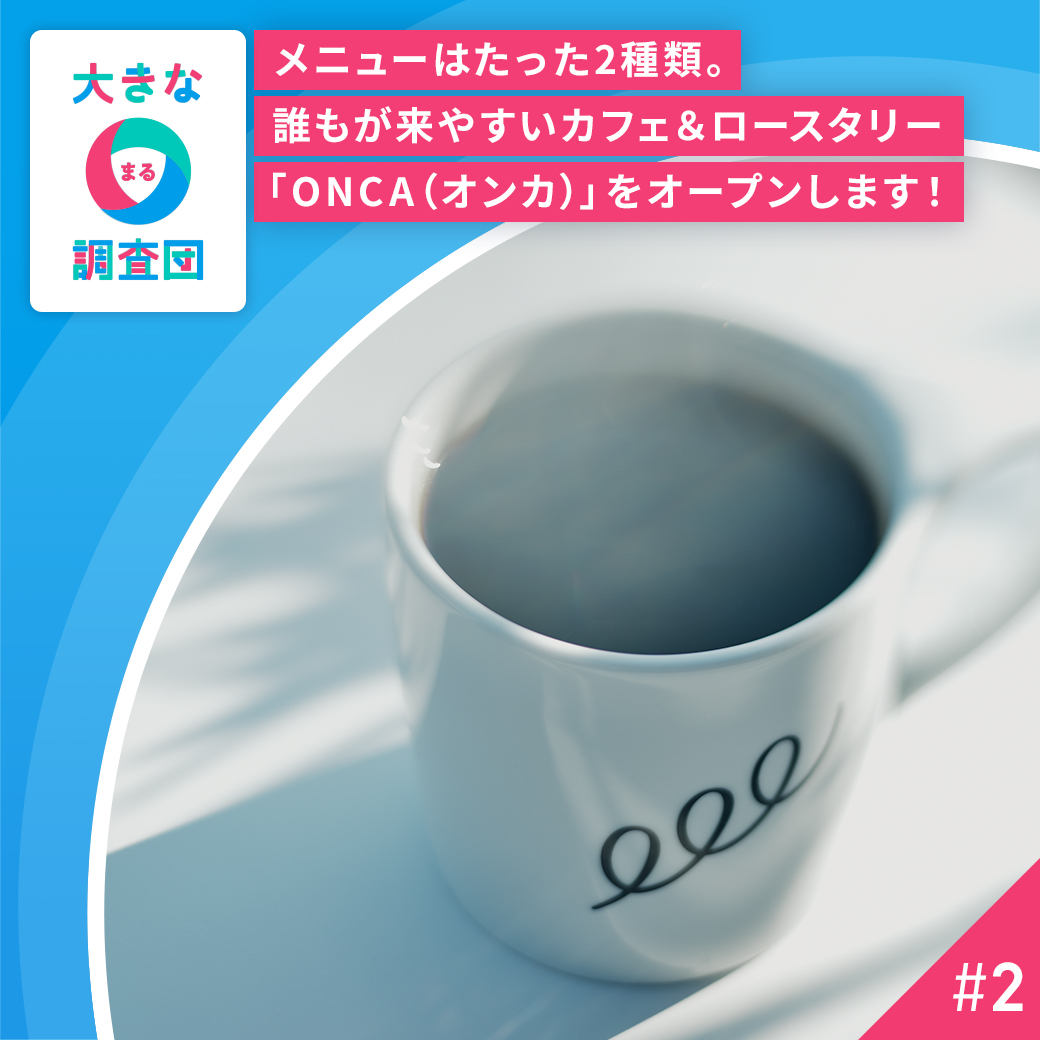2月某日、時刻は10時30分。“大きな〇調査団”は群馬県高崎市にある畑にいた。目の前には整然と植えられたネギ。雲ひとつない快晴で太陽は燦々と地上に降り注ぎ、青々と伸びたネギの葉を照らしている。取材した日はひんやりしていてまだ肌寒かったが、澄んだ空気を吸い込むと気持ちがいい。これから私たち大きな〇調査団は、JINS normaという農業に取り組んでいる事業に密着取材をする。
JINS normaの“norma”は「ノーマライゼーション」が由来。「障がい者と健常者が、お互いに区別することなく共に生活する社会を目指す」ことを意味する。障がい者と対等に働くために、JINSは本業とは全く異なる農業の事業に取り組み、雇用の輪を広げているのだ。
手際よくネギを収穫している5人組がいた。まさにJINS normaで働かれている方々だ。障がい者と健常者がひとつのチームとなって作業を行っている。樋下田 修一(ひげた しゅういち)さん、斉藤 美智子(さいとう みちこ)さん、小野 裕太郎(おの ゆうたろう)さんに話を聞いた。
樋下田 「障がい者の雇用では、障がい者は作業する人、健常者はそれをサポートする人、という関わり方が一般的です。私たちJINS normaはそういった区分をせず、同じチームのメンバーとして、一体となって農作業を行っています。このネギ畑のように自社農園もあれば、近隣の農家さんから「手伝ってほしい」と声をかけてもらい、農作業を受託している農園もあるんです。ナスやトマトなど、場所や季節によって多様な野菜を育てています。収穫した野菜はJAなどに出荷して日本全国へ。同じく前橋にある、JINS PARK(実店舗)でも販売しています」

JINS norma 樋下田さん
JINS normaの取り組みがスタートしたのは2015年。健常者3人と障がい者2人で始まった取り組みは、今やメンバー約50人という規模まで拡大しているという。「農業は続けたいけど人手が足りなくて……」と後継者や担い手不足に悩む農家さんの声に応え、農作業を受託し、サービスを提供することで地域と繋がっている。
JINS normaの健常者の社員が逐一指示を出すという様子は一切なく、みんな慣れた手つきでネギを抜き取っていく。遠目から観ている限り、みな同じように生き生きと働いている。

樋下田 「障がい者の方もコミュニケーションは問題なく取れますし、作業の覚えも早いんです。
業務についての提案なども積極的にしてくれるので、チームワークを活かして仕事に取り組めています。僕たちも、彼らのモチベーションが上がるようなコミュニケーションを取るよう意識しているんですよ。
農家さんも彼らと関わってみて普通にできることが多いことに驚かれますね。長時間の作業でも、みんな集中して取り組んでくれています。健常者がやるより作業のスピードは早いかもしれません。——そうこう話しているうちに、収穫が終わったようです。次は事務所へ行きましょうか。今から選果(せんか)と呼ばれる作業を行います」
選果というのは、作物の大小や品質をチェックすること。お店に並ぶ野菜は長さや太さが決まっているケースが多く、出荷するためには欠かせない作業だ。
収穫したネギを積み込んだトラックを追いかけ、私たちも車で移動。到着したのは木で作られた温かみのある看板が目印の、JINS normaの事務所。先ほどの収穫メンバーから人数が増え、10名ほどが外に座ってネギを触っている。すでに作業は始まっているようだ。

作業場所から少し離れた場所で車から降りると、一瞬にしてネギの香りが鼻をくすぐってきた。採れたてのネギってこんなに香りが豊かなんだ。
このままとり肉といっしょに串を刺し、タレを絡めておいしいねぎまにしちゃいたい……。想像しただけで、なんだかお腹が空いてくる。
作業している場所に近づいてみると、あそこにいる人は皮を剥いて、こっちの人たちはネギを切って。あれ、それぞれ行っている作業が違う。

樋下田 「ネギの下の根っこを切る作業、外側の緑の部分を剥く作業、太さと長さを測る作業と、みんなで作業を分担しているんです。“ネギの選果”と一括りにしてしまうと覚えなければいけない手順が多いですが、複雑な作業を分けることで、ひとつひとつはシンプルになって覚えやすくなります。普通の農家さんだとそもそも人員が少ないですから、ここまで作業を分けることはできません。チームでやっているからこそ分業できて、誰でも働きやすい環境を作れているんです」
奥の小屋の中ではネギの長さや太さを測る作業を行っている。箱のようなものを使っているけど、あれはなんだろうか。樋下田さんと同じくJINS normaのチームメンバー、斉藤さんに話を聞いた。

斉藤 「あれは治具(じぐ)といって農作業の補助工具です。サイズを分けるために手作りした私たちのオリジナル。農作業って感覚で教わることが結構あるんですけど、わかりづらいんです。特に障がいのある方にとっては伝わりにくくて難しいことも多い。ネギは長さや太さによってランクがA、Bと分けられるのですが、「長さがこれくらいで太さがこうだとA」という感覚的な言い方ではなく、「この箱におさまるものはB」「これに入るのはA」というように明確でわかりやすくするために治具を使っているんです。メンバーの中で一人でもできない作業があれば、なぜできないかを考えて「どうすればできるようになるか」を探る。想像力を大切に、解決策を導き出しています。得意不得意はみんなそれぞれの個性。個性は健常者・障がい者を問わず、どんな人にもあって当たり前ですよね。みんなができるためにはどうすればいいかを考えることが、この仕事の面白さでもあります」
斉藤さんは6年前にJINS normaに転職してきたんだそう。前職は農業に全く関係ない職業で、農業の知識はゼロからのスタート。トライアンドエラーを繰り返す中で、地域との繋がりが深まったという。

JINS norma 斉藤さん
斉藤 「聞き慣れない用語も多くて、たとえば「残渣(ざんさ)捨てといて」と言われても、全く意味がわかりませんでした。残渣って収穫するときに発生する、食用には適さない茎や葉っぱなどの残りかすのことなんです。何もかもがわからないことの連続で大変でしたね。ほうれん草を初めて育てたときは、全然芽が出なかったんですよ。困り果てていたら近所の農家さんが声をかけてくれて。ほうれん草の種は「鎮圧」といって、種を蒔いた後に土を踏み固めないと芽が出ないということを教えてくれたんです。やり方を丁寧に教えてくれた結果、無事に芽が出て。嬉しかったですね。農業の知識が得られることはもちろん、人との関わり方を学ぶこともたくさんあります。地域の方たちから様々なことを教えてもらい、支えられながら農業に取り組んでいます」
地域の人と、コミュニケーションの場にもなっているJINS norma事業。プロジェクトの立ち上げから携わり、メンバーの採用や育成などを担当しているのが小野さんだ。

JINS norma 小野さん
小野 「メンバーは20歳から30歳くらい中心ですが、50歳を超える方もいらっしゃいますし、男性も女性も働いています。農業っていわゆる3Kの「キツい・汚い・危険」といわれることがありますよね。チーム農業ならではの分担作業などで働きやすい環境づくりを進めて、そういう農業に対するネガティブなイメージも変えていけたらいいなと思っています。みなさん、働く熱意はすごいですよ。それに集中力と持久力、根気強さがずば抜けている人が多いです。あそこにいるたかしさんは入社第一号なのですが、特に集中力がすごいですね」
JINS normaの立ち上げ当初から、共に奮闘してきた小野さんとたかしさん。たかしさんは「小野さんとはライバルのような関係です」と笑いながら教えてくれた。運動会や懇親会など職場の交流の機会もあって、たかしさんも楽しみにしているという。働く人たちみんな、生き生きしている。JINS normaのネギ畑では雇用の輪に地域の輪、“人の輪”が広がりをみせていた。


JINS normaにあるのは“人の輪”だけではない。2022年からは小麦の栽培を少しずつ開始。JINS normaで育てた作物を使って、同じくJINSが運営しているベーカリーカフェ「エブリパン」でパンを販売することも予定している。食の循環、いわば“食の輪”を作りだそうとしているのだ。

5月頃は、小麦の栽培も!
そしてその取り組みがいま、実現に近づいている。前回取材したカフェ&ロースタリー「ONCA COFFEE & ROASTERY 前橋店」。オープンした4月12日(水)は、お客様の行列とともに開店し、大盛況だったそう。そのONCAで出たコーヒーの欠点豆や抽出後の豆のカスをJINS normaの畑に肥料として利用する実験はもう始まっているという。人の輪に食の輪、〇は大きく広がっていく。
取材を終えて車に乗り込むと、JINS normaのメンバーみなさんがお見送りをしてくれた。たかしさんは深々とお辞儀してくれている。私たちが見えなくなるまでお見送りしてくれたみなさんの気持ちにすっかり心を掴まれて、JINS normaで働く人たちのファンになってしまった調査団だった。