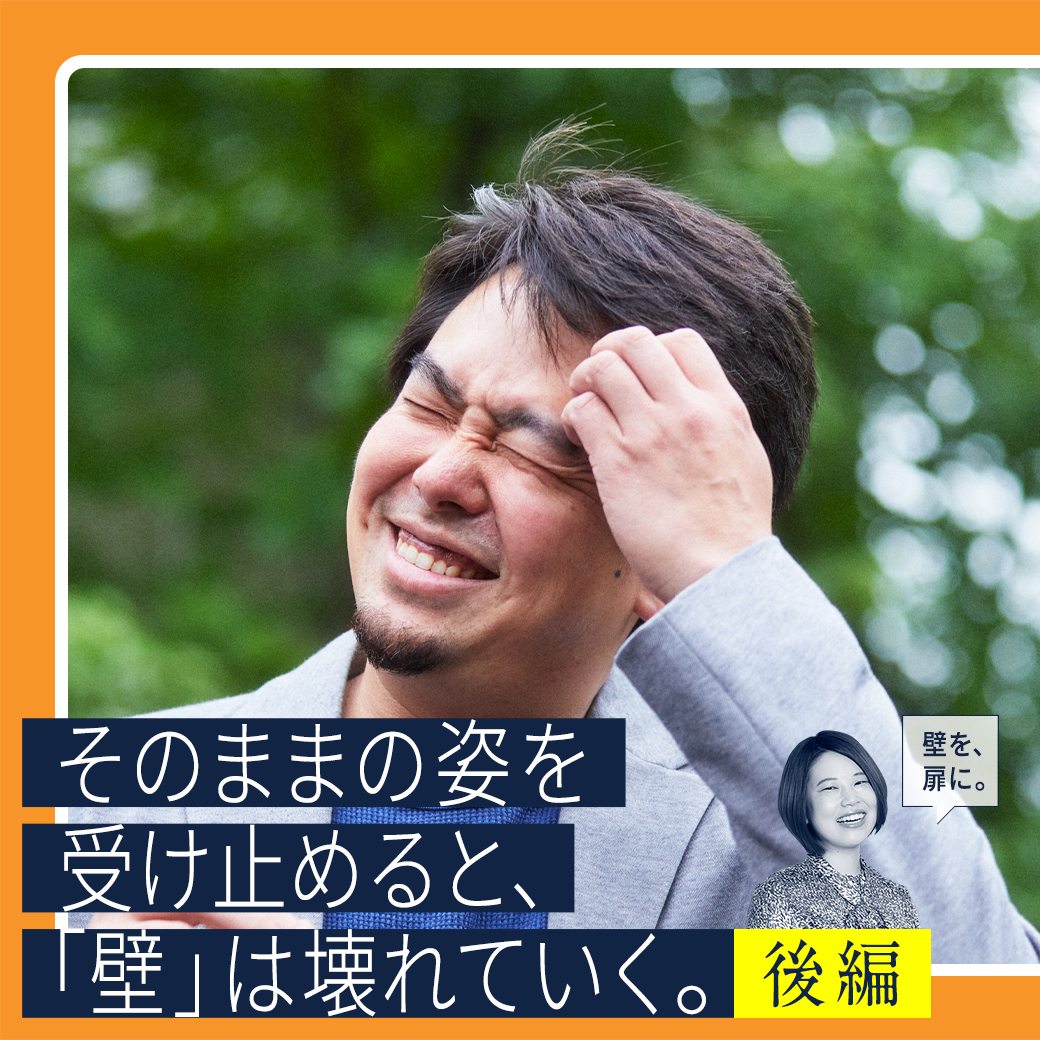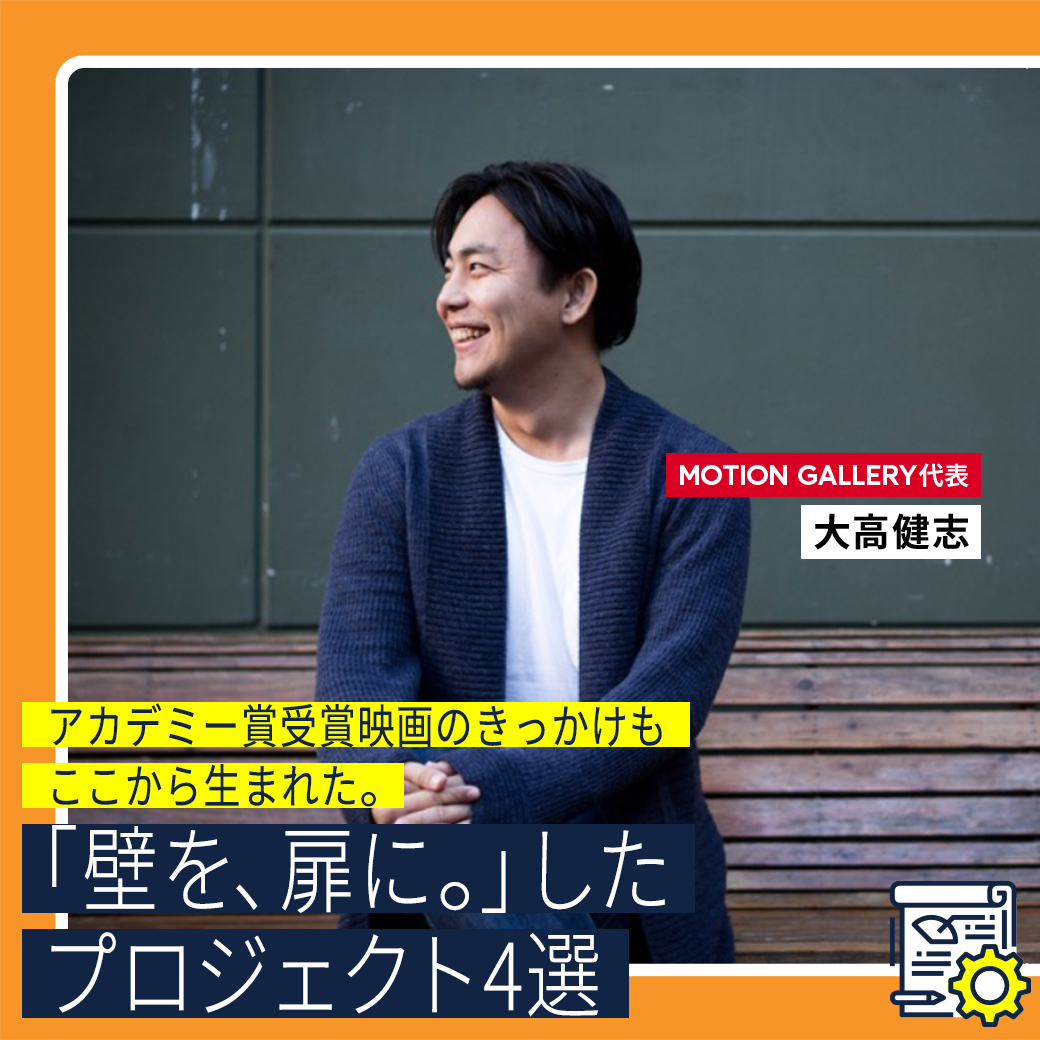「そこにいるだけで」ダンサーになれる空間
東京・JR武蔵境駅からバスに揺られること8分。交通量の多い道路をまっすぐ進んで目を引くのは、原色にちかい鮮やかな色の球体と立方体がくみあわさってできた、世にも不思議な建物です。
幼稚園や保育園など、どこか子どもの遊び場を思わせるようなカラフルなたたずまいですが、これこそ、今回ご紹介する「三鷹天命反転住宅」です。
じつはこれ、人が住んでいるれっきとした賃貸住宅。しかも、ただの奇抜な建築物ではありません。
扉を開けてまず気づくのは足元の違和感。
視線を落とすと、なんとリビングの床一面がでこぼこになっているうえに、大きく傾いています。予想外のしつらえに、取材班もしばらく真っ直ぐ立っていられないほど。
よろよろとしながら動きまわること数十分。先ほどまでおぼつかなかった足取りに、変化が現れてきました。床のでこぼこに足裏が反応したのか、だんだんと一歩が軽やかになってきたのです。
ためしに靴下を脱いでみると、小さな砂のような素材でできたザラザラのつぶが、足裏を気持ちよく刺激。気づいた時には、はだしのまま軽快なステップを踏んでいました。

いわゆる“住みやすい”部屋とは正反対をいく空間であるにもかかわらず、一歩足を踏み入れたとたん、ふしぎと身体を動かしたくなる…..。この身体感覚の活性化こそまさに、建物のつくり手であるアーティストの2人、荒川修作とマドリン・ギンズのねらいでした。
荒川さんはこの空間を、著作『22世紀の荒川修作+マドリン・ギンズ 天命反転する経験と身体 』の中で、「普通の人がいるだけで、ダンサーになれる場所」と表現しています。

住人のモデルはヘレン・ケラー? 身体の感覚を開放させる家のひみつ
「ここの正式名称は、『三鷹天命反転住宅 In Memory oh Helen Keller 〜ヘレン・ケラーのために〜』。盲目かつろうの作家、ヘレン・ケラーを住人のモデルとして設定した建物なんです」
そう話すのは、荒川修作+マドリン・ギンズ東京事務所代表の本間桃世(ほんまももよ)さん。
「ヘレン・ケラーは目が見えないぶん、全身をつかって世界を認識していました。荒川とギンズにとっては、こまやかな身体感覚を備えた盲目の彼女こそ、この建物の住人のモデルとして最もふさわしい人物だと考えていたのです」

荒川とギンズが目指した理想の住まい、それは「身体を中心とした家」でした。しかし、三鷹天命反転住宅の完成した2005年、世は「バリアフリー」ブームのまっただなか。天命反転住宅は「反バリアフリー」の代表建築として批判されることもありました。
たしかに身体を意識した家であるならば、段差をなくしたり、平坦で歩きやすいフローリングを敷くことで「安全な家」にする方法もあったはずですが——。
「意外に思われるかもしれませんが、目の見えない方からするとでこぼこの床は良いガイド。彼らはわたしたちに比べて、足の裏から情報を取り入れる能力に長けているんです」

じつはこの床、人間の土踏まずに合うよう綿密に設計されたもの。床だけでなく、部屋の設計はすべて、身体のセンサーを刺激するよう考え抜かれています。結果として、感覚に繊細な子どもや障がいを抱えている人ほど、「ここへきた瞬間、身体を開放できる」のだとか。
「どんな人でも、すべての身体にはすばらしい能力が秘められているんです。現代の生活では、その能力が発揮する機会も場所もなかなかありません。もともと備わっている個人の身体のポテンシャルを、最大限に引き出せるような空間を目指してつくられたのが、この三鷹天命反転住宅なんです」

天命反転という思想がひろげる、「死」の概念
死なない家といってもやっぱり、「どんな人でもいずれこの世を去ってしまうじゃないか!」と思ってしまうのはおそらく筆者だけではないはず。事実、荒川修作とギンズのおふたりはすでに、10年ほど前に他界されています。
「死なないための家」とはつまり、「仕掛けがたくさん隠された家に住むことで、身体の可能性を引き出し、肉体的な寿命を伸ばす」ということなのだろうか? そもそも、「死なない」ってどういうこと……?
頭の上にたくさんの疑問符がついた筆者を見かねた本間さんが、こう答えてくださいました。
「死んだ後の世界のことは、誰も知らないわけですよね? であれば、わたしたちが理解できない死後の世界に対して、そんな一元的な見かたをしなくてもいいのではないでしょうか。」
そう、荒川修作とギンズ夫妻が考えた「天命反転」という思想はまさに、社会で染み付いたあたりまえを疑うスタンスのもとに成り立っていました。「絶対に変えられないと思っている人間の運命を、異なる角度から捉えなおす、つまり天命を反転することで死という行き止まりの先に進める」と信じていたのです。

重要なのは、この建物が死という「天命」をどう捉えなおし、「反転」させるのか。
あらためて部屋の中を見てみると、あらゆるところで内と外が「反転」していることに気づきます。
「たとえば、本来は自然界にあるものを積極的に部屋の素材として持ってきています。床は天然の土とモルタルを混ぜた素材でできていますし、畳のそばには砂利もありますよ。本来は外にあるものを中に持ってきているという点も、あたりまえをひっくり返すという『天命反転』の思想が影響しているんです」

自然界のテクスチャーが混在しているため、全盲の方といっしょにやってきた盲導犬が「ここはどこ?」と迷ってしまうということもあるそう。
「人間に比べれば動物としての能力がまだ残っているはずの犬ですら、人間社会のあたりまえをきちんと教育されている。まずは住宅という誰もが使う空間から、みなさんの中にある常識を少しずつ変えていきたいと思うんです。
この天命反転住宅は、変えられないと思っている常識や運命を反転、ひっくりかえす舞台装置になっています。人々の身体に染み付いたあたりまえという『壁』の先へすすむ、『回転扉』となる空間なのかもしれませんね」

壁を回転扉にするために、身体の声を聞いてほしい。
その昔、街や道路のない広大な自然を走り回っていた人間。人類の長い歴史の中で見れば、さまざまな色や素材に囲まれ、なるべく自然環境にちかい状態で生きることのほうが、むしろ「ふつう」のことなのかもしれません。
「現代的な生活をしていると、どうしても動物の本能としての自分を忘れてしまう。自然界の中で生きていたときの能力や感覚を引き出すような、しかけづくりが必要だと思います。もっと身体の声を聞いてほしいんです」

ここで暮らしていた元住人のなかには、大手ニュースアプリ『スマートニュース』のCEOである鈴木健さんや、独立研究者として数学を探求している森田真生さんなど、今もなお社会というサバンナの第一線で走り続けている人がたくさんいます。
「奇抜で混沌としたこの空間に少なからずインスパイアされてしまうのは、きっとわたしたちのDNAに組み込まれている自然界での記憶が、室内のしかけとして巧妙に反映されているからなのでしょう」
あたりまえだと思っていた「壁」が、回転扉のようにくるっと反転して、あたりまえではなくなる瞬間。そのとき扉の向こうに見えるのは、いったいどんな景色でしょうか。わたしたちを「動物」に戻す自然界? それとも、「人間」のアイデアの泉……?
***
『あたらしい、あたりまえ』を創り、まだ見ぬ世界を拓いていくこと」を志しているJINS。
あたらしい世界を見るためには、逆説的ですが「見る」以外の、身体の感覚を研ぎ澄ます必要もあるのかもしれません。「見る」を追求する企業として、これからもあらゆる視点を持ってあらたな価値をつくっていきたいと思います。
© 2005 Estate of Madeline Gins. Reproduced with permission of the Estate of Madeline Gins.