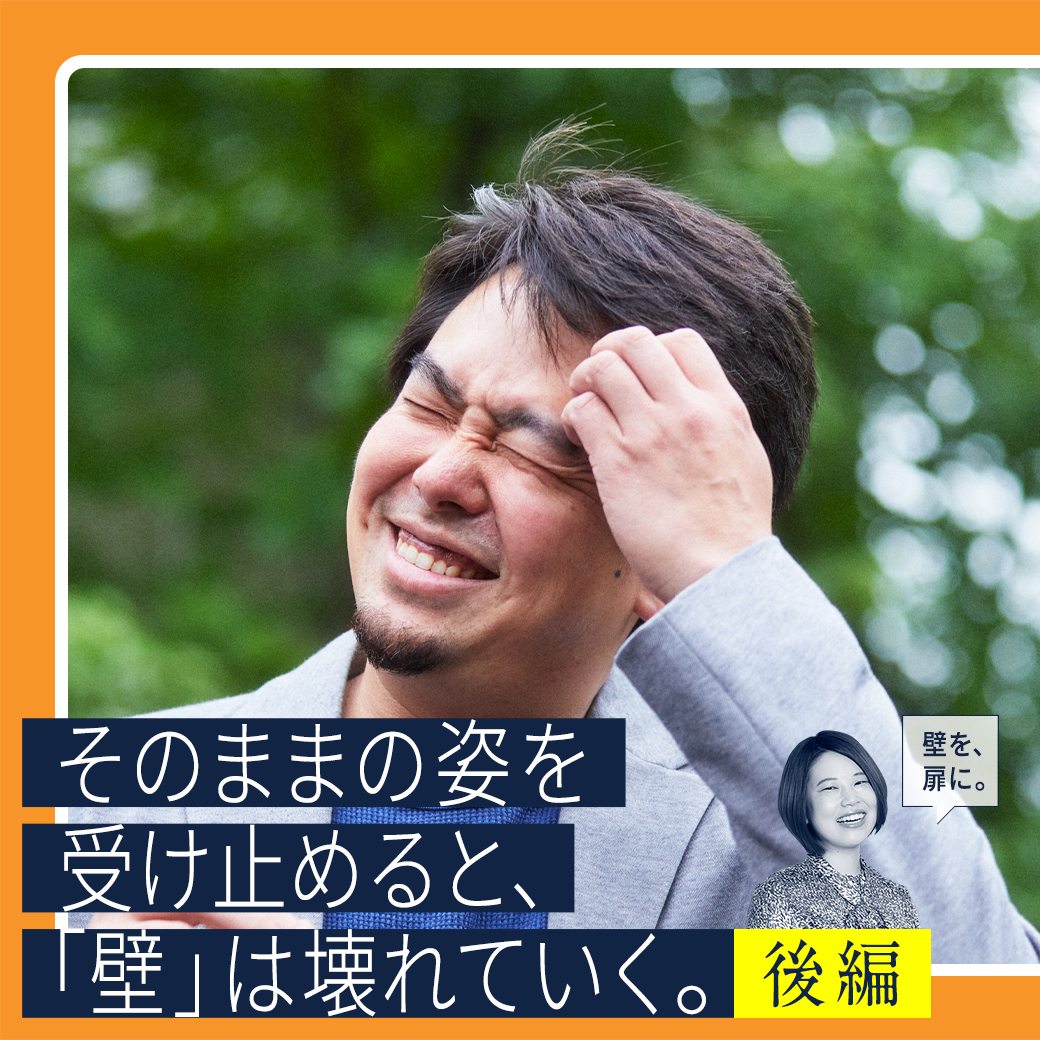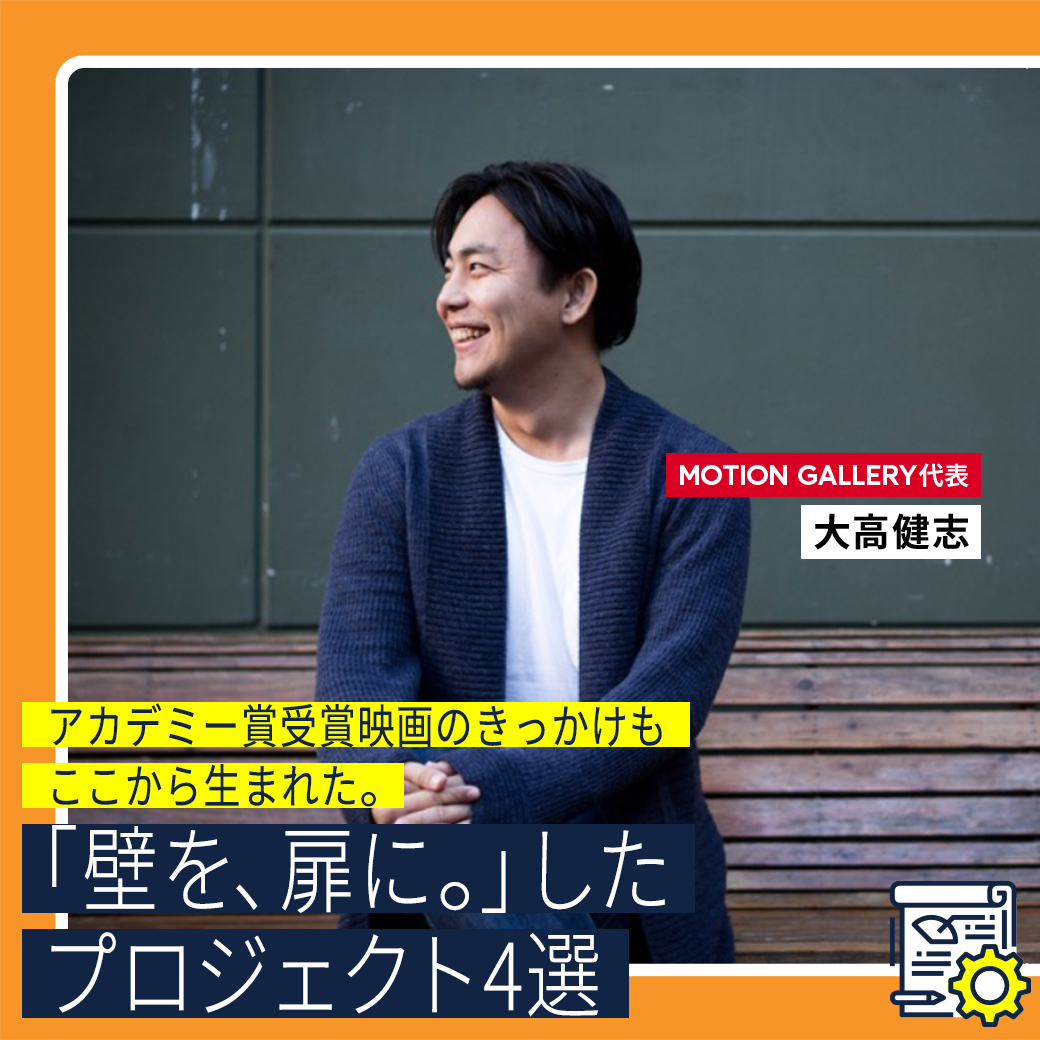スナックという混沌
——事業継承にあたって改装されたと伺いましたが、「かつて」と「今」が同居したような内装がとても素敵ですね。前身の「すなっく・せつこ」から引き継いだものを大切にされている様子がとてもよくわかります。
ありがとうございます。気に入っていたライトも残していますし、椅子も生地を張り替えて使っています。カウンターはちょっと今っぽく木製のものにしていますが、もちろんここで「カラオケ」もやっていますよ。

——坂根さんも歌われているんですよね。十八番の曲はありますか?
『酔っぱらっちゃった』(内海美幸 / 1982年)というスナックソングがあって、それを気に入ってよく歌っています。昭和歌謡は、「すなっく・せつこ」時代にママとお客さんにたくさん教えてもらったんですよ。「この曲知ってる?」って突然聞かれたり、「デュエットしよう」って誘ってくださったり。スナックでは、カラオケが1つのコミュニケーションツールになっているんですよね。
——居酒屋にはない特徴的な文化ですよね。最初にスナックと出会ったとき、そこに戸惑いはありませんでしたか?
4年以上前の出来事ですが、戸惑いはすごく大きかったです(笑)。特にカラオケは、嫌でも耳に入ってくるものじゃないですか。ましてや偶然、隣になった人と肩を組んで歌うなんてことは、スナック以外では絶対起こり得ないコミュニケーションですもんね。でもそういった「ノイズ」も、スナックに大きな魅力を感じた理由のひとつかもしれません。
初めて人に連れられてスナックに足を踏み入れたのが、今のお店の前身である「スナックせつこ」でした。そのときのことは、本当によく覚えてるんです。平気で横から他のお客さんが会話に入ってきて、「何歌う?」だなんて聞いてくるし、ママもいっぱい話しかけてくるし。「なんだここは」という感じでした(笑)。全然くつろげないんですよね。でも自分の失敗話や、離婚した話なんかを替え歌にして歌ってるおばさまがいたりして。みなさん底抜けに明るいんですよ。根っからそういう人たちなのか、ここにいるからそんなに楽しそうなのか……。気づけば、その「スナック」という場の不思議な魅力にどっぷりとハマっていたんです。

心の壁が溶けていく?
——スナックで働く側になっても、魅了される気持ちは変わりませんでしたか?
そうですね。むしろ「なるほど」とおもしろく思うことがとても多かったです。たとえば、毎週来てくれるお客さまに「あ、前はこんな話はしてくれなかったけど、してくれるようになったんだな」と感じたときとか。逆に「自分もこの人に気を許しはじめているな」なんて些細な話す調子の変化で、互いの関係性が変わっていることに気づくんですよね。その経過も楽しくて。
別に、すごく込み入った話がしたいわけじゃないんですよ。だけど、ただダラダラと話したり、一緒にカラオケをしたり。そんなしょうもない時間を重ねていって、その分だけ、気を許し合う関係になっていく。「“非生産的”な時間を人と多く重ねることって、決して“意味がない”ものじゃないんだな」ということに気付かされましたね。そういう時間の過ごし方って、それまでのわたしができなかったことなんです。
——どこか生産性や効率をいつも意識されていた。
そうですね。もともと、学生時代から事業をやっていたり、丸の内で働きたい! なんてバリキャリ志向だったこともあって、時間が惜しいという感覚が常にありました。
それに、わたしは社交性はあるんですけど、気づけばいわゆる「よっ友(大学のキャンパスや街中で遭遇したら「よっ」と軽く挨拶を交わす程度で、それ以上の関わりはない関係)」ばかりが増えているような。人を傷つけるのも怖いし、傷つくのも怖いから、ちょっといい距離をとって卒なくこなしているような人間関係がすごく多かったんです。恥ずかしいんですが、人との距離の詰め方がよくわからなかったんですよね。
でも、ちょっと相手に踏み込んでしまったり、迷惑をかけてしまったり。その傷とか歴史こそが意外と信頼関係に結びついてるんじゃないか。わたしがいちばん忌避していたことが壁になって、人に頼ることが難しかったんだなあ、と今ならわかりますね。

——心の壁にノックするようなお仕事で、ご自身が抱えていた壁に気づかれたんですね。数年経験され今ではママになった坂根さんでも、まだノックが難しいときはありますか?
もちろん。経験としてもまだまだなので当然いっぱいありますよ。すごく寡黙なお客さんがいらっしゃれば「楽しまれてるかな」と心配になって、ちょっと無闇に話しかけすぎて失敗してしまったり。だけど、何を求めて今日来られてるのか、どんなコミュニケーションが心地良いのか、というのは常に探ろうと努力します。
中には、カラオケとお酒でたのしくなっちゃって「周りのお客さんにすこし迷惑かな?」という遊び方になってしまうお客さんがいらっしゃるんですけど、そういったときには、「きっと何か普段我慢してることがあるんだろうなあ」「何か辛いことがあったのかもしれない」と背景を想像しながら対応しますね。ちょっと偽善的かもしれないですけど、わたし自身も何かに当たってしまったり、はしゃいでしまったり、そういうことでしか解消できないよ! っていうときはあるので。なるべく自分と重ねて理解しようと努力しながら、お客さんには接するようにしてます。
——お客さまと自分の壁を溶かすような感覚でしょうか。
そうですね。もちろんこの場所を管理する使命もありますから、そこはしっかりと判断をしますが、自分も完璧じゃないからこそ、なるべく寄り添いたいと思うんですよね。
ここは、「それぞれ水の中をプカプカ漂うように楽しんで、明日に向かって再浮上していく場所」。だから名前も「スナック 水中」としたので。みなさんにとってプカプカと心地のいい場所を守りたいと考えています。

「衰退産業」だからこそ
——「かつてはバリキャリ志向」というお話がありました。「スナックのママになる」という決断は、相当悩まれたのではないでしょうか。
悩みましたね。それでも踏み出せたのは、やっぱりわたしはスナックが好きだし、スナックを心からおもしろいと思ってるんですよね。「すなっく・せつこ」という場にわたしはいろんなことを教わりましたし、「一緒に働こうよ!」と引き入れた後輩の女の子たちもすごく楽しんでくれて、わたしたちにとって本当に大切な居場所だったんです。
だから、若い人たちにもスナックのおもしろさを知ってほしいですし、たとえばわたしのように「人に頼れない」「強がってしまう」そういう若い女性が集まる場所にもなれるはずだと思うんです。「これは、いける」という確信があるから、事業として挑戦してみたい、と思えたところがあります。
——スナックのリバイバルに、大きな可能性を感じているんですね。
そうですね。それに、もしもわたしが普通に就職していたとして。夕方に「ーーさんがスナックのリバイバルに挑戦しています」なんてニュースが流れたりしたら、すごくすごく悔しいと思ったんですよ(笑)。他の誰でもないわたしがやらなければ、絶対、超後悔する! と思いました。そのぐらいスナックを想っていますし、「わたしがやりたい!」という気持ちは確実に決め手となりました。

呼吸するような、扉の役割。
——「心の壁」とは別に、このスナックの物理的な「壁」にも興味があります。スナックといえば、「窓がなく、外から中が見えない空間」というのも特徴のひとつかと思うのですが、ここはドアがガラスになっていますね。
実はこれは開閉式なんです。月曜日から金曜日は、中が見えない壁。土日には、中が見えるガラスのドアにして、営業しています。
スナックには良いところがたくさんありますけど、衰退産業になってしまったからには反省点もあると思っているんです。それは、外を排除して中だけでコミュニティを作ってしまったために、お客さんの層が高齢化する一方で新しいお客さんを迎え入れることができなかったという点なんですよね。
ガラス張りにすることで、「ここは健全な場だよ」「清潔感のある場所です」というアピールにもなりますし、「みなさんウェルカムなんですよ」ってメッセージを伝えたかったんです。新しい人にもどんどん入ってきてもらいたいですから。
だけど、もちろんずっと来てくださる方がゆったり飲める場所でもありたい。「あなたが大事ですよ」と語りかけることも大切だと思ったので、あえてどちらも取れる「開閉式」という仕組みを採用しました。

——反響はいかがですか。
ここを開けていることで、「気になって入ってみました」というお客さんもいらっしゃいますし、開放感があって、わたしもすごく気持ちいいですね。
平日はちょっとクローズドなコミュニティ、土日はちょっと2駅3駅ぐらい離れていても、「行こうかな」と足を伸ばして来てくれるような20〜30代の男女の方がやっぱり多くて。スナックが育ててきた閉鎖性なコミュニティの良さを維持しつつも、呼吸するように開いたり閉じたりする入り口なら、なんだか新しい人がどんどん入ってきてくれそうだと思いませんか。

混ざり合って愉しめる「夜の拠点」へ
——今、ママとしてお店に立たれている中で、1番楽しいことってどんなことですか?
やっぱり女性や若いお客さんが「ああ楽しかった」って言いながら帰られる姿を見ると、「ああ、スナックの魅力を新しい人に届けられた」とうれしくなりますね。届けたいところに、届いている! と。
あとは、ここが「再会の場」になることも多いんですよ。身近なところだと、わたし自身も「すなっく・せつこ」で一緒に働いていて今は大阪に転勤してしまった子と再会できたり、その子とママ・せつこさんの再会を見ることができたり。そういう出会いや再会をこのカウンター越しにみられるのもこの仕事の醍醐味のひとつだなと思います。
ママが来てくれると、やっぱりわたしもうれしいですしね。

——ママ・せつこさんは、今のお店をどんなふうに仰っていますか?
テレビで見たよ、すごいじゃん! 活躍してるじゃん! と喜んでくれていますね(笑)。1度ママの姿をこの店で見たときに、うるっと泣きそうになってしまったことがあって。
やっぱりアルバイトとして見ていたお店の景色と、今ママになって見る景色は全然ちがうんですよね。「ああ、今日お客さん来るかな」っていう不安や、悩むこともありますし、背負っているからこそ辛くなることもいっぱいあるんです。そういうことを感じるとき、「実はママはスタッフに嫌な思いさせないように、全部吸収していたんだな」と改めて思います。それを考えると、ぐっと来てしまって。
あとで、わたしが「実はちょっとうるっとしちゃいました」とメッセージを送ったら、「あなたはもう立派な経営者で、この場に責任持って、たくさんのスタッフを抱えながらやってる証拠だね。それはきちんと伝わってるので、頑張ってください」って返してくれたんです。そんなハンサムなママのお店をわたしは引き継いだので。いろんな課題にぶち当たりながらも、お客さんにとって「壁を取り払える、最高の場所」を追求して、提供し続けようと思っています。
* * *
スナックのリバイバルに本気で取り組む坂根さんの姿。同じようにJINSも、かつてのどこか「壁」を感じてしまうような閉鎖的なメガネ店舗のあり方を変え、身構えずに来店いただけるよう工夫を探求し続けてきた自負があります。常連さんが安心し、初めてのお客様も身構えずに過ごせる坂根さんの笑顔に、「これからも、もっと」と改めて店舗づくりについて考える機会となりました。
最後に、坂根さんにJINSへの印象を聞いてみました。
「軽くてサッと身につけやすいものが多くて、デザインも豊富ですよね。今年はあまりに暑いので、日差しに負けないサングラスが気になっています。
実は、昼間は他の仕事もしていてダブルワークなんです。そうしている方が精神的にも体調的にもバランスが良くて。日中に外に出ることも多いので、サングラスなども取り入れて、よりアクティブにしていきたいですね」

【プロフィール】
坂根千里(さかねちさと)
一橋大学社会学部卒。学生時代からスナックを愛し、卒業と同時に東京・国立市の半地下にある9坪のスナック「すなっく・せつこ」を事業承継。クラウドファンディングで387万円の支援を受け、2022年3月に「スナック水中」として同店舗をリニューアルオープン。お店ではママを務め、「ちり」のニックネームで親しまれる。