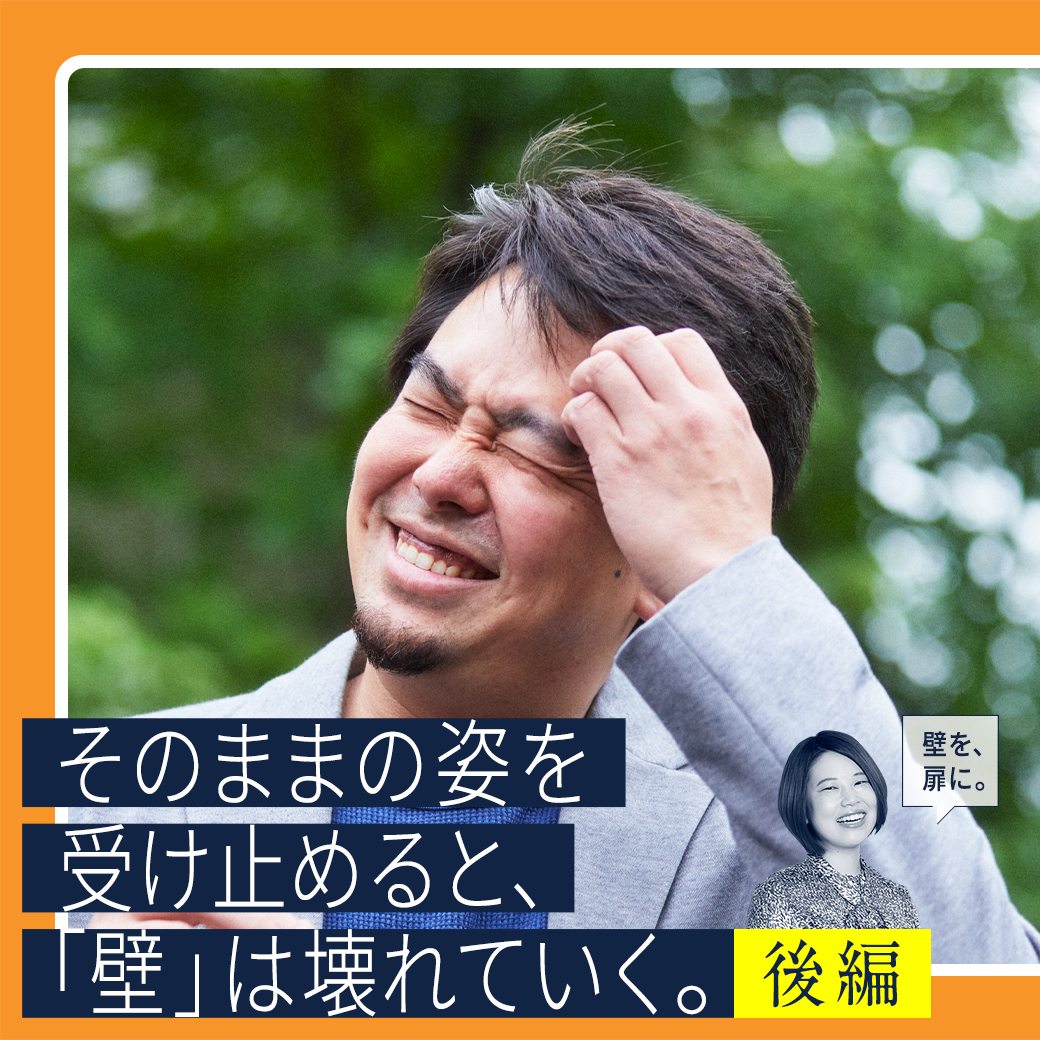「助けなくちゃいけない」とは思われたくない
——前編では、聴者がろう者に対して「気を使いすぎてできた壁」についてお話を聞きました。ろう者の親を持つ聴者の子供、いわゆるCODA(Children of Deaf Adults)の筆者が気になったのは、同じくCODAである息子さんと、江副さんの関係です。そこに「壁」はあるのでしょうか。
いいえ、子どもは子ども。ろう者だからといって親に気を使う必要なんてありません。ろう者である親の自分が苦労しているところは、なるべく見せないように心がけています。やはり、どうしても困ってしまう場面はあるんです。でも、息子には頼りません。「ろう者だってできるんだぞ、馬鹿野郎! 心配いらないから、子どもは向こうで遊んでろ!」という気持ちで接しているんです。
——江副さんが手話指導をされたNHKのドラマ『しずかちゃんとパパ』でも描かれていましたが、CODAがろうの親の“通訳”をするケースがあります。でも江副さんは、お子さんに通訳をさせないという方針なんですね。
そうなんです。もちろん、私の言語は手話なので、きちんと教えてきました。だから、息子も手話ができます。でも、通訳を頼むつもりはありません。

——私は、率直に言うと、やはり「聴こえない親を助けたい。役に立ちたい」と思う瞬間があります。
わかります。私の息子もそう考えるみたいで、聴者と話していると近くに来るんですよ。親として、彼の気持ちがよく伝わってくる瞬間です。でも、そのたびに「必要ないよ」と言ってきたんです。仮に頼ってしまったら、「次もやらなきゃ!」という義務感が生まれてしまうかもしれない。そして、聴こえない親だから、「助けなくちゃいけない」と思われてしまうかもしれない。私はそれが嫌なんです。そんなこと考えず、ただ「親」として見てもらいたくて。
——障がいがあるからといって、必ずしも弱いわけではないということですね。ただ、この社会にはどうしても「障がいのある人=助けなければいけない人」という見方も残っているように感じます。
必要な支援はありますし、「助けたい」という気持ちが、みんなのメリットにつながることもあると思います。一方で、「そこまでされても……」と感じることもあるんですよ。私個人としては、ろう者から求められたときにだけ、助け船を出してもらえたらいいなと思います。求めてもいないのに何から何までされてしまうと、「馬鹿にされてるのかな?」と思ってしまうんです(笑)。
そのためには、ろう者からも必要なこととそうではないことをはっきり主張しなければいけない。大切なのは、お互いが腹を割って話し合える関係だと思います。

ありのままの姿を見せることで、「壁」は壊れていく
——江副さんと話していると、ろう者だから、聴者だから、と気を使いすぎたり、思い込みを持つのではなく、相手をそのまま受け止めることで「壁」が壊せるのではないかという気持ちが湧いてきました。
『しずかちゃんとパパ』の現場では、まさにそれを意識しました。ろう者役の(笑福亭)鶴瓶さんに手話を指導する時、まずはろう者とのコミュニケーションを体験してもらったんです。ろう者の動き、生活のすべてを見せて、通訳者を介してガンガン話しかけました。
——鶴瓶さんにありのままのろう者の姿を見てもらった、と。
私がどんな人なのかもよく分からず、信頼関係が成立していないうちから手話を教わっても、きっと苦しいのではないかと思ったんです。だから、日常生活のなかでろう者がどのようにコミュニケーションを取っているのかをすべて見せて、ちょっとずつ理解してもらおうと考えました。すると段々、「ろう者ってこういう風に動くんだ」「手話ってこういう間(ま)なんだ」とわかってくる。ろう者への「壁」を取り払ってから、手話指導をスタートさせました。

——リアルなろう者の姿を受け止めて、演じてもらうことにこだわったんですね。
鶴瓶さんは本当に苦労されたと思います。落語家なのでロールシフト(自分以外の話者を演じること)や間の取り方は上手なんです。ただ、初めての手話ということもあり、手をたくさん動かすことに慣れないみたいで。一生懸命やるうちに手がつってしまうこともあって、大変そうでした。なので、鶴瓶さんに合わせて、手話の表現を変えたんです。「もうええ」「いらん」「断れ」など、なるべく簡単な動きで表現できるように。
また、地方に住む高齢のろう者という役柄に合わせて、使う手話や動き方も工夫しました。実際にモデルにしたろう者も存在します。「たしかにそういうろう者っているよね」と思ってもらえるように、リアルさを追求したんです。手話にはいろいろな考え方があるので、もしかしたらろう者からクレームがたくさん来るかもしれないな、と覚悟もしていましたが、「クレームが来たって構わないぞ!」と自信が持てるくらいの仕上がりでした。
——吉岡里帆さんが演じた、同じCODAの立場から観ても素晴らしいドラマでした。CODAが親を思う気持ちがよく描かれていましたし、かといって、同情を誘うようなストーリーにはなっていなかった。まさに、リアルなろう者やCODAの姿を描くことで、彼らに対する思い込みの「壁」を壊してくれるような。
そうなんです。これまで、ろう者のことを描くドラマというのは、どうしても同情させるようなものが多かった。でも、制作陣は「それを壊したいんです」と言ってくれて。見ている方向が一緒であることがわかって、現場はとても楽しかったです。

呼ばれたら「壁」を壊し、基盤を固める
——ドラマの中では、ろうの父親とのコミカルな掛け合いも印象的でした。
それは脚本を書かれた蛭田直美さんのおかげでもあります。この脚本を手話に翻訳する時も、ひとつ思い込みの「壁」を壊したんですよ。
——どんなことだったのでしょう?
初めて脚本を読んだとき、とにかく面白かったんです。蛭田さんは、ろう者やCODAの日常をコメディに近い形で描こうとされていました。そして、日本語がすごく魅力的だったので、セリフをどうやって手話に翻訳するか、迷いました。
私が脚本のセリフを手話に翻訳するときは、その文章のニュアンスや意味を再現します。だから文章としての流れを見ていくと、日本語と手話とではどうしても異なる部分ができてしまう。つまり、画面に表示される字幕と手話が微妙に異なってしまうんです。すると制作陣は、手話に合わせてより簡単な日本語に字幕を変えようとする。実際、これまでの現場でそういったことがありました。

でも今回は、字幕の日本語は変えないでほしいとお願いしたんです。たとえ字幕と異なっていたとしても、手話で同じニュアンスを伝えることができる。ろう者を軽んじないでほしい、と。すると蛭田さんをはじめとする制作陣は理解を示してくれました。結果として、日本語で書かれたセリフと手話での表現とが異なるシーンが多々あったと思います。
——日本語と手話は異なる言語であって、そこに優劣はない。対等なものである、と理解してもらったんですね。
そうなんです。「ろう者だから仕方ない。日本語が苦手なんだもんね」という思い込みではなく、実際の手話が持つ表現の豊かさを理解してもらえたのがうれしかったです。
——江副さんのおかげで、ドラマを観る人たちに限らず、制作陣の意識も変わっていったのではないかと思います。江副さんにかかれば、ろう者に関わる思い込みや、気を使いすぎることでできる「壁」がどんどん壊れていきそうです。
もしもいまのような仕事を続けていけるのであれば、そんな「壁」はすべて壊していきたいと思っています。ただし、自分の立場に執着するつもりはなくて。「壁」を壊して基盤を固められたら、若いろう者たちに譲りたい。「江副、この壁を壊してくれ」と頼まれたらそこへ行き、すべてぶっ壊して、次の世代に譲っていく。そんな風に活動していきたいんです。
* * *
ろう者のことを「弱い存在と思われたくない」と真摯に語ってくれた江副さん。その言葉に滲むのは、リアルで、ありのままで、等身大のひとりの人の姿をちゃんと見てほしいという思いでした。
翻って、JINSも、毎日様々なバックグラウンドをお持ちのお客様との出会いがあります。これからも挨拶を大切にし、一人ひとり、「あなた」として向き合い、良い関係性を築くことを大切にしていきたいと改めて感じました。

【プロフィール】
江副悟史(えぞえさとし)
東京都出身。日本ろう者劇団に入団後、手話狂言や自主公演などに出演。2010年3月までNHK『こども手話ウイークリー』のキャスターを務める。映画『獄に咲く花』で杉敏三郎役を演じる。3.11震災後にネット手話ニュース『DNN』を立ち上げる。2017年より日本ろう者劇団の劇団代表を務める傍ら俳優、講演、手話表現者(国際手話など)、手話弁士、キャスターなど幅広く活動中。