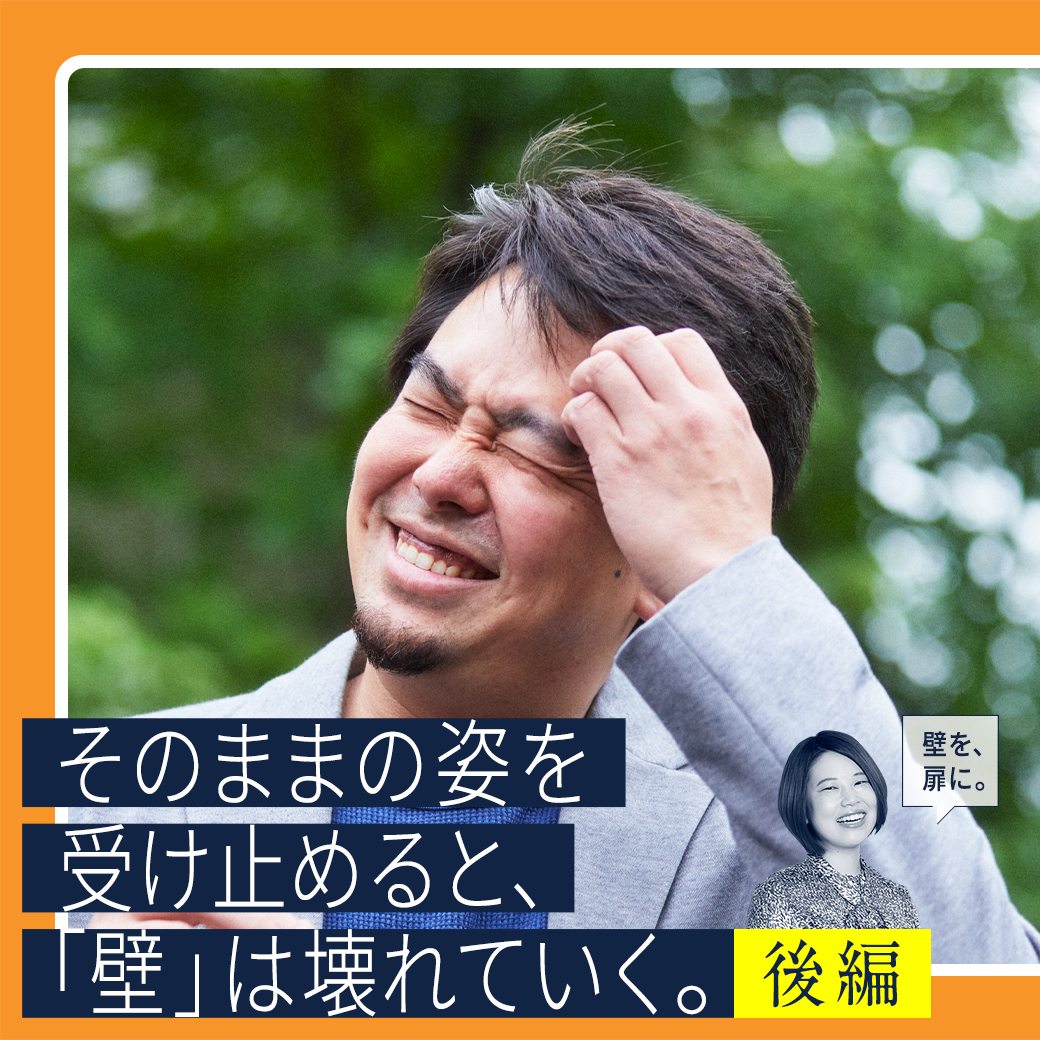「配慮しなければいけない」という思い込みを壊したい
——江副さんは日本ろう者劇団の代表を務めながら、手話弁士やキャスターなどにもチャレンジされています。最近ではNHKのプレミアムドラマ『しずかちゃんとパパ』の手話指導をされましたね。意欲的に活動の幅を広げている印象ですが、一方で、「壁」を感じる瞬間はあるのでしょうか?
たとえば、聴者(聴こえる人)ばかりの環境に飛び込むとき、「壁」を感じることがあります。彼らはろう者のことを知らないので、そもそもどのようにコミュニケーションを取ればいいのかすらわからないんです。
——でも、「手話」が存在することは知っていますよね?
ろう者の言語である手話のことを知っていても、どう表現すればいいのかはわからない。声を掛けるタイミングにすら戸惑うことが多いみたいです。そんなときは、私から積極的に声を掛けるようにしています。
どんどん話しかけていって、「たとえ手話ができなくても、なんとかすれば通じることもあるんだ」と肩の力を抜いてもらえると、「よっしゃ!」と嬉しくなるんです。
社会には「障がい者には配慮しなければいけない」「障がい者と接するときには注意しなければいけないことがある」という考えがあって、私には時々それが過度な思い込みに見えることがあります。私はそれを壊したいんです。
聴者とろう者の間に「壁」があるとしたら、きっと聴者からすればそれはとても分厚い壁だと思います。でも、私からすればそんなものは、ただのカーテンみたいなもの。「カーテンが閉まってるな」と思ったら、サッと開けてしまえばいいと思っています。

——他者との間にある「カーテン」を開けることを怖いと感じる人は少なくありません。どうして江副さんはためらいもなく開けてしまえるんでしょうか?
大学生の頃の経験が大きく影響していると思います。小学校から高校までずっとろう学校に通っていた私にとって、大勢の聴者に囲まれるという経験は、大学生になって初めて味わうことでした。当時は、私も「壁」を作っていたんです。
友達になりたいけど、どんな風にコミュニケーションを取ればいいのかわからない。紙にメッセージを書いて、それを渡したいんだけど、タイミングをうかがってしまう。今、話しかけてもいいのかな、迷惑じゃないかなって。
それはまわりのみんなも同じで、私に気を使うあまり迷っている様子でした。お互いに探り合っていたんです。
でも、それって無駄なエネルギーを使っていることだと気づいて。それから積極的に話しかけるようになりました。するとみんなも同じように、肩を叩いてくれたり、メモを渡してくれたりと、たくさんコミュニケーションを取ってくれるようになったんです。
——すごく勇気のいる行動だったとも思います。
そうかもしれません。最初は恐怖心もありましたしね。自分のコミュニケーション能力がどこまで通用するのかわからなかったですし、「馬鹿にされないかな?」と不安でした。でも、それは私の勝手な思い込みで、つまり私自身が勝手に「壁」を作っていたということなんです。
自ら動いてみて思ったのは、聴者とろう者の間にあるのはカーテンでしかない、ということ。それ以降、カーテンをどんどん開けて、たくさん話すようになっていきました。友達が増えて、六本木のクラブに行ったり、カラオケに行ったり……ほとんど毎日飲み歩いていましたよ(笑)。

ろう者ではなく「江副」として見てもらいたい。
——酔っ払った江副さんが楽しそうにお喋りしている様子が目に浮かびます。そうやって聴者と触れ合うようになって、なにか発見はありましたか?
ろう者も聴者も結局は変わらないんだということに気づきました。同じ人間なんですよ。ただ、私が出会った日本人の聴者の多くは控えめで遠慮がちなところがあって、それが「壁」になっているとも感じました。
私の親戚は、ほとんどが国際結婚をしているんです。なので、子どもの頃から「日本人なのか外国人なのかではなく、ひとりの人間として見なさい」という教育を受けてきました。だから外国人とコミュニケーションを取ることにも慣れていて。
そこで気づいたのが、まわりにいる外国人の聴者との話しやすさ。彼らはろう者を前にしても堂々としているし、身振りで伝わることも多い。無意識に「壁」を作ってしまうことがあるとしたら、気を使いすぎなんじゃないでしょうか。
まあ私は、その「壁」も勝手に壊して、「どう? 江副ですけど?」って相手の懐に入っていっちゃうんですけどね(笑)。

——ろう者を傷つけたくないけど、どうしたらいいのかわからない……。そう悩んだ結果、話しかけるのをやめてしまう人もいますね。まさに「気を使いすぎてできた壁」だと思います。
そんな「壁」はいらないんですよ。仮に迷ったり悩んだりすることがあるのだとすれば、個人的にははっきりストレートに訊いてほしいと思っています。そして、ろう者ではなく「江副」として見てもらいたい。
——勝手にラベルを貼って、決めつけないでほしい、と。
そうです。ろう者に対して失礼なんじゃないかと思う質問があったとしても、私個人にはなにも気にせず訊いてもらいたい。だから初対面の聴者には、わからないことは「わからない」と言ってもらいたいし、全部受け止めます、と伝えています。すると聴者も安心して、徐々に打ち解けてくれるんです。
でも、これは個人差があります。私と同じ質問をされて、傷ついたりショックを受けてしまったりするろう者もいる。ただ、それって聴者も一緒ですよね? 訊かれて平気なこと、嫌なことは一人ひとり違う。
——たしかに。「ろう者だから」「聴者だから」ではなく、目の前にいる相手をひとりの人間として捉えて、どう接していけばいいのか個別に考えるのが大事ということですよね。
そう思います。この話をすると、大抵の聴者はハッとした表情を浮かべるんです。でも理解してもらえると、ぎゅっと距離が縮まります。

挨拶が、扉をあける
——江副さんのお話から、「身近なろう者にもっと話しかけてみよう」とポジティブになる聴者も多いかもしれません。そのときに気を配るポイントはありますか?
「特別な配慮」を意識しすぎなくてもいいと思います。手話ができないなら、筆談で構わない。「配慮しなければ」と考えすぎて、結局、身動きが取れなくなって時間がすぎるなんて、無駄無駄! もったいない(笑)。
——ぼくの母は江副さんと同じろう者なんですが、先日「聴者の友達ができた」と喜んでいて。手紙でコミュニケーションを取っていて、「この間の炊き込みご飯が美味しかったです」とか、そういう些細なやり取りを重ねて仲良くなったらしいんです。
そうそう! そういうコミュニケーションこそが大事なんだと思います。聴者のなかには、手話を使うことは知っていても、話しかけ方すらわからないという人もいますが、決してそんなことはありません。むしろ他愛のない会話が一番大事です。
——その考え方は、あらゆる関係性にも通ずるように思います。
そうかもしれません。ろう者と聴者の関係以外にも、いろんなところに「壁」は存在しますが、それを「扉」に変えるときに重要なのは、「挨拶」だと思うんです。どんな人に対しても、いつでも気軽に挨拶できるかどうか。
——特別なことをするのではなく、「挨拶」からスタートする。
そう、逆に自分のなかに「この人には挨拶しづらい……」という変な思い込みも持ってはいけないとも思います。私がいま付き合っている友達や仕事仲間のなかには、挨拶しづらい人なんていません。まずは気楽に挨拶できる関係を築く。それが「壁」を突破していく手掛かりになると思います。
* * *
「壊す」という手話は、両手を握り親指をくっつけて横に並べ、一本の木を折るようにこぶしを外側に90度回転させて表現します。
江副さんのこの手話の動きはポキッと小枝を折るように軽快。それを繰り返しながら、いくつも「壁」があるならば、どんどん壊していくまでだと、いきいきと語ってくれました。
後半は、江副さんがさまざまな「壁」を、どう「扉」にしてきたのかを、さらに深堀りします。どうぞお楽しみに!

後編にすすむ
【プロフィール】
江副悟史(えぞえさとし)
東京都出身。日本ろう者劇団に入団後、手話狂言や自主公演などに出演。2010年3月までNHK『こども手話ウイークリー』のキャスターを務める。映画『獄に咲く花』で杉敏三郎役を演じる。3.11震災後にネット手話ニュース『DNN』を立ち上げる。2017年より日本ろう者劇団の劇団代表を務める傍ら俳優、講演、手話表現者(国際手話など)、手話弁士、キャスターなど幅広く活動中。