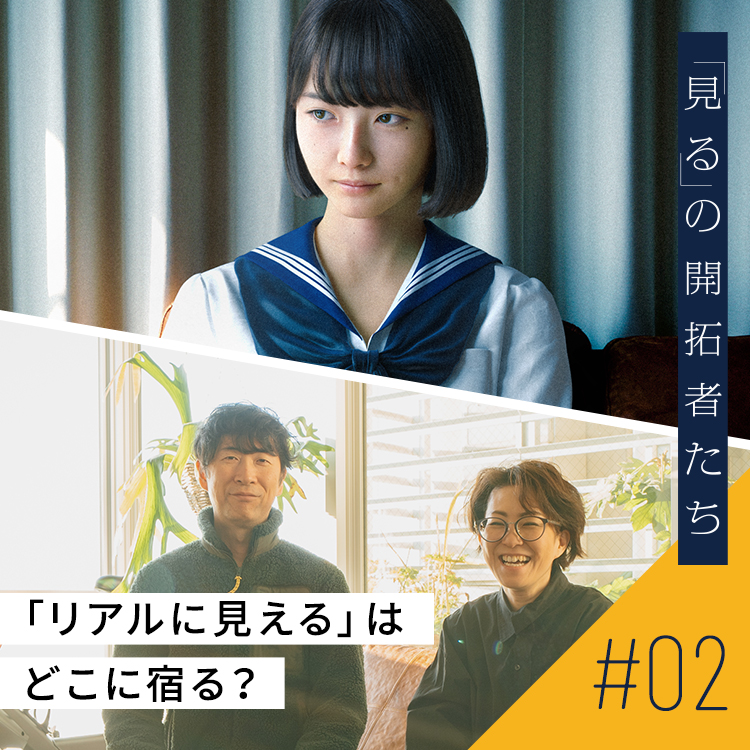「この紙袋、ちょっと使っていい?」
取り出したのは、ご足労いただいたお礼にと編集者Sさんが手渡したお菓子の紙袋。HIRO-PONさんはそのまま、紙袋を意味ありげに目の前のテーブルの上に乗せる。なんだか、マジックが始まる前のような緊張感だ。
「この紙袋から、何が見えますか?」
えっ……お菓子の袋、取っ手、クリーム色の紙、和菓子屋さんの名前とか。
「うん。じゃあ中身は見える?」
…見えません。
「ですよね。でも、これを買ってきてくれたSさんには、中身まで見えていませんか?」
まだ話の脈絡を掴みきれていない編集者Sさんは、すこしためらいがちにうなずく。HIRO-PONさんは、そのまま話し続けた。
「もちろん、いま僕たちに見えているのは、取っ手のついたクリーム色の紙袋だけ。けど、Sさんには、中身であるお菓子やこれを買ったお店の雰囲気、店員さんとのやりとりまで、紙袋を通して『見えて』いますよね。
舞台に立って何かを見せるときも同じ。紙袋を通してお店の様子や中身まで見えてくるように、ただ壁があるように見せるだけじゃなくて、ここに壁があることを通じて『壁以上のもの』を見せていくのが僕らの仕事なんです」

パントマイムが見せる「壁以上のもの」
パントマイムと聞くと、つい壁を触ったり綱引きをする様子を思い浮かべてしまう。けれどもHIRO-PONさんは、そうやって壁や綱が実在するかのように見せかけるだけがパントマイムの仕事ではないと言う。じゃあ、「壁」を通じて見せる「壁以上」のものって……?
「それは、どういう人生を経てその人が壁の前に立っているのか? 壁の前に立ってどんな気持ちでいるのか? そして、これからその人がどうなっていくのか? といった人間の姿を想像してもらうことです。ただの紙袋が、Sさんにお店の雰囲気やお菓子の味、街の風景まで見せられるのであれば、パントマイムアーティストも見えない壁や綱を使って、その前にいる人間の姿を『見せられる』はず。僕らは『見る』ということを、そう捉えているんです」

見せたいのは「壁」ではなく、その壁の前に立つ人間の姿や複雑な心情。そんな言葉は、筆者がこれまで抱いていたパントマイムに対する既成概念、また「見る」という固定観念をも覆していく。
「壁があることを伝えるだけならば、ジェスチャーゲームと変わらないし、喋って伝えればいい。でも、パントマイムは表層的なジェスチャーではなく、観てくれる人に登場人物の心まで想像させる芸術。僕も、はじめる前はパントマイムがそんなに奥深い世界なんて知らなかった。その奥深さに触れて、『一生、この世界を探求し続けていこう』って決心したんです」
ではHIRO-PONさんは、どうやってそんなパントマイムの奥深さに触れていったのだろうか。 話は、今から数十年前に遡る。

「生きたい」気持ちが拓いた道
HIRO-PONさんがパントマイムの道を志したのは20代なかばのこと。高校卒業後、モラトリアムな日々を送っていた彼は、「20代のうちに自分の生きていく道を決めよう」と考えていたが、月日が経っても何も発見することができないまま、タイムリミットは刻一刻と迫っていた。
そんなある日、それはまるで天啓のように降ってきた。
「ガソリンスタンドのアルバイト中、お客さんを見送ったときにふっと『パントマイムをしよう』って思ったんです。それまで、ちゃんとパントマイムを見たこともなかったし、ダンスの経験があるわけでもなかったのに……。
ホント、どうしてパントマイムだったんだろう? 自己顕示欲はあったから、人前で何かをすることがいいなって思っていた。そして人間関係が苦手だったから、一人でできる表現をしたいっていう気持ちもあった。そうやって日々悶々と考えていたら、ふっと、パントマイムに行き着いてしまったんです」

まるで事故に遭うかのように突然あらわれた、パントマイムアーティストという道。今となって振り返ると、それは若さゆえの向こう見ずな思いつきだったかもしれないが、20代の若者にとっては、ようやく掴んだ手応えのある選択だったという。当時、彼の頭の中には「生きたい」という切実な思いがあった。
「若いころって、『なんで生きているんだろう?』って考えるじゃないですか。そのとき、僕が行き着いたのが、『ほかの人の中で生きる』ことこそ生きる意味なんじゃないか、という答え。たとえば、僕が幼いころに通っていた幼稚園の先生が、今もまだ元気でいてくれているのかは正直わからない。けれど、僕にとって、先生はたしかにこの身体の中で、記憶として生きている。どうせこの世に生を受けたのだから、死ぬまでに多くの人の中で生きてやろう。そう思ったんです」
選択こそ衝動的なものだったかもしれない。でも、その根源にある「生きたい」という欲望は切実なものだった。そうして、熱に浮かされるようにパントマイムにのめり込んでいった彼は、練習スタジオや劇場に足を運びながらその技術を習得していく。猪突猛進に突きすすむ若者は、周囲の人々と比較しても遅すぎるスタートを、必死の練習で取り返そうとしていた。
「背水の陣だったんですよ」
そんなHIRO-PONさんに、もっとも大きな影響を与えたのが、師匠・清水きよしさんとの出会いだった。
「当時刊行されていた情報誌に『1年かけてパントマイムを教えます』という情報を乗せていたのが師匠でした。それを見て、すぐ師匠のもとに飛び込んでパントマイムを教わったんです。
はじめの3ヶ月は身体づくりのために、ずっと基礎トレーニングをしていました。レオタードを着て、鏡越しの自分の身体を見つめているのは恥ずかしかったですね(笑)。でも不思議と、全然苦ではなかった。訓練を通じて早く一人前としての技術を身に着けたくて必死だったんです」

師匠のもとで厳しい訓練に明け暮れた彼は、やがてソロのパントマイムアーティストとして晴れて初舞台に立ち、1999年にケッチ!さんとともに「が〜まるちょば」を結成。NHKなど国内のバラエティ番組だけでなく、BBCをはじめとする海外の番組にも出演し、世界中で人気者となっていった。惜しくも2019年にケッチ!さんは脱退したが、HIRO-PONさんはが~まるちょばという名前を残して再始動。今、ふたたびソロのパントマイムアーティストとして大きな舞台に立っている。
「感じる力」は言葉よりずっと多くを伝える
さまざまなパントマイムの技を駆使しながら、舞台上で人の過去や心までをも見せていくHIRO-PONさん。では、舞台に立っているとき、HIRO-PONさん自身の目には、いったい何が見えているのだろうか? もしかしてその目には、あるはずのない壁や綱が見えているのでは……?
「何も見えませんよ(笑)。壁をつくっていても、綱を引いていても、存在しないものは目に映りません。でも『感じている』っていう意味では、『見て』いるのかもしれないね。

壁があることを見せるためには、僕は『本当に』壁を感じなければならない。ガラスなのかコンクリートなのかによってその触り方も異なるし、向こう側が見えているのか、見えていないのかによって壁に対峙するときの感情も異なります。
僕自身が壁や綱の存在を強く感じることで、お客さんも同じように壁の存在を感じてくれる。そうして、お客さんと共犯関係になってイメージが共有される。だから僕が『本当に』感じることで、お客さんは壁の存在を見ることができる。人間の見る力、感じる力って、すごいんです」
そう話すと、HIRO-PONさんは、テーブルの上から想像上のカップを持ち上げ、口元に持っていき、すこし顔をしかめた。

「今の行動と表情だけでは、何を飲んだかはわからない。でも『なにか不味そうなものを飲んだのかな……』って。じゃあ、こうしたらどうだろう?」
続けてHIRO-PONさんは、何かをひとつまみカップの中に入れてまた一口すする。今度は、少し表情がほどける。
「こうすることで『さっきは苦いコーヒーを飲んだのかもしれない』と思ったでしょ? 人間の感じる力っていうのはすごくて、言葉に出さなくても想像でそういうふうに受け取ってくれる。
もっと言うと、文化圏が変われば今の一連の流れが、『スープに塩を入れた』に変わる可能性もある。想像の余地を残すことで、『コーヒーに砂糖をひとつまみ入れた』という行為に限定されることなく、言葉以上にお客さんに伝わるものが現れてくるんです。
海外で、言葉を使わなくてもコミュニケーションが成り立つ経験は誰にでもありますよね。人は、言葉以外の、いろいろな情報を感じ取ることができるんです」
人間の感じる力は、パントマイムという行為を、言葉以上に雄弁にしたり、繊細にしたりする。その意味で、パントマイムは、人間の力を信じるパフォーマンスといえるのかもしれない。
けれど、それは今の時代に対して逆行する行為ではないのだろうか? テレビを見ていれば、あらゆる背景が言葉による説明で覆い尽くされてしまい、その映像からはどんどんと想像の余地が奪われる。「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視し、すぐに伝わることを求める現代の時間感覚にもパントマイムはそぐわない。
「うん、たしかに時代に逆行しているのかもしれませんね。でもそれって競争相手が少ないっていうことだから、僕にとってはむしろ好都合なんです。
人間って本来いろいろ感じられる力を持っているのに、多くの人はそれを忘れてしまっている。僕も、こうしてパントマイムをやってお客さんの反応を目の当たりにしていなかったら、そんな人間の力を信じられなくなっていたかもしれないね」

どんな時代にあっても、人の感じる力は信じられる。その具体例として、HIRO-PONさんはこんな事例を教えてくれた。
が〜まるちょばの演目には、チャップリンの『街の灯』を下敷きにした作品がある。強盗として指名手配を受けている男が目の見えない花売りの少女と出会い、彼女の手術のために懸命に金を稼ぎ、その費用を用意する。そして目的を果たした男は、警察に捕まってしまう。
次のシーンで舞台上には雪が降り、数年の月日が流れたことが表現される。そして、刑務所から出てきた男は少女と再会する……。
「ある子どもは、その雪を見て『あの雪は汚れた心を洗い流しているんだね』と感想をもらしていました。小さな子どもだって、大人と同じかそれ以上に感じることができている。パントマイムはそうやって、言葉も道具も使わずに、ずっと多くのことを伝えられるんです。
最近のテレビやネットのコンテンツでは想像の余地がなくなっているというけれど、そんな時代に生まれ育った子どもだって、こんな豊かな感性を持っている。まだまだ人間の感じる力というものを信じていいんだと思います」

「今」しかない、表現者が生を受けるとき
ソロになってから、2021年には全国ツアー『PLEASE PLEASE MIME』を実施。また東京五輪の開会式では、ピクトグラムのパフォーマンスを創作し、半世紀ぶりの祭典に華を添えた。
かつて衝動的にはじめたパントマイムで、日本一知られた存在となったHIRO-PONさん。では、20代のころに抱いていた「生きたい」という野望は満たされたのだろうか?
「いえ。自分では、どれだけ他人の中で生きられているかわからないし、どれだけ自分のパフォーマンスが求められているのかもわからない。それに、過去にみんなを喜ばせられたからっていっても、今日それができるかもわからない。パントマイムを生業にするのって、まるで綱渡りをしているような気分。未来もなく、過去もない。いつも『今』しかないんですよ」

「今しかない」それは、舞台に立ち芸を披露する人々にとって、根源的な価値観なのだろう。舞台に立つことができるのは、過去でも未来でもなく、まぎれもない「今」の自分だけなのだから。
「今の僕は、2人から1人になって、これまでやってきたアプローチとはまったく別のかたちでパフォーマンスをしているし、いまだに新たな挑戦を続けています。昔の名前でやっているわけじゃなく、現役でいつも新しいものをつくり続けている。だから、映像ではなく、ぜひ劇場でパントマイムを見てほしいですね」
舞台から届く、息づかいや足音、表情。HIRO-PONさんが「壁以上のもの」を表現するために発する情報は、映像だけではとても受け取りきれない。逆に言えば表現者は、私たちが客席から舞台を見上げることで、本当の意味で「生」を受けるのかもしれない。
「そういえば、この紙袋の中身って本当はなんだったの?」
HIRO-PONさんが紙袋の中に手を入れると、そこに入っていたのは、おいしそうなどらやき。地元で愛され続けてきたお店のものだろうか。あるいは購入するのに1時間は並ぶ人気店。職人さんが一つひとつ丁寧につくっている光景も、目に浮かぶ。
インタビューがはじまったときには、ただの手土産としか思っていなかったのに、HIRO-PONさんとのお話の後では、なんだかそこに「どらやき以上のもの」が見えてくる。
取材後、HIRO-PONさんの後ろ姿を見送りながら、彼が最後に見せてくれたいたずらっぽい笑顔を思い出す。もしかしたら、紙袋を例に出してくれたときからずっと、私たちはパントマイムアーティストが仕掛けた「見る」ことの魔法にかかっていたのかもしれない。

【プロフィール】
HIRO-PON(ひろぽん)
パントマイムアーティスト。ソロ活動を経て、1999年に「が~まるちょば」結成。サイレントコメディー・デュオとして、世界の35カ国以上から招待され公演を行う。現在はデュオ活動に終止符を打ち、HIRO-PONのソロプロジェクトとして「が~まるちょば」を継続。2021年の東京2020オリンピック開会式では、ピクトグラムパフォーマンスの演出・構成を手掛け話題を呼んだ。黄色のモヒカンがトレードマークで、ロック、バイク、革ジャンをこよなく愛する。2023年6月より、新作舞台公演「が~まるちょば シネマティック・コメディー JAPAN TOUR 2023」を全国にて開催。
Twitter:@GAMARJOBAT_H