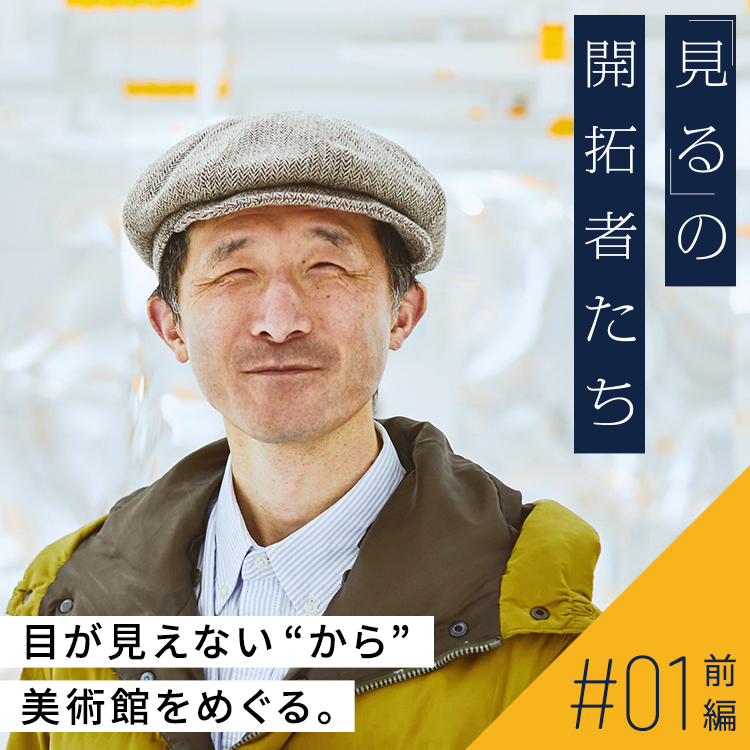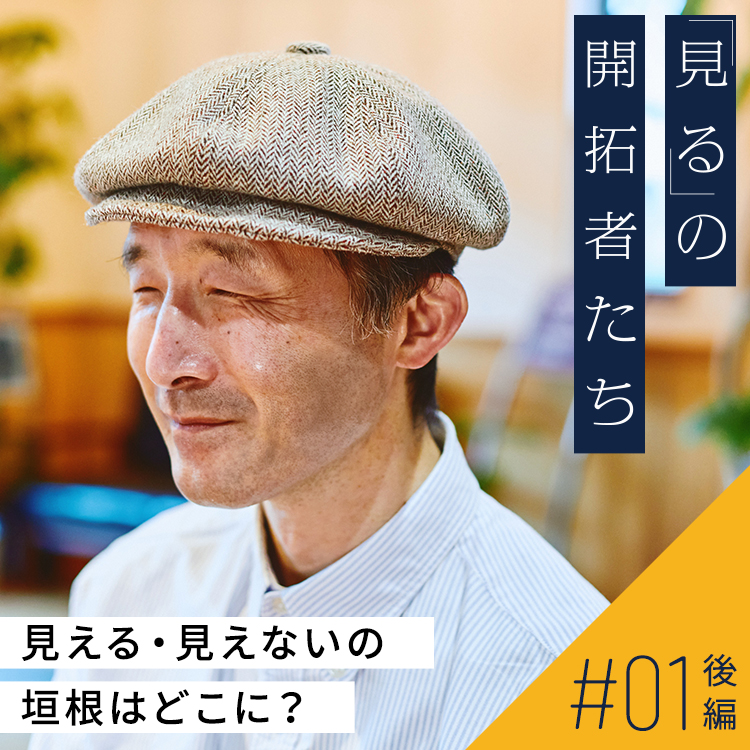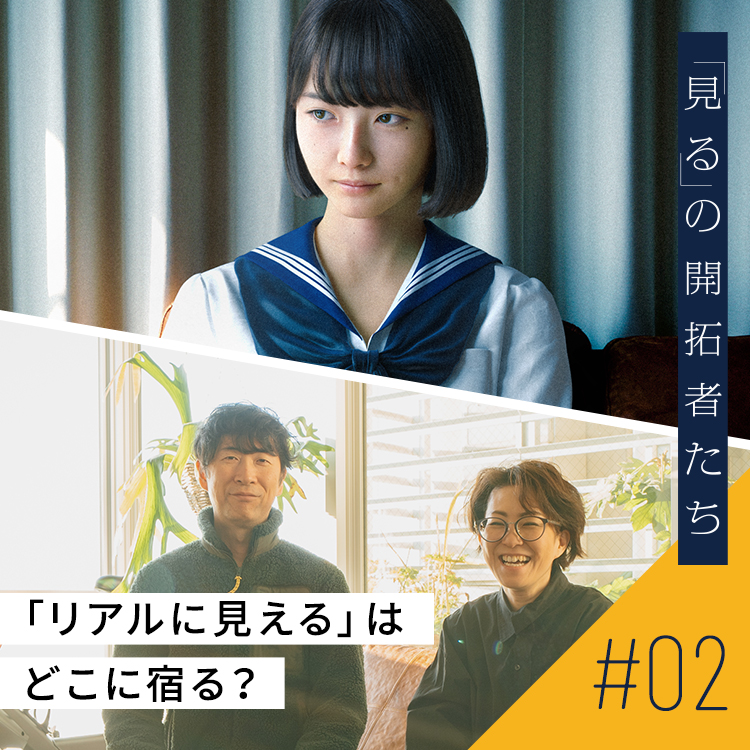緑に囲まれた敷地のなかには、山の高低差を利用した回遊式のユニークな園舎が建つ。まわりの園舎からちょうど谷の部分にあたる園庭を見おろせば、同じ空間に暮らす羊のめえちゃんやブタのトンコちゃん、畑やコンポストトイレまで見渡すことができる。
「あっ、追いかけっこがはじまった」美和さんの声に釣られ、園庭を走りまわる子どもたちにピントを切り替える。つむじ風のように散りぢりになる、黄、水色、緑の帽子。声は聞こえないが、楽しそうな光景にほほがゆるむ。

彼女は普段からここで子どもたちをよく眺めているのだろう。その後も、「あ、〇〇くん、年長の子に触発されているのね。まだ登ると危ない場所に登ろうとしてる」「あの子はこの春から弟が入園して、お兄ちゃんの顔をしてる」と、実況の言葉が続く。
しばらく眺めたあと、園舎の中をぐるりと案内してもらう。音楽室にはジョン・ケージの写真にプリペアド・ピアノ*。建築室には「レゴをより自由に遊べるように」と天板や裏にまで凹凸のついたオリジナルのテーブルが置かれ、図書室の本棚の裏側には隠れ家もある。なんてワクワクする園舎なのだろう。
*プリペアドピアノ……ピアノ内部の弦にゴム、金属、木などを挟んだり乗せたりすることで、音色を打楽器的な響きに変えたもの。

「好きな部屋を子どもたちが自分で選べるように、役割ごとに分けているんです。園庭もぜひ見ていってください」
園舎から外に出ると、たくさんの声が聞こえてくる。土や草木、豚舎のにおい、子どもたちの表情。それらの情報が一斉に押し寄せてきて、先ほどまでのふわふわとした夢見心地はあっという間に流されていった。
「ねえねえ、花びら拾ったよ!」子どもたちのうち1人が、拾ったばかりの花びらを見せてくれる。するとそれを見てか、瞬く間に他の子どもたちが集まってくる。物怖じしない様子にすこし驚きながらも、子どもたちとの和やかなひとときを楽しむ。
この一連の時間は、美和さんが与えてくれた「子どもを見る」ための準備運動だったのかと、園舎に戻り彼女の話を聞くうちに思い至った。

歩んだ場所に「道」はできる
そもそも美和さんは、どのようにして保育の道に入ったのだろうか。園長になるまでの経緯を聞いてみると、意外な答えが返ってきた。
「もともとそこまで子どもが得意じゃなかったんです。だけど大学を卒業してから、短い期間でいろんな変化があって……。夫である紘良(こうりょう)さんの実家のお寺が営み、いまは彼自身が理事長を務めるこの園に入職したのは、2005年のこと。当時はまさか保育にはまるとは思ってもみませんでした」
小学生のころから国語が得意で、そのころにはすでに編集者になることを決めていたという美和さん。大学3年生から編集プロダクションでアルバイトを始め、卒業後はそのまま編集の道に進むことを決意した。
しかし、編集者としての道を歩き始めた矢先に、美和さんの父が急死。心の疲れから仕事を休んでいたが、のちにナナロク社代表となる村井光男さんに誘われて、当時カルト的人気を誇った文芸誌『少年文芸』をつくり始めた。ミュージシャンとして活動していた、のちに夫となる齋藤紘良さんとも、編集の仕事に打ち込むなかで出会ったそうだ。
結婚後はいったん編集業界から離れることになるも、そのとき紘良さんから提案されたのは家業である保育への転身ではなく、なんと「イギリスに語学留学しよう」というものだった。留学なんて夢にも思わなかった美和さんは、その申出に驚きつつも「おもしろいことがおこるかも」と快諾。夫婦で英語と教育について学びながら、現地のアーティストに突撃。取材をしながら出版・音楽レーベルとして自費で雑誌をつくり、海外のミュージシャンの来日公演や国内アーティストの作品リリースも行った。
ようやく美和さんが保育に関わりはじめたのは、約1年の留学を経て紘良さんが本格的にしぜんの国保育園を受け継いでから。ただ担当していたのは、「子育てひろば」という地域に住む人たちを対象とした、子育て支援プログラムの広報や企画の仕事。あくまで最初は紘良さんをサポートするかたちでのスタートだった。

なぜすぐに保育士にならなかったのか。美和さんは「違う業種からきた私は、保育の学校を出ているわけでもなかったので、もちろん保育士資格もない。自信も持てずどこかこわくて、なかなか本腰を入れられないまま『夫の家業を手伝っている』というような気持ちでいたんです」と当時を振り返る。
しかし出産を機に、その「お手伝い感覚」は大きく変化していった。
「私はかなりの難産で、自分の命を守るために子宮を摘出することになって、最初で最後の出産、おそらく最後の子育てになることが決まっちゃったんです。そこで『人生の終わり』を見てしまったからこそ、『自分が関わるみんなに幸せになってほしいな』って思うようになりました。そこからだんだんと『目の前にいる子どもたちのことを見て、もっと知りたい』と意識が変わってきて、ようやく踏ん切りがついた。それで育児をしながら、3年ほど勉強して保育士資格を取りました」
これまでのフィールドとはまったく違う場所で、決心を固めての再スタート。さぞかし覚悟をもって道を切りひらいていったのだろうと思いきや、実際は常に「いま何を大事にするか」に集中していたという。
「学生時代に影響を受けた『道は後からついてくる』という老子の考えがいつも心にあって。保育に携わるようになってからも、先輩方から『こうした方がいい』と言われたことは全部そのとおりやるつもりで取り組んでいました」
そんな地道な積み重ねがあったから、2018年に園長になったときには『私、強くなったかも』と振り返って自分の成長を実感できたという。

『見守る』ばかりでは疲れてしまう
美和さんは園長であり、中学生の子どもを育てる母でもある。仕事でも家庭でも子どもに向き合い続けてきた美和さんは、どのように保育と育児に折り合いをつけ、どのようにその苦労を乗り越えてきたのだろうか。
「『保育』と『育児』は似ているようでまったく違うものなんです。保育は子どもの命を預かる仕事。そのためには保育士としての技術を磨く鍛錬はもちろん、毎日記録を書いて振り返りをしたり、カンファレンスをしたり。子どもを守るプロとしての専門性が必要です。反対に家庭では、子どもと同じ目線でいるために「保育士」にならないように気をつけています。子どもも家にまで「先生」がいたら嫌ですもんね」
「見守る」という言葉は、少し上から俯瞰して見ているような感覚だからこそ、「気をつけて使う必要がある」と美和さんは続ける。
「保育の中で子どもと過ごしていると、いつの間にか自分という存在と、子どもという存在と、それを取り巻く環境や風景が、ごちゃまぜになっていく瞬間があるんです。そのいっしょになっていく感覚がとても好きで。大人と子どもがいっしょにいるときに疲れてしまうのは、きっと大人が子どもを見守りすぎて、コントロールしようとしているときなんですよね。だから家では、親も子も同じ目線でものを見て暮らしていくくらいがちょうどいいんだと思います。
家に帰って疲れてたらスーパーのお惣菜でもいいし、お掃除もサボってもいい。親と子と言えども、ひとつの家庭にある別々の人生の組み合わせ。家族としてはもちろんですけど、一人ひとりの幸せや楽しみもたいせつにしています」
出産をきっかけに考えるようになった「目の前の人を幸せにしたい」という気持ち、そして「いまに集中する」という生き方。ものごとの変化のスピードが速い今の時代、自分の力だけで未来を切りひらこうとすると、かえって焦ってしまい苦しむこともある。美和さんのように「いまに集中し、歩いた場所に道はできる」という心構えがあれば、目の前の幸せにもっと集中できるのかもしれない。

対話を通して暮らしを育む「小さな村」
町田にあるしぜんの国保育園は、別名「small village」と呼ばれている。家族の延長ともいうべき、小さな村。そこには「社会のコミュニティの中で、保育者、保護者、地域みんなで子どもたちを育てていきたい」という思いが込められているという。
「大人がなんでもかんでもやっちゃうと、うるさいだけ。“小さな村”の距離感で、私たち保育者の専門性を活かしながら、子どもとともにどう生きていくのか、思いがけない出来事や、コントロールできないことに直面しながら日々をどう愛していくかを考えています」
たしかに、お互いを近くで見守りやすい“小さな村”だからこそ、一人ひとりの自主性が育つためには、程よい距離感が必要なのかもしれない。一方で「自然の中でのびのびと育つ」ということは、子どもたちが自由気ままに振る舞えることと同義ではないだろう。実際に美和さんはどのようなバランス感覚で、この小さな村を運営しているのだろうか?

「しぜんの国保育園では、子どもたちが環境になじんできたころから、彼ら自身がその日なにをしたいか、今後何をしていきたいか、そして今の気持ちを話す『セッション』をはじめるんです。保育園での生活のほとんどは、このセッションを通して子どもたち自身で考えていて。ここで自分がやりたいことがかなう経験を、どんどん積み重ねていく」
このときに大人がすることは、子どもたちのアイデアを可能な限り叶えられるように動いていくだけ。大人の気持ちを伝えることはあっても、基本的には「子どもたちの気持ちや心を知りたい、聞かせて」という想いをたいせつにする。この距離感こそが、仲間といっしょになって考え、お互いを感じ合い、対話をしながらみんなで答えを見つけていく姿勢を培っていくという。
「たとえば、友だちが体調を崩して遠足に来られなかったとき、同じチームの子から『かわいそうだから、その子のためにもう一度遠足をしよう』というアイデアが出てきて。でもまたバスを使うことはできないからどうしようか? とみんなで話し合っていたら、たっくんという子が『うちに来ていいよ』って言ってくれたんです。お母さんと子どもたちで手紙のやりとりをして許可をもらって、本当にみんなで遠足代わりにたっくんのおうちまで行きました。もちろんアイデアをすべて叶えられるわけではありません。でも子どもたちにとっては、そんな経験も悪くはないと思っていて」
エピソードを聞き、子どもたちの発想の大胆さと、熱量の高さに圧倒される。幼いころ、筆者は自分がやりたいことをここまで伝え、話し合うことができただろうか? ここまで行動に移せたことがあっただろうか? そもそも、こんなふうに考える時間すら与えられていなかったようにも思う。何かを決めるときは、多数決がほとんどだった。
「園では多数決で決めないようにしています。声が大きいほうが勝つのは子どもたちも納得いかないと思うし、数が少ないから諦めるという経験もしてほしくないので。じゃあどうやって決まるのかというと、意外と話し合ううちに場の方向性が自然と定まっていくんですよね。希望が叶えられる経験が積み重なっている子どもたちは、『また今度』があることがわかっているから、『次があるなら今回はいいよ』ってひくことができるんです。だから私たちも『また今度』は絶対回収するようにする。この関係を結ぶことはとてもたいせつにしています」
自分が子どもと、いや人と向き合うときのことを思い返すと、ぐうの音も出ない。この経験があったからいい大人になれる、とまでは言えなくとも、幼児期にこうした体験をすることで、自尊心や他尊心が育まれ、他者と対話しながら答えを見つけていく術が身につくことは想像できる。それはきっと、これからも「小さな村」を生きる、今後の人生においても大きな糧になるはずだ。

近づいたり、引いたり、角度を変えたり。いろんな子どもの見方
とはいえ、子どもと接していると急に不機嫌になったり、思い通りにいかないと泣き出したり、わがままに困らされることがある。そんなとき美和さんならどうするのだろうか。
「まずその子と同じ目線になって、何か言いたいことがあるんじゃないかと想像します。わがままって『自分のあるがままを出す』っていうことでもあると思うので。たとえば音がうるさかったりにおいが気になったり、わがままは意外と環境が要因になっていたりするんです」
たしかに、先ほど園庭を見ていたときも美和さんは、子どもたちが何をしたくて動いているのか、どんな心境で次にどんな動きをしそうか、常に想像しながら状況を把握していた。私も同じようにじっと見ていたはずだが、見えている世界がぜんぜん違うのだ。
「『子どもを見る』っていっても、いろんなピントの合わせ方があって。真正面から向き合うこともあれば、その子が見ているものと同じものを見ようとするときもあるし、俯瞰して司令塔のようになることもある。ほかの人の視点を借りて、同じ子の別の一面を見ることもあるし、見ている私たちが見られる側にまわることもあります。
でも、実は見ることが正解じゃないことも多いんです。ただそばにいるだけのほうがいいときもある。心の距離も、身体の距離も、人それぞれタイミングによっても、絶妙な間隔があるんですよね」

そういえば先ほども、園舎から園庭に移動した途端「子どもたちを見ていた私たち」が、いつの間にか「子どもたちに見られる存在」に変わっていた。なるほど、あの時間は「子どもを見るための準備運動」のように感じていたが、同時に「見られるための時間」「複数の視点を感じる時間」でもあったのか——保育士の目から子どもの視座へ、子どもから鳥のように俯瞰した視点にうつり、ときには目を閉じてそっと寄り添う——こうした視点の切り替えを、美和さんたち保育者たちは頻繁にしているのだろう。もしかするとこんなにたくさんのフォーカスは、読者、著者、編集と視点をずらしていく、編集者としての美和さんに由来しているのかもしれないが。
「それに、子どもが見ている目線に立って物事を見ることで、思い出すことや学ぶものってたくさんあるんです。私たちが世の中に出てから失っていくものって、すごく多くて」
美和さんから話を聞いているとき、「お母さんに会いたくなっちゃった」と園庭の真ん中で急に座り込んで泣きはじめる女の子がいた。また別の場面では、ある男の子がスタッフのひとりに「暑いから持ってて!」と上着を持たせてどこかに走り去ってしまった。
「本当は大人も、泣きたいときは泣いたっていいし、ほしいものはほしいと言っていい。もっと近くの人を頼っていいんです」

遠くを見すぎず、目の前の幸せを見る
現在、都内に3園あるしぜんの国保育園。それぞれに色があるが、理事長である紘良さんのなかでは、町田にある「small village」をより「村らしく」していく構想があるという。今後は隣接するお寺で断食を行える施設や、坐禅と瞑想が体験できる宿坊も開いていくそうだ。
「紘良さんにはいつも豊かなアイデアがあって、やりたいことにあふれているけれど、私自身に展望はあんまりなくて。それこそ子どもたちにも、ただ健康で幸せでいてさえくれたらいいな、って思うだけなんですよね。たとえばサッカーが上手な子がいたら、『じゃあ将来はサッカー選手だね!』なんて言う大人がいるじゃないですか。そこで私は10年後、20年後のことをなんで聞きたがるの? 『今は好き』ってだけでいいじゃんって思う」
たしかにビジョンを持つこともたいせつだが、もしかしたらそれは夢や未来の押し売りかもしれない。
おそらく編集者や経営者の視点をもってすれば、遠くを見ることも解釈することも容易にできるはず。でも一貫して美和さんは、あえてそれをせず、あまり遠くを見すぎずに、視点を切り替えながら、子どもたちの今、自分の今を見つめ続ける。
そうしたまなざしの根っこには、「目の前の人を幸せにしたい」「個々の幸せをたいせつにしたい」といった、終わりを見たからこそわかった「幸せ」への想いがあるのかもしれない。見て、見られて、見守るけれど、見すぎない——育っていく子どもたちの「今」に手を添え、やさしく支える保育園。今日も美和さんはあのおおらかなまなざしで、子どもたちが走り回る園庭を眺めているのだろう。

【プロフィール】
齋藤美和(さいとうみわ)
「しぜんの国保育園」園長。雑誌・書籍の編集者を経て2005年より「しぜんの国保育園」で働きはじめ、2018年に園長に就任。保育業と並行して「北欧暮らしの道具店」「Hugkum」などで、子どもや暮らしをテーマにした執筆やインタビューを行い、2015年に出版した翻訳絵本『自然のとびら』では第5回「街の本屋さんが選んだ絵本大賞」第2位、第7回ようちえん絵本大賞を受賞した。園長をつとめる現在も、夫・齋藤紘良とともに「saitocno」という出版レーベルを運営している。
Instagram:@saitocno_m
Webサイト:https://sizen-no-kuni.net/