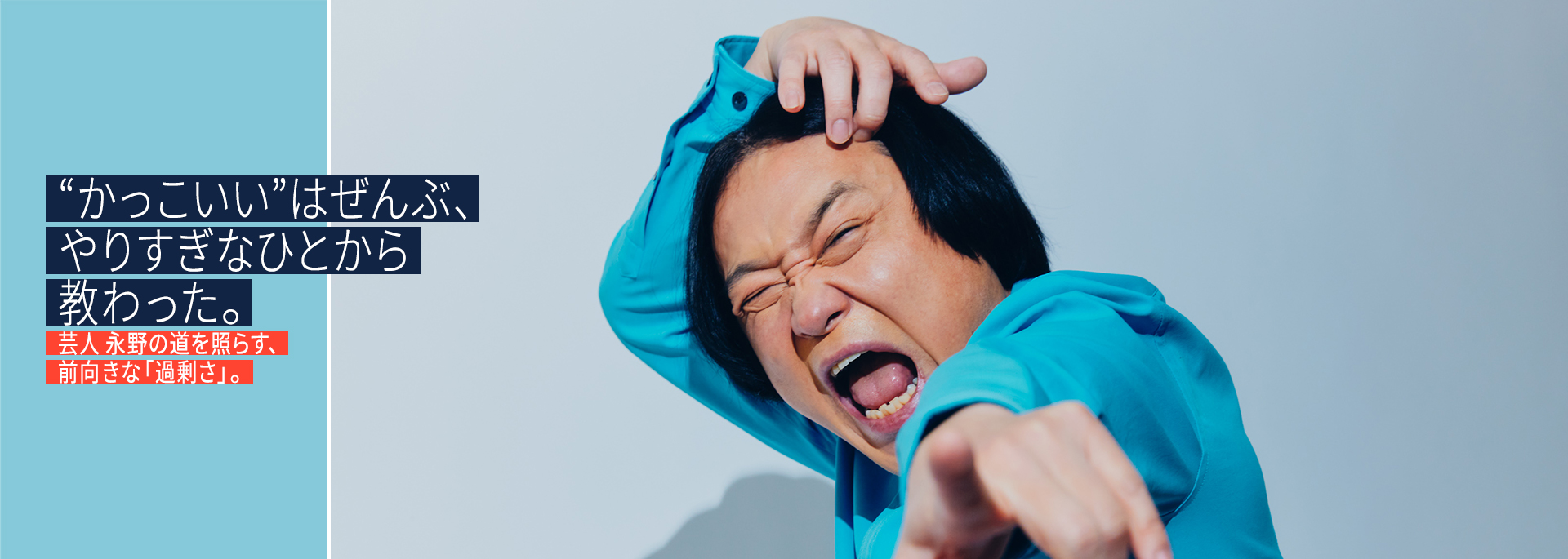「テレビ一択」の時代が終わって、ようやくリアルを表現できた
——永野さんの過剰ともいえる芸風に人気が再燃しています。最近では「だれかtoなかい」「チャンスの時間」など人気テレビ番組での活躍を拝見しました。いまの状況をどのように受け止めていますか?
ほんとうに奇跡だと思っています。「僕たちがここにいるのは奇跡で~」とか言う芸能人がよくいるじゃないですか。ほとんどが「いや、おまえはどっちにしろ売れただろ」とツッコミたくなるやつばかりなんですけど。その点、自分はほんっとうに奇跡なんですよ。
——(笑)。その奇跡はどのように起こったのでしょう。
「ラッセン」でブレイクしてしばらく経ったころから、人気が下り坂になってキツい時期が続きました。潮目がかわったのはコロナ禍ですね。
——仕事の予定がほとんどキャンセルになるなど、苦労も多かったのでは?
いや、むしろ自分は働かなくていいのがうれしくて(笑)。暇になったので、それまで断り続けていたYouTubeの仕事を受けるなどしていました。

——YouTube「永野CHANNEL」では、永野さんのロックに関する持論が話題を呼びました。
「どうせだれも見ないだろう」と期待せずに撮った、自分の大好きな音楽についての話がバズって。ほんとうにびっくりしましたね。
それまではロック好きであることをひた隠しにしていたんです。芸人なのに「ニルヴァーナがー、U2がー」と語るのが恥ずかしくて。だけど、音楽を語るYouTube動画を通じて「こいつ、奇声をあげるだけの芸人じゃないんだ」「意外としゃべれるし、おもしろいじゃん」と言ってくれるひとがいた。業界のひとの目にも止まり、本の出版やラジオの出演に声がかかるようになりました。
——活躍の場がテレビ以外にも大きくひろがったのですね。
そうなんです。テレビ一択の環境じゃなくなりました。いままでテレビではカットされていたリアルな姿をたくさんのひとに見てもらえたのが、ほんとうに大きかったですね。
ラッセンではじめて売れたころ、「テレビの世界へようこそ」と言わんばかりの顔をした“芸能人”たちが「テレビは団体芸だから、勝手なことをするな」「おまえは大声を出して場を盛りあげればいい」とルールを一方的に押し付けてきたんです。テレビ以外に選択肢のなかった当時は、それを真に受けてすっかり萎縮してしまった。でも、落ちぶれたあと冷静に考えてみてわかったんです。「縛られていたルールは、そいつらが気持ちよくなるためのものだった」と。
テレビ一択の世界が崩れたのも追い風になって「どうでもいいわ、好きにやってやろう」と思いました。自由気ままにしゃべってゲラゲラ笑っていたら、その姿が世間にウケていまに至ります。
——つまり、永野さんの芯の部分はずっと変わらないまま、環境の方が変化して奇跡の再ブレイクに至ったと。
そうです、そうです。以前から付き合いのある、ミュージシャンで俳優の金子ノブアキくんが、いまの状況を「みんな、永野さんをあきらめたんですね」と言ってくれました。
——それは「断念する」などのネガティブな表現ではなく、「そのままの永野さんを見るようになった」というポジティブな意味合いでしょうか?
はい。時間をかけてようやく「僕はこういう人間です」と自己紹介できた気分ですね。
テレビのルールを押し付けてきたやつらが突然、ヒロシさんのマネをして必死にキャンプしている姿が滑稽でおもしろいです。焚火しながら「いやされる~」とか言っているけど、平成の芸能界でうまい汁を吸ってきたお前らに息抜きなんか必要ねえだろって。あいつらに森は不要です。

過剰なノリの原点は、高校時代の友だちとの会話
——急所を一撃して倒すような永野さんの言葉のするどさ、毎回おどろかされます。
自分が話す内容は、高校時代の友だちとしゃべっていたようなことなんです。当時から目の前のやつを一発で負かす言葉をずっと考えてきました。だから悪口が湯水のように湧いてくる(笑)。
自分の悪口芸は、ある意味ヒップホップのMCバトルと似ていますね。矢つぎばやに出てくる言葉の強さに笑ってくれよ、と思いながら放っています。
——永野さんが変わらないのは、高校生のころから……。
そう! ずっと変わらないんです。もしかすると、視聴者は「昔、クラスにこんなやついたな」と思いながら見てくれているのかも。
たとえばいま、ここにいるみなさんが高校生だったとして、目の前にサンドウィッチマンがいたら「選挙にでも出るのか」とか思いません? 批判や皮肉ではなく。純粋に。
——サンドウィッチマンさんと永野さんは同じ事務所ですよね(笑)。
はい。こうやって事務所のタレントに対してもめちゃくちゃに言ってしまうので、事務所とはちょっとした緊張感があります。

——永野さんが噛みつく対象は、目上のひとや、自分より売れているひとだと感じるのですが、いかがでしょう?
べつに種明かしするわけじゃないですけど、「自分はみじめです」と一段低い立場から悪口を言うようにしています。いわゆる、弱いものイジメがきらいなんですよ。
ひとをただ傷つけるような芸は絶対にしたくないです。お客さんが悲しい気持ちになるのもいや。純粋にお笑いをたのしもうとしているお客さんを、へんに茶化す芸人なんて許せないですね。
ひとを傷つけないギリギリのラインをねらうのがおもしろいんじゃないですか。そのへんの塩梅には気をつけています。
——永野さんの毒舌が不快ではない理由がわかったような気がします。
あくまで芸というか、ゲーム感覚で適当にしゃべっているだけですからね。悪口を投げた相手ににらみつけられたら、「ウソです! すみませんしたっ!」とすごすご逃げ帰る高校生のノリなんです。正論で相手を追いつめて悦に入っているやつとは種類がちがう。だってそんなの、うすら寒いじゃないですか。

エネルギーに満ちたロックや映画が「かっこいい」を教えてくれた
——永野さんは芸能界きってのロックフリークであり、映画好きでもありますが、いままで触れてきたカルチャーは芸風や生き方に影響していますか?
確実に影響していると思います。なかでも、ロックバンドのギターウルフから受けた影響はおおきいですね。日本でメジャーデビューした1997年からずっと好きです。とにかく言葉がいい。詩人なんですよ。
ギターウルフの歌詞はものすごく簡潔で、「こんな出来事があって、私はこう思った」みたいな長くて細かい説明がありません。
たとえば『カミナリ ワン』という曲に「首都高の夜をカッ飛ばして Hey! 雷見たのさ Baby Rock ‘n Roll Hey!」というくだりがあるんですが、これだけで「空気を切り裂くくらいバイクを飛ばすんだろうな」と目の前に情景がひろがります。「僕はバイクに乗って~」といちいち表現するよりずっと強い。この言葉の強度をエンターテイメントとしてたのしんでいました。

——たしかに言葉のインパクトは、永野さんの強烈なトークとも通じます。
もちろん言葉だけじゃなくて、音楽も、見た目も、アクションも全部がエネルギッシュでかっこいいです。ギターウルフのライブって、メンバーが缶ビールを一気飲みするところからはじまるんですよ。ふつうだったら「ウエっ」とむせそうなものですけど、むせない。ライブ中、革ジャン革パンでずっとパフォーマンスしていて絶対しんどいはずなのに暑がらない。自分が信じる「かっこいい」にまっすぐで、ありえないほどのエネルギーを注いでいるんです。
——ギターウルフの「過剰さ」に惹かれた?
そうです。やっぱり「やりすぎだろう」とつっこみたくなるようなひとや作品が好きですね。
ジャッキー・チェンの1992年の映画『ポリス・ストーリー3』もぶっ飛んでますよ。ミシェル・ヨーがスタントをつけずに、走行中の電車のうえをオフロードバイクで突っ走ったり、ジャッキー・チェンが命綱なしでヘリコプターのはしごに飛び移ったり。人間の限界に挑戦するような映画は、狂った情熱がないとつくれないです。

——永野さんが好きな「過剰」は、言い換えると「尊敬や人気を集めるためにやっていない」「ひたすら好きにやっている」その情熱なんですね。
まさにそうです。ギターウルフのボーカル セイジさんを見ているとわかるんですが、自分の哲学で生きてきたひとは、まわりになにを言われようがびくともしません。
ブルース・リーもそう。彼が31歳のときに受けたインタビュー映像がおもしろい。カナダのテレビ番組のインタビュアーに向かって、めちゃくちゃえらそうにしゃべっているんです。
(背もたれにもたれかかりながら)こーんな感じで踏んぞりかえって。現代よりアジア人に対する差別意識がずっとひどく、肩身が狭かった時代にですよ。身のほど知らずというか恐れ知らずというか。セイジさんにしろ、ブルース・リーにしろ、自分に自信があるから揺るがない。その感じに憧れます。
だから、逆のスタイルはほんとうに好きじゃないです。たとえば、ちょっと売れた芸人が、若いころに住んでいた高円寺の安居酒屋で飲んで、その写真をSNSにアップしたりするじゃないですか。「ルーツの高円寺は忘れない」みたいな。忘れろよ高円寺なんて。ウソくさい。
——おっしゃるとおり、最近のSNSには点数かせぎのようなアピール投稿が多いかもしれません。
そうなんですよ。承認欲求の強いやつばかりで窮屈すぎます。自分は売れないころ、チャンス大城さんと「僕たちはやく死なないかな」とか言いながら路上で飲んでいました。2人とも体がつよくて死ななかったんですけど。みじめなあの時代には絶対戻りたくない。それがリアルだと思います。
俺は「立派でいいひと」と言われるよりも、「自分の好きにやりすぎてて、やべぇ」「めちゃくちゃだな」と思われるほうがいい。そういう理想を、ロックや映画の「過剰なひとたち」から教わってきたんだと思います。
——たっぷりお話をうかがって、永野さんの信条に触れられた気がします。最後に、編集長着任の意気込みを聞かせてください!
いまは「自分らしく好きにやる」「やりすぎる」ことが、昔よりもずっとむずかしくなっていると思います。すこし目立っただけでSNSで叩かれて、人格まで否定されてしまう。批判されないようにと保険をかけた表現ばかりが増えて、おもしろいものが生まれにくくなってしまいました。
だけど、こんな窮屈な世の中にも、自分の好きなことにまっすぐで、ついやりすぎてしまうひとたちがいる。この特集では、そんな過剰なひとたちをどんどん紹介したいと考えています。希望が持てなくて悩んでいる若いひとにこそ届いてほしいですね。「ああ、こんなひともいるんだ」と、その存在が光になればうれしいです。
過剰なことって、おもしろいんですよ。ほんとうに。

* * *
撮影のために着用いただいたJINSのメガネがたいへんお似合いだった永野さん。「フィット感と軽さがすごくいいですね」と感心してくださる様子が印象的でした。
永野さんとともに、前向きな「過剰さ」について考える数カ月。その道中には、JINSが目指す「あたらしい、あたりまえ」の創造につながるヒントがきっと転がっているはずです。
編集長・永野さんがお届けする記事をたのしみにお待ちください!