「変わらない」の裏側を見せないという粋
——ハマ・オカモトさんを編集長に迎えて、これからお届けしていく記事のテーマは「続ける、変わる、続ける。」です。この言葉にどんなイメージを持ちましたか?
いわゆる「変わらない良さ」って、たいてい長く続いているからこそ与えられる評価じゃないですか。でも変わっていないように見えて、実は「変わっている」部分もあるはず。「変わらないな」と感じている人はそのことに気付いていないし、わざわざ「実は変わってるんですよ!」と伝える必要もない。水面下での工夫や変化はむしろ表面上では見せない方が、「粋」に当てはまる気もします。
だから今回の「続ける」ために「変わる」部分にフォーカスする、このテーマを深ぼっていきたいなと思いました。自分もOKAMOTO’Sとして十数年やってきて、否応なしに意識してきたことでもあるので、フィットしていますね。

定年のない音楽業界に、「中堅バンド界の若手」でいる意味
——最初の打合せの際に編集部スタッフがOKAMOTO’Sを「中堅バンド界の若手」と絶妙な言い表し方をしていましたね。
ホントその通りですよ。デビューが19歳だったから同世代と比べて早かったし、自分たちのことをあんまり知らない人からすると「なぜかずっといるよね」と思われているでしょう。もう若手と呼ばれるキャリアではないのに、年齢で言えばまだ30代前半。社会における「中堅」ってだいたい30代後半~40代くらいのイメージかと思うので、すごく微妙な立ち位置なんです。昔からよく引き合いに出していますが、KANA-BOON(大阪出身の4人組ロックバンド。10~20代からも人気を得ている)と同い年ですから。彼らが若々しいのか、僕たちがふてぶてしいのか(笑)。
——19歳でのメジャーデビュー。初期はライブやフェスの現場でも最年少だったかと思います。同世代と横並びになってきたなという感覚は、いつくらいから出てきましたか?
黒猫チェルシー(俳優としても活躍している渡辺大知が所属のバンド)のような同時期にデビューした同世代もいるにはいますが、どこにいっても一番下っ端という感覚がなくなってきたのは、SuchmosやYogee New Waves、never young beach(いずれも1990年前後生まれのメンバーから成る人気ロックバンド)とかが出てきたタイミングですかね。だからデビューして5年~6年くらいから徐々に。

——それまでは孤独を感じることもあったのでしょうか?
孤独感というか、同世代の結束感が日本は特に強いじゃないですか。同じ時期にデビューした[Alexandros]([Champagne]という名前でデビューし、のちに改名)をはじめとするひとまわり上の世代の結びつきは強かった。フェスのバックヤードなどで見ていて、ちょっといいな……みたいなことは思っていました。
僕がソロで出て行く、サポートやスタジオ・ミュージシャンとしての仕事になると、もう年上ばっかりですよ。定年がないから、超絶うまいレジェンドたちがずっといる業界です。ようやくここ3年くらいで石若駿くん(King Gnuの常田大希、米津玄師、星野源などの作品にも参加しているジャズ・ドラマー)しかり同世代と一緒に作品を残せる機会も増えてきたので、今までとは少し違う喜びがありますね。
—— 一足デビューが早かった中で、自分たちがこの世代を引っ張っていかねばという使命感はありましたか?
そんなの自分にはおこがましいと思っていたんですけど、7年ほど前に現場で一緒になった先輩のドラマーに言われたんですよね。「もっと貪欲に同世代をレコーディングの現場に引っ張ってきた方がいいよ。それが若いハマくんの役目だと思う。もうちょっとしたら絶対『だれかいい人いますか?』って聞かれる立場になるから」って。
しばらくしたら本当に相談されるようになったので、その際は自分が知っている近しい世代の人を誘うようになりました。それもデビューして5~6年経ってからの話ですね。
「おかしい」ファンに助けられて
——そんな最年少の10代と、「中堅バンド界の若手」となった30代前半の今とでは、仕事への取り組み方は変わってきましたか?
昔は、「これはやりたい」「これはダサく見られそうだからやりたくない」って、自分だけで自分像を作ろうとしていたんです。でも今はむしろ、人に「こういうことも向いているんじゃない?」と言われたことをやりたいと思うようになりました。許容範囲が広がったし、選択肢が増えることが嬉しいと捉えるようになれたというか。「角が取れた」感覚ですかね。
——人から言われることを受け入れられるようになったのはなぜでしょうか?
それはファンの存在が大きいですね。デビュー当時と今では情報伝達量が明らかに違って、SNSを通して良くも悪くも全部届く状況じゃないですか。だから自分のやることがちゃんと伝わっているか、どう見られているかに関して、応援してくれている人の反応が一つの物差しになってきました。みなさんの感想を見て、この方向に行ってもいいんだと確認できたり、引き出しを広げてくれたり。お互いが手のひらの上で転がされているような、いい関係性なんですよ。
——ここまで続けてこられた原動力でもあるし、新しいことにも積極的に取り組める支えにもなっていると。
僕たちをずっと好きでいてくれるって相当懐が深いですよ。愛想もないし、急に音楽性も変わりますし。それを「OKAMOTO’Sらしくていい」と言える方たち。相当助けられていますし、あえてこう言いますけどかなり「おかしい」と思います(笑)。「ファンは自分を映す鏡」ってホントその通り。

旧友と音楽を続けるため、あえて「知らないまま」でいる
——今までのキャリアの中で、OKAMOTO’Sを続けていくために意識的に何かを変えたことってありますか?
音楽的なところで言うと、楽曲の制作についてはボーカル(オカモトショウ)に任せているので、自分から何か言えることはないです。
変えたこと——僕個人としては、メンバーとの距離の取り方がそうですね。いかんせん学生時代にはじめたバンドなので、最初は「友だちでいること」が先にきてしまっていました。好きなものも、性格も、得手不得手もぜんぶわかっている状態。それは決して悪いことではなかったと思います。むしろ、初期の勢いは僕たちのそういった関係によるものも大きかった。
しかし、思ったように自分たちの音楽が広がらないとか、望むような結果が出ないときには、互いにきびしいことも言わないといけなくなります。ずっとなあなあ、仲良しこよしではやっていけない。これからもバンドを続けていくためには、お互いにもっと新鮮味を感じる付き合いをしていく必要があると思いました。
——活動方針や音楽性というよりも、メンバーとの付き合い方の部分なんですね。少し意外なポイントでした。
「やっぱりこいつ面白いな」と思えないと、一緒にいるのはしんどいですし。だから惰性で知ることを一旦遮断! そこからプライベートに全く関心を示さないようにしました。これは大きい変化でしたし、今まで続けてこられた一因だと思います。

——知らずにいることで、逆に風通しを良くするというか。実際にいい流れになりましたか?
すごくいいですよ。ライブのMCで喋っていることをお客さんと一緒にびっくりするみたいな。ボーカルが猫を飼っているのもライブ中に知りました。「お互いのことを知らない」って言葉だけだと仲悪そうに見えますが、自分の知らない側面が出てくることは尊敬に繋がりますし、発見があるのはいいですね。
——OKAMOTO’Sはコンスタントにアルバムも出すし、ライブもずっとやっている一方で、それぞれソロ活動も精力的ですよね。その部分に対して報告や相談などもない?
各々がやることについてメンバーと話し合ったことはないです。僕がバンド以外の仕事をし始めたのが2011年ごろだったので、今振り返るとだいぶ早い。徐々に他の3人も色々やるようになっていきました。今はOKAMOTO’S共有のGoogleカレンダーがあるんですけど、何をしているかはそこで知ります。「ボーカルがミュージカルの曲の和訳? ドラム(オカモトレイジ)は映画撮影? ほー、そんなことしてるんですね」って。
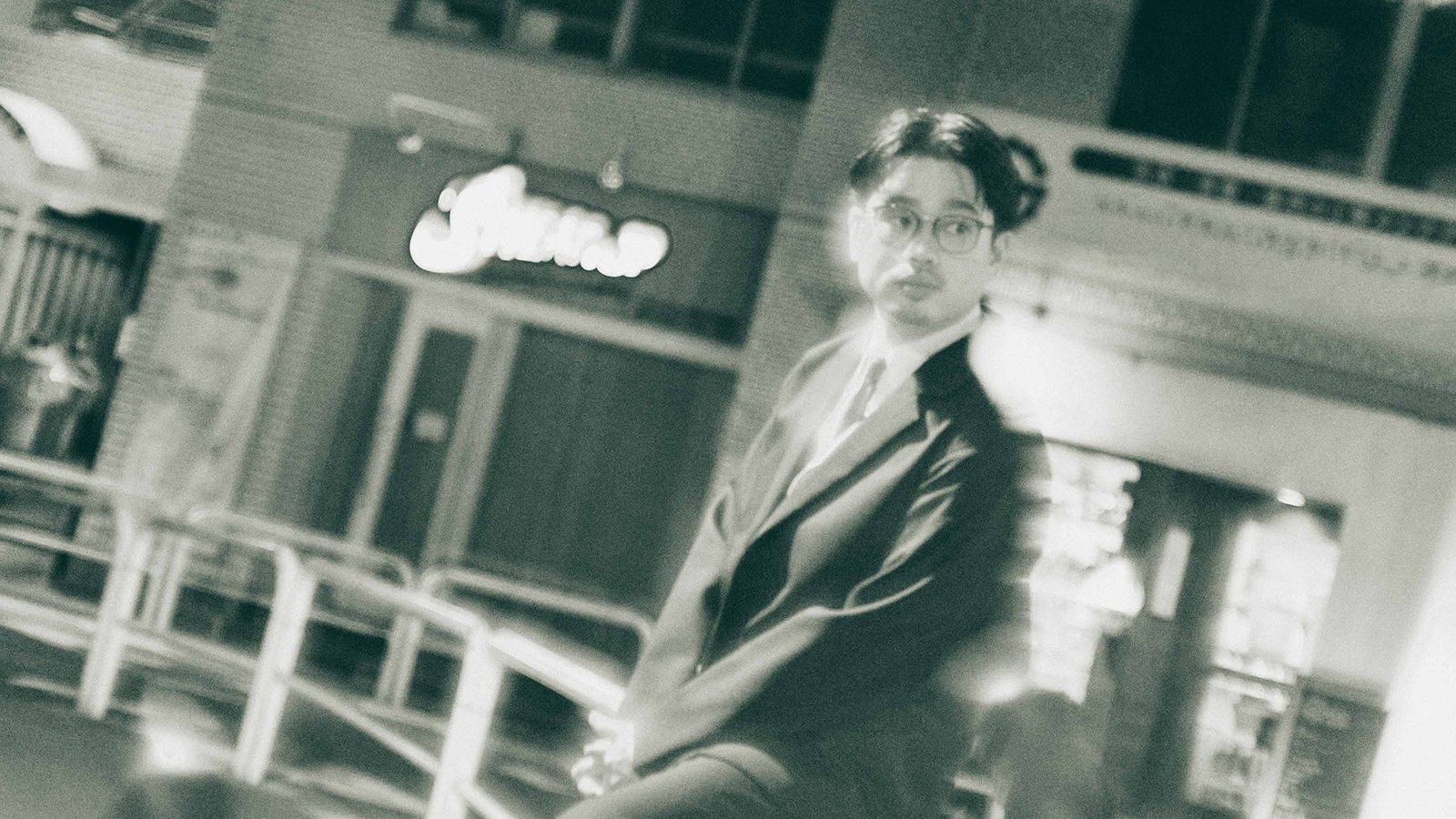
バンドは「甘え」。だから外に出る
——ハマさんは現在、ラジオ『THE TRAD』(TOKYO FM)の水・木曜パーソナリティー、テレビは『ハマスカ放送部』(テレビ朝日)、『沼にハマってきいてみた』(NHK Eテレ)にMCとしてレギュラー出演中ですが、そもそもなぜ音楽以外の仕事にもこれだけ積極的なのでしょうか?
「バンドはボーカルだけじゃない」という信念が学生のころからありましたし、メンバーそれぞれ個性が立っていて、全員の名前が覚えられる存在を目指したかったんですよね。そのために音楽という間口だけで好きになってもらう必要はなくて、バンド以外でもやれることがあれば適材適所でやればいいと思う。
「この人は元々何の人だろう?」という興味からOKAMOTO’Sに繋がることは決してカッコ悪いことじゃないですし。この理想のバンド像は結成する前から友達だったからこそ、4人の中で一致していると思います。
——OKAMOTO’Sとしての活動と、ハマさん個人のラジオ・テレビの活動は今どういう風に影響していると思いますか?
音楽面で直接何か影響することは正直ないです。バンドをやっていると、うまくいかないこともあるじゃないですか。その時にそこしか自分の場所がないと、気持ちが落ちていく一方なんですよ。
でも第一の場所が調子悪くても、第二、第三の場所があれば、そこで気分を取り戻せるというか。好きな子と喋れて嬉しいとか、おいしいもの食べるみたいなことと同じ、シンプルな話です。なおかつ、いかに自然体の自分でいられるかがコツで。
キャラを演じて「ハマ・オカモト」をやるのではなく、今お話ししているこの感じでどの場所にもいられることが、自分の精神的な安定につながっています。それぞれ別の角度から自分を客観的に確認できるし、それがルーティーンになっている。今のバランスは本当に楽しくてありがたいですね。

——複数の役割や居場所があることでメンタル的なバランスが保てるということですね。
はい。あとは自分にとって、バンドは「甘え」なんです。4人で一つの集合体だから責任も分散されていますし、「オカモトズ」なんてふざけた名前で30代に突入しても真剣にやっているって、よっぽどネジが外れた人間という自覚がある。だから公共の電波でお喋りしているとか、日本で一番有名なアイドルグループのセンターだった人と毎週テレビに出ているという、張り詰めた状況があることである意味均衡が取れている (笑)。
——メンタルだけでなく、自分の社会性としてのバランスでしょうか。でもその「バンドは甘え」とは決してネガティブな意味だけではないですよね。
もちろんです。よく「家族」で例えられるのがなんかイヤで「甘え」と言っているのですが、甘えられる場所、最終的に戻るところがあるから、色んなところに出てお喋りできているところはありますね。
——ここまでお話を聞いて、自分がバンドマンであることに対してすごく客観的に捉えられていると思いました。だからこそ他のお仕事とのいいバランスが保てている。
これは僕が歌詞を書いたり、ボーカルだったら、また違う考えだったと思います。自然体でお喋りしている内容と、作詞や歌で伝えるメッセージが相反すると、どちらにも悪影響じゃないですか。自分はベースで、バンドのメッセージを背負っている人間ではない。そこは一貫してボーカルに任せています。いい意味で責任感がないから出来ていることなんでしょうね。
——バンドを代表してラジオやテレビに出ているという意識はない?
ないですないです。あくまで個。他のメンバーよりもメディアへの露出が多いことの驕りで「俺がお前たちの翼となる」とか言い出したらサブいし、履き違えてます(笑)。結果的にバンドを知ってもらえる間口になっているのはいいですけど。

——結果、バンドマンの中ではかなり独自の動き方をされていますが、この今のスタンスにおいて参考にしたり、影響を受けた人はいますか?
その意味でしたら開高健さんですかね。コピーライター、ルポライターと色んなことをやっていた方ですけど、1980年代に『週刊プレイボーイ』で「風に訊け」という読者からの人生相談コーナーを連載されていて、それがすごく好き。お悩みについて解決策を与えるというより、あくまで経験談や持論を述べるだけなんですよ。
例えば、眠ることが大好きだという24歳男性が、ぐっすり寝て目ざめたあと、生きているうれしさを痛いほど感じると書いていて。彼は「目覚めたときのあの充実感がなくなるのが死だとすると、死が恐ろしくてなりません」」と相談するんです(編注:『風に訊け』(集英社文庫、1986年出版)。すると開高さんは「男女が眠りについて寝息だけが聴こえるあの時間のことをフランスのことわざで『小さな死』と呼んでいる。どうでしょう、人生観が変わりませんか?」みたいな感じで答える。
そうかと思えば、「血液型の性格診断を『お信じになりますか?』」という質問に対して「お信じにならない。血は信ずるが型は信じない。おわかりか?」って突き返す。その案配もいいんですよね。
自分を取り繕っていないし、質問した人の思考にあとはバトンを渡すような受け答え。僕の性格的にも、自分も人に何かを伝えたり、影響を与えるのであれば、そういうスタンスでありたいなと思います。
——小説やノンフィクションを多く残している開高さんのワークスの中でも、人生相談コーナーを挙げるところが、今のハマさんの活動の幅広さと重なります。
そうなんです。これが開高さんの本業じゃないんですよ。そう振り返ると僕がおもしろいと思う人って、第二、第三の場所がたくさんある方が多いなとつくづく思います。
リリー・フランキーさんも、僕が学生の頃はテレビや雑誌のコラムでずっとふざけたことを言っているおじさんというイメージでしたけど、その後『東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜』を書かれたり、色んな映画・ドラマに出たり。自分が今やらせてもらっていることは、そこからの影響もあると思います。

ユーモアと真面目さ。緩急のある4ヶ月間に
——今回、ハマさんはJINS PARKの6代目編集長となりますが、これも新しい場所となることを期待しています。
かなり楽しみにしています。JINSがこんな取り組みをされていることは知らなかったので、せっかく携われるんだったら、多くの人に見てほしいですよね。
今日はすごく真面目に話しましたが、最初に打ち合わせさせていただいた時は「メガネをどうにかして食べられないかやりたい」みたいなバカな話もしてたんで(笑)。緩急のあることができればいいなと。自分がこういう風に企画から入る経験は今までも何度かありましたが、基本は単発で終わってしまうので、この貴重な期間を精一杯やりたいと思います。
***
この日の撮影では、JINSのメガネをかけてくださったハマさん。これまでも、JINSをご利用いただいたことはあったのでしょうか?
「ありますよ。メガネをかけている人間として避けて通ることができない存在でしょう。今回フレームを選ばせてもらったんですけど、プライスタグを見て改めてびっくりしました。このクオリティでこの値段なんだって。メガネって回転式のスタンドに刺さっている500円くらいのものから、数十万円するものまで、ブランドも大量にあるじゃないですか。その中でお客さんに選ばれ続けているすごさを感じます」
選ばれるために、過去に捉われず変化することを大切にし、様々なトライをしているJINS。「続ける、変わる、続ける。」を体現するハマさんの姿勢に共鳴して6代目の編集長に就任いただきました。普遍的なテーマであるだけに、ハマさんはどんな人や物事に目を凝らしていくのでしょうか。
今後の記事をどうぞお楽しみに。



